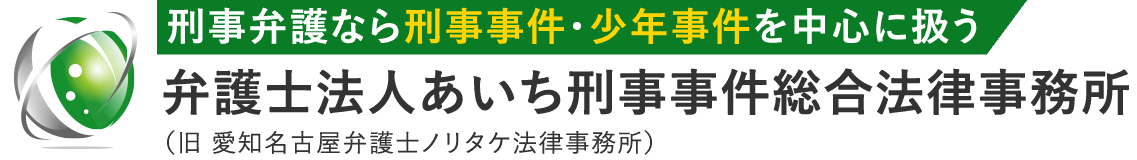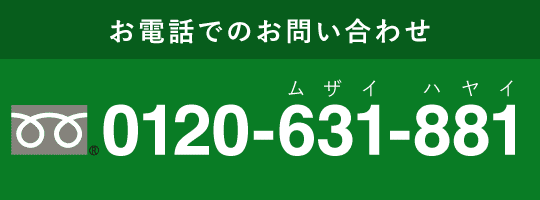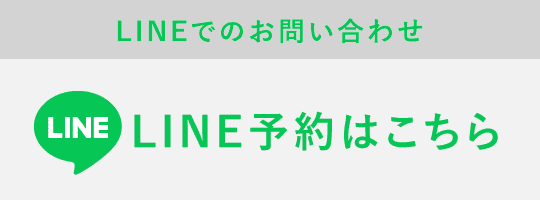Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧め
他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧めについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
名古屋市中区にある社員寮に住むAさんは生活費に困り、ローン無人契約機でお金を借りることを思いつきました。
しかし、Aさんには返済できるだけの財産はなく、Aさんは同じ社員寮に住むBさんに顔が似ていると言われたのを利用してBさんになりすまそうとしました。
AさんはBさんの運転免許証を持ちだし、無人契約機でBさんの運転免許証を提示しAさん名義のローンカードの交付を受けました。
Aさんが「お金を借りるのは後日にしよう。」と思い、社員寮に帰るとBさんが待ち構えており、Bさんは「俺の運転免許証を盗んだだろう。1000万円俺に払えば、愛知県中警察署に言わないでやる。」とAさんに言いました。
Aさんは「確かに自分が悪いのだけれど、それにしても1000万円払えとは言いすぎなんじゃないか。」と思い、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
刑法246条には詐欺罪の規定があります。
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件として
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつこの①~④は繋がっていなければいけません。
つまり、他人になりすまして消費者金融会社の無人契約機でローンカードの交付を受けた場合、これは無人契約機を介して社員が審査したうえで交付しているものですので、消費者金融会社を被害者とする詐欺罪(第1項)が成立します。(最高裁判決平成14年2月8日【一部】)
【1000万円払えと言われました…】
BさんがAさんに「1000万円払え、そうすれば警察には言わない。」と言ったことは、Bさんがいわゆる「示談」で解決しようとしたものだと考えられます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
(今回の事例の場合、Bさんはローンカードの交付を不正に受けた詐欺罪の被害者ではありませんが、運転免許証を盗まれた窃盗罪の被害者になる可能性が有ります。)
一般的には弁護士が加害者の代わりに、被害者と示談交渉を行います。
詐欺罪のように被害者のいる事件では、事件の早期解決を図るための方法としてよく用いられます。
示談交渉のポイントとしては「示談交渉は弁護士にまかせる」ことが大切です。
一般的に詐欺被害者は加害者との接触を避けるため、警察などの捜査機関が被害者に対して「加害者に連絡先を教えてもよいですか」と確認しても、連絡先を教えることを断ることが多いのです。
仮に被害者の連絡先を教えてもらった、または以前から被害者の連絡先などを知っていたとしても、被害者が感情的になるなどして、示談交渉がかえってうまくいかない危険があります。
更に、加害者が被害者と直接示談交渉を行うと、被害者からあまりにも高額な示談金額を要求されることがあります。
弁護士が被害者と加害者の間に入り示談交渉を行うことによって、冷静に交渉を進めることができ、妥当な金額で示談がまとまりやすくなるのです。
また、示談が成立した場合は、示談書を作成することもとても大切です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立した(もしくは示談交渉を行ったが決裂した)ことを警察や検察官、裁判所に対して証明することができないからです。
Bさんが「1000万円」と言った示談金の一般的な相場ですが、詐欺罪は被害者がいる事件ですので一概にこの金額とはなかなか言えません。
ただ、被害総額に加え慰謝料などを上乗せした額であることが多いです。
仮に弁護士を通して誠心誠意Bさんと示談交渉をしても、Bさんがあまりにも高額な示談金額を提示し続けた場合、示談が決裂することもあります。
その場合は示談交渉が決裂に至った経緯を書面にまとめて、警察や検察庁、裁判所に提出することになります。
この書面は、場合によっては示談に準じる効力を有することもあります。
被害者からあまりにも高額な示談金額を提示されてお困りの方はご自分で対応する前に、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人になりすましてローンカードを作った方、被害者に高額な示談金額を提示されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
被拘禁者奪取罪を学校に知られたくない
被拘禁者奪取罪を学校に知られたくないことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
高校3年生ので17歳のAさんが名古屋市南区にあるスーパーに入ると、同級生のBさんが警備員と店員に腕をつかまれているのを見つけました。
Aさんは警備員に対し、「友人だけどなにかあったのですか」と尋ねると、警備員は「私が彼を万引きで逮捕したので今から愛知県南警察署に行きます」と答えました。
Aさんはとっさに「僕が警察署に連れていきます」と警備員に嘘をつき、警備員と店員の制止を振り切ってBさんの腕をとって一緒に逃げました。
2人は、追跡してきた愛知県南警察署の警察官に取り押さえられました。
Aさんの両親は、高校は何とか卒業させたい、学校に知られない方法は無いかと法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
【Aさんはどのような罪に問われますか】
Aさんには「被拘禁者奪取罪」が成立する可能性があります。
被拘禁者奪取罪は、刑法第99条に規定があり
法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
とあり、未遂も処罰されます。(刑法第102条)
「法令により拘禁された者」とは、法的根拠に基づいて国家機関から身体の自由を拘束されている者とされています。
その中には警察官によって逮捕された者のほか、警察官以外の者が現行犯逮捕した者、逮捕段階であり勾留前の者、少年院や少年鑑別所に収容されている者、などがあてはまります。
「奪取」とは、被拘禁者を看守者の実力支配から離脱させて、自己または第三者の実力支配下に移すことです。
Aさんは警備員によって現行犯逮捕されているBさんを、制止を振り切りBさんの腕をとり一緒に逃げているので、被拘禁者奪取罪が成立する可能性があるのです。
(一般人は、通常逮捕、緊急逮捕はできず、現行犯逮捕のみできます。)
【学校に事件のことを知られたくない】
学校に事件のことが伝わるのはいくつかの理由が考えられます。
少年やその保護者が学校に直接連絡した場合を除き
①警察から学校に連絡する場合
②調査官から学校に連絡する場合
の2つが考えらえます。
【警察からの連絡への対応】
全国の都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、警察と学校が連絡を取り合う制度があります。
この制度により、少年や保護者のしらないところで警察から学校に連絡が行き、学校に事件のことを知られるという可能性が有るのです。
しかしこの制度があっても、警察は必ずしもすべての事件について学校に連絡しているわけではありません。
ですので、弁護士は学校に連絡をするべきでは無い事情があるなどの場合は、警察にその旨を申し入れ、学校へ連絡しないように働きかけることも可能です。
【調査官からの連絡への対応】
まず調査官とは、専門知識を活用して非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行う人のことです。
警察が学校への通報を控えた場合には、警察の捜査が終了後に事件が送られる、家庭裁判所もそれに応じるのが一般的です。
しかし再度、弁護士から学校に連絡をするべきでは無い事情などを家庭裁判所の調査官に伝え、学校への連絡をしないように働きかけることが可能です。
【学校に事件のことを知られてしまった】
弁護士が警察などに申し入れをする前に、既に警察が学校に連絡していることも考えられます。
しかしその場合でも、弁護士から学校の校長先生や担任の先生と面談し、少年が更生していることや、少年事件の手続きや理念を説明し、少年を受け入れてくれるように要請することも考えられます。
それでも、残念ながら少年が学校に受け入れてもらえず、退学せざるを得ないケースはあるかもしれません。
その場合は、もちろん転校先を決めるのは少年と保護者の方ではありますが、弁護士からもアドバイスをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が被拘禁者奪取罪で話を聞かれることになった、学校に事件が知られてしまうかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ホテルにおける窃盗事件で逮捕
ホテルにおける窃盗で逮捕された事例を題材に、刑事弁護士が行う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【刑事事例】
Aは、適法に宿泊していたホテル内の備品(ドライヤー等)を、チェックアウトする際にホテルに無断で持ち出した。
愛知県東警察署警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
【窃盗罪か(単純)横領罪か】
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
刑法252条1項は、いわゆる横領罪(単純横領罪・委託物横領罪)を定めた規定です。
これに対し、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
窃盗ではなく横領に当たる場合、上記のとおり横領罪には窃盗罪と違い罰金刑が定められていないため、どちらに当たるのか判断することは被疑者や弁護活動を行う弁護士にとって極めて重要な事項となります。
では、本件では横領罪が成立する余地はあるのでしょうか。
上記252条1項が示すとおり、横領罪が成立するためには被害客体が「自己の占有する他人の物」である必要があります。
ホテルの備品たるドライヤー等は、ホテル側の所有物であることは明らかであり、「他人の物」であることに間違いはありません。
また、Aは金銭を払ってホテル内の部屋に宿泊しているのですから、「他人の物」を「占有」しているともいえそうです。
もっとも、「占有」とは物に対する事実的支配をいうところ、これは社会通念に照らして判断されることになります。
この点、ホテル側が提供した備品はあくまで、宿泊客の利用に供されているだけであり、室内の備品に対する事実的支配は未だホテル側にあると解するのが通常でしょう。
したがって、Aの行為は横領罪ではなく、「他人の財物」をその所有者・占有者の意思に反して「窃取」したものとして窃盗罪を構成することになります。
【逮捕後の弁護活動について】
ここまで、法定刑等の違いに着目した上で、窃盗罪と横領罪の成否について見てきましたが、以下ではより弁護活動に直結する我が国における具体的な事件処理について見てみましょう。
多くの方は逮捕等の身体拘束がされた刑事事件においては、我が国の有罪率が99.9パーセントともいわれることから、ほぼ間違いなく刑罰が下されると思われているかもしれません。
しかし、刑事事件のうち検察官が起訴するのは実はその一部にすぎず、統計上は6割近くが不起訴処分となっています。
つまり、逮捕等がされたとしても、被害弁償や弁護士を通じたその後の対応によって、多くの事件は刑事裁判になることなく終了しているのです。
逮捕・勾留された場合には、(原則として)最大23日間の身体拘束が法律上認められていますが、検察官はこの期間までに起訴・不起訴の判断をする必要があります。
したがって、刑事事件はよくいわれるように時間との勝負に他なりません。
窃盗事件で逮捕された場合も、早い段階から弁護士とのコンタクトをとることが何よりも重要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
多数の刑事弁護士が、日々精力的に刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、まずは24時間/365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
担当者が、弁護士による逮捕されてしまった方との接見(面会)サービス等についてご案内差し上げます。
【解決事例】安城市の詐欺未遂事件で一部接見禁止解除と不起訴獲得
【事案の概要】
ご本人様(20代女性)は特殊詐欺事件の現金受け取り役をしたとして、愛知県安城警察署で逮捕・勾留され、接見禁止がつきました。
ご両親は、一刻も早く娘と面会がしたい、娘は受取った郵便物の中身が詐欺のお金だと知らなかった、受取る荷物は書類だと信じていたと言っていたと、相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
裁判所に対し、①両親と面会をしても罪証隠滅のおそれやその余地がないこと、②両親と面会しても逃亡のおそれがないこと、③家族と面会する必要性が高いこと、④弁護士と被疑事実の打ち合わせを十分行うために必要である、などのため、ご両親との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、ご両親に対して接見禁止等一部解除決定がなされ、ご本人様はご両親との面会や手紙のやり取りができるようになりました。
また、弁護士が検察庁に対し、本人は受取った郵便物の中身が詐欺によるお金であると知らなかった、受取る荷物は書類だと信じていたことから、詐欺の故意や共謀は認められない旨を主張した結果、ご本人様は不起訴処分となりました。
【まとめ】
組織的な特殊詐欺事件など共犯者がいる事件では、勾留時に接見禁止がつくケースが多くなります。
しかし、事件に無関係な家族(配偶者、両親、子供など)に対しては、家族は事件には無関係であることや、面会の必要性を裁判所に適切に主張していくことにより、接見禁止が解除されることも多いのです。
また、ご本人様の行ったことが犯罪にはあたらない、その他、被害者様と示談が成立している、再犯防止の環境が整っている、本人も反省している、などを検察庁に適切に主張していくことにより、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
接見禁止一部解除や不起訴処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
特殊詐欺事件、詐欺事件で家族だけでも接見禁止を解除したい、不起訴処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、接見禁止一部解除の可能性や不起訴処分が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。
業務上横領事件の「横領」行為と弁護活動
業務上横領事件の「横領」行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市名東区内にあるIT企業(V会社)に従業員として勤務していました。
Aさんの仕事内容としては、経理としてV会社の預金(預金口座)を管理することが含まれていましたが、Aさんは約40回にわたり、勝手に会社の預金口座からAさん自身の銀行口座に合計約1億5000万円を送金しました。
その後、V会社が被害を届け出たことで、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「横領した約1億5000万円には一切手を付けていない。何とか被害を弁償したり示談をしたりすることはできないか」と話しています。
Aさんの話を聞いたAさんの家族は、被害弁償や示談を含めた業務上横領事件の対応や、業務上横領罪自体について詳しく聞きたいと思い、名古屋市の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(2020年9月10日に中國新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【業務上横領罪の「横領」とは】
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する(刑法253条)。
前回の記事では、業務上横領罪の条文上にある「占有」について詳細に確認をしました。
今回の記事では、まずは残りの条件について確認していきましょう。
業務上横領罪の「自己の占有」(刑法253条)は、所有者その他の権限者からの委託に基づいてなされている必要があります。
簡単に言うと、その物の所有者などから任されてその物を「占有」しているという委託関係の状態が必要なのです。
業務上横領罪の要件である委託関係は、委任、寄託、賃貸借、使用貸借のような物の保管を内容とする契約のほかに、売買契約や雇用契約などによって発生するものであっても差し支えないと考えられています。
刑事事件例に当てはめて考えてみましょう。
AさんはV会社との雇用契約により、V会社の経理担当としてV会社の預金口座の管理を行っていました。
よって、V会社の預金口座の管理について、AさんとV会社との間には委託関係があったといえると考えられます。
さらに、業務上横領罪に該当する行為は、自己の占有する他人の物を「横領」することです。
業務上横領罪の「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に領得すること、すなわち、「不法領得の意思」を実現するすべての行為をいうと考えられています。
「不法領得の意思」の定義は、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」であるとされています(最高裁判決昭和24年3月8日)。
今回のAさんの刑事事件例で考えてみましょう。
本来、V会社の預金をAさんの口座に送金することは、預金の所有者であるV会社の意思に基づかなければできない行為です。
会社の預金を送金するということは会社の預金を外部に移すということですから、会社の意思に基づかなければできないことは当然であると考えられます。
また、無断でV会社の預金をAさんの口座に送金することは、経理担当の従業員の職務内容には含まれているとは考えられませんから、AさんとV会社の委託関係の範囲を超えることになるでしょう。
それにも関わらず、Aさんは無断でV会社の預金を自分の口座に送金しています。
これは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分を」していたといえます。
よって、Aさんの行為は業務上横領罪の「横領」に該当すると考えられます。
最後に、業務上横領罪は、今まで検討してきた自己の占有する他人の物を横領する行為が「業務上」なされる必要があります。
業務上横領罪の「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であるところ、刑事事件例のAさんの経理担当としての職務は、業務上横領罪の「業務」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。
【業務上横領罪と示談】
会社の金を横領した業務上横領事件を起こしてしまった場合、被害を受けた会社に被害金を返還することが重要な弁護活動の1つとなることが予想されます。
刑事事件例では、Aさんは横領した約1億5000万円には手を付けていないと話しています。
刑事弁護士の活動としては、すみやかにV会社の担当者又は代理人弁護士と連絡を取り、上記の被害金の全額を返還するための交渉を開始するといった弁護活動が考えられるでしょう。
そして、V会社の担当者又は代理人弁護士との示談交渉の結果として示談が締結出来れば、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判になった際の刑罰の重さの判断に際して有利な事情となり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
会社の金を横領した業務上横領事件を起こしてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
業務上横領罪と「占有」
業務上横領罪と「占有」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市名東区内にあるIT企業(V会社)に従業員として勤務していました。
Aさんの仕事内容としては、経理としてV会社の預金(預金口座)を管理することが含まれていましたが、Aさんは約40回にわたり、勝手に会社の預金口座からAさん自身の銀行口座に合計約1億5000万円を送金しました。
その後、V会社が被害を届け出たことで、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「横領した約1億5000万円には一切手を付けていない。何とか被害を弁償したり示談をしたりすることはできないか」と話しています。
Aさんの話を聞いたAさんの家族は、被害弁償や示談を含めた業務上横領事件の対応や、業務上横領罪自体について詳しく聞きたいと思い、名古屋市の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(2020年9月10日に中國新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【業務上横領罪とは】
刑法253条は以下のように業務所横領罪を規定しています。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する(刑法253条)。
業務上横領罪は、被疑者自身が占有(濫用のおそれのある支配)をしている被害者の財物を領得することにより成立する犯罪です。
同じ財産に対する犯罪としては窃盗罪が思い浮かびやすいですが、窃盗罪とは異なり、被害者の占有(事実上の支配)を排除して被害者の方の財物を領得することにより成立する犯罪ではないことが、業務上横領罪の特徴です。
以下では、業務上横領罪が成立するための具体的な要件である「占有」に注目してみましょう。
【業務上横領罪の要件~「占有」】
業務上横領罪の客体(対象)は「自己の占有する他人の物」(刑法253条)です。
まず、V会社の預金が、Aさんにとっては「他人の物」(刑法253条)に該当するということは理解できるでしょう。
業務上横領罪の要件の理解が少々難解な部分は「自己の占有する」(刑法253条)という要件にあります。
業務上横領罪の「占有」(刑法253条)とは、濫用のおそれのある支配力であると考えられています。
濫用するおそれのある支配力を有していればよいことから、業務上横領罪の「占有」(刑法253条)は、物に対する事実的支配に加えて、法律的支配も含むとされています。
法律的支配の分かりやすい例としては、不動産の登記を有している場合が想定できるでしょう。
不動産の登記がある場合、必ずしも不動産に対する事実的支配もあるとは言えませんが、法律的支配があるとして、業務上横領罪の「占有」(刑法253条)に該当するのです。
対して、同じ財産に対する罪である窃盗罪では、「占有」の考え方は物に対する事実上の支配を指すと考えられています。
なお、今回の事例のように、預金を銀行に預けていたという場合には、銀行に預けているお金なのだから、その預金の事実上・法律上支配=「占有」は銀行のものではないかと疑問に思われるかもしれません。
しかし、現在の通説では、預金債権の支配が、性質上金銭その物の支配を同一視できると考えられています。
つまり、銀行に預金しているというケースであっても、その預金を操作できる立場にある場合には、預金に対する「占有」(濫用のおそれのある支配力)(刑法253条)を有していると考えられています(大審院判決大正9年3月12日)。
学説によっては、先に述べたように、銀行に預けている預金は銀行の「占有」のもとにあるとしているものもありますが、現状はこうした考えが通説となっています。
今回の刑事事件例では、AさんはV会社から預金の管理を任されています。
このとき、上記の考え方に照らせば、AさんはV会社の預金口座内の預金について占有(濫用のおそれがある支配)をしていたといえることになります。
刑事事件では、犯罪に当たるかどうかを考える時、この業務上横領罪の「占有」のように、1つ1つ条件の定義を考えた上でそれに当てはまるかどうかを検討し、判断していきます。
自分の行為のどこかどのように犯罪に該当しているのかといったことを正しく把握しておくことも、取調べで意図していない供述をしないようにするなどの防御においては重要なことです。
しかし、こうした検討・判断をするには、刑事事件の経験や知識が必要不可欠ですから、専門家の弁護士の力を借りることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
名古屋市の業務上横領事件でお悩みの場合、刑事事件への対応にお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県犬山市の商標法違反事件で任意同行を相談
愛知県犬山市の商標法違反事件で任意同行を相談
愛知県犬山市の商標法違反事件で任意同行をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県犬山市に住んでいるAさんは、有名ブランドであるXの偽ブランド品を大量に輸入して、近日自分で運営する個人サイトで販売する予定でした。
数日後、愛知県犬山警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、「インターネットであなたの個人サイトを拝見しました。商標法に関連して、販売予定のXの商品で聞きたいことがあります。警察署で詳しく話を聞かせてください。」などと言い、Aさんは愛知県犬山警察署に任意同行することになりました。
(フィクションです)
【商標法(侵害の罪)】
今回Aさんが任意同行される際に警察官から伝えられている商標法という法律には、以下の規定があります。
商標権または専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(商標法第78条)
第37条または第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(商標法第78条第2項)
このようにして、偽ブランド品やコピーした商品などの商標権等を侵害した商品を輸出・輸入・所持・譲渡等した場合、商標法第78条第2項により処罰されます。
1 商標とは
商標法で保護されている商標とは、具体的な商品について使用される標章(人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的若しくは色彩またはこれらの結合、音など)(商標法第2条1項)を指します。
商品だけでなく、役務(いわゆるサービス)についても認められます。
2 犯行の主体
商標権を侵害する行為の主体に特に制限はなく、誰でも行えます。
3 犯行の対象
犯行の対象とされているものは、指定商品、指定商品や指定役務に類似する商品、その商品やその商品の個装に登録商標またはこれに類似する商標を付したものです。
「指定商品」、「指定役務」とは、商標出願にあたり、その商標を使用しているまたは使用を予定している商品や役務を指定する必要がありますが、この指定された商品や役務のことをいいます。
「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいいます(商標法第2条5項)。
類似する商標に該当するかは、商標の見た目(外観)、読み方(呼称)、一般的な印象(観念)の類似性や、取引の実情を踏まえ、総合的に出所混同のおそれがあるのかを取引者や一般の人を基準に判断していくことになります。
4 行為
今回の商標法違反に該当する行為は「所持」で、人が物を保管する実力的支配関係を内容とする行為をいいます。
5 目的
先ほど触れた「所持」については、譲渡、引渡し、輸出のために所持する目的が必要です。
【刑事事件例について】
Aさんは有名ブランドの偽ブランド品を輸入して、販売目的で所持していました。
上述の理由によりAさんには商標法違反の罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
偽ブランド品を所持していても、それを自分で使うためだけに所持していたり、そもそも偽ブランド品であることに気づかなかった・知らなかった場合は商標法違反は成立しません。
例えば、このような事実がある場合には、まずはこのことを客観的な証拠から主張していくことが考えられます。
商標法違反の成立に争いがない場合は、被害者への被害弁償や示談交渉を行うことが大切です。
被害金額が大きくなく、商標法違反や不正競争防止法違反などの同種前科が無ければ被害者との示談成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
仮に裁判になった場合でも、被害弁償や示談成立がされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
また、被害弁償や示談成立がされれば、逮捕・勾留などの身柄拘束を回避できる可能性を高めることができます。
いずれにせよ、弁護士のサポートがあることで有利な結果を得る手助けになりますから、早期に刑事事件に強い・示談交渉に強い弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を数多く行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県犬山市の商標法違反事件で相談をしたい、家族が商標法違反事件で任意同行をすることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
交際あっせん詐欺事件で逮捕されたら
交際あっせん詐欺事件で逮捕されたら
交際あっせん詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、出会い系サイトで、Vさん(愛知県名古屋市守山区在住)に「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」などと虚偽の内容のメッセージを送りました。
これに騙されたVさんは、合計60回にわたり、Aさんの銀行口座に合計3000万円を振込みました。
振込み後もAさんから連絡がなかったため、Vさんは交際あっせん詐欺に遭ったと自覚し、愛知県守山警察署の警察官に被害を訴えました。
その後、Aさんは愛知県守山警察署の警察官により詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月5日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【詐欺罪とは】
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法246条1項)。
詐欺罪は、①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」→②被害者の方の「錯誤」→③被害者の方の「交付行為」→④被疑者の方の「取得行為」という経過を経ることによって成立する犯罪です。
【詐欺罪の各要件】
以下では、詐欺罪の各要件を見ていきます。
詐欺罪の①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」とは、被害者の方が真実を知っていれば財産の交付を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
詐欺罪の②被害者の方の「錯誤」とは、上記①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」により、被害者の方が瑕疵ある意思を有すること(騙されたこと)をいいます。
詐欺罪の③被害者の方の「交付行為」とは、上記瑕疵ある意思に基づいて財産を被疑者の方に移転させることをいいます。
詐欺罪の④被疑者の方の「取得行為」とは、被疑者の方が財産を取得することをいいます。
【詐欺罪と刑事事件例】
以下では、刑事事件例のAさんの行為が上記詐欺罪の各要件を満たすかについて見ていきます。
刑事事件例では、AさんはVさんに「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」などと虚偽の内容のメッセージを送っています。
このメッセージが虚偽であること、すなわち連絡先交換費用を支払っても本当は女性の携帯番号など提供されないという真実を知っていれば、Vさんはお金を支払わなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、詐欺罪の①「欺く行為」に当たると考えられます。
また、VさんはAさんから送られてきた虚偽のメッセージに騙されて、「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」と騙されてしまっています。
ここに、Vさんは詐欺罪の②「錯誤」状態にあったといえると考えられます。
さらに、VさんはAさんの銀行口座に合計3000万円を振込んでいます。
ここに詐欺罪の③「交付行為」及び詐欺罪の④「取得行為」があると考えられます。
以上より、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【詐欺事件と刑事弁護活動】
詐欺事件において有効な刑事弁護活動のひとつとして「示談」があります。
詐欺事件の示談では、Vさんに刑事弁護士を通して正式に謝罪をし、示談金を支払い、被害の弁償を行います。
詐欺事件の示談金としては、振り込まれた金額が手元に残っていればその返還を行った上、一定の慰謝料を支払うのが一般的だといえます。
振り込まれた金額が手元に残っていない場合は、被疑者の方自身が準備するか、ご家族の協力を得て工面する必要があると考えられます。
示談により、執行猶予が得られたり、刑が軽くなったりするため、示談交渉に強い刑事弁護士を選ぶことは非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交際あっせん詐欺事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(後編)
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(後編)
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(前編)の続きとなります。
【遺失物等横領罪の要件(その2)】
遺失物等横領罪を規定した刑法254条を再度引用します。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物等横領罪における「横領」とは、領得行為をいうと考えられています。
すなわち、不法に領得する意思を持って、遺失物等を自己の事実上の支配下に置くことをいうと考えられています。
そして、不法に領得する意思の意義については、物の経済的用法に従って、所有者でなければできない処分をする意思を指します。
刑事事件例について見てみると、Aさんは、本件自転車を持ち去り、遺失物横領事件が発覚する日までの間、本件自転車に乗っています。
こAさんの行為は、まさに本来の所有者でなければできないであろう経済的な使用であり、Aさんは本件自転車を不法に領得しようという意思を持って自己の支配下に置いていたといえます。
よって、Aさんの行為は遺失物等横領罪の「横領」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには遺失物等横領罪が成立すると考えられます。
【遺失物等横領罪と微罪処分】
本件遺失物等横領罪は微罪処分の対象事件に該当する可能性があります。
微罪処分とは、検察官により指定された極めて軽微な事件についてのみ認められた処分であり、検察官に事件の送致をすることなく刑事手続を終局させる処分をいいます。
すなわち、微罪処分となれば警察の捜査段階で事件が終了し、裁判を受けたり刑罰を受けたりということはないということです。
微罪処分については、刑事訴訟法246条や犯罪捜査規範198条1項が以下のように規定しています。
刑事訴訟法246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。
犯罪捜査規範198条1項
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
微罪処分の対象となるのは、通常、犯情が軽微、被害額が僅少で、被害回復が行われ、被害者の宥恕(許し)があり、かつ偶発的犯行であって再犯のおそれがない事件です。
遺失物横領事件も、事情によっては上記微罪処分の対象事件の要件を満たす余地があります。
先ほど触れたように、微罪処分となれば、検察官に事件が送致されないため、当該事件の被疑者の方が起訴されることはありません。
そこで、刑事弁護士を選任し、遺失物横領事件の被害者の方と示談交渉を経て、被害弁償や示談を行うことが重要です。
遺失物横領事件の被害者の方の宥恕(許し)を得ることができれば、検察官へ事件が送検されることなく、刑事手続を終局させることができる可能性があると考えられます。
微罪処分とならなくとも、示談締結の事実は不起訴処分の獲得や刑罰の減軽に有利に働く事情となりますから、いずれにせよ遺失物横領事件の当事者となってしまったら早めに弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
遺失物等横領事件のような微罪処分対象事件を取り扱った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(前編)
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(前編)
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県名古屋市天白区内に住むAさんは、深夜、同市内の路上を歩いていると、1台の自転車(以下、本件自転車と呼びます)が無施錠の状態で路上のわきに放置されていることに気付きました。
Aさんはこの自転車が盗難車で乗り捨てられているのだろうということにすぐに気が付きましたが、「盗まれるやつが悪い」と思い、そのまま自転車を持ち去りました。
後日、Aさんが深夜に本件自転車に乗っていると、愛知県天白警察署の警察官から職務質問を受け、Aさんが自転車を持ち去ったことが発覚しました。
愛知県天白警察署の警察官によると、自転車は本来Vさんが所有していたものであったといいます。
その後、Aさんは愛知県天白警察署の警察官により遺失物横領罪の容疑で取調べを受けました。
(2020年7月30日に千葉日報オンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【遺失物等横領罪の要件(その1)】
刑法254条は遺失物等横領罪を規定しています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
実務では、「遺失物」「を横領した者」には遺失物横領罪、「漂流物」「を横領した者」には漂流物横領罪、「その他占有を離れた他人の物を横領した者」には占有離脱物横領罪というように、名称が区別されることがあります。
遺失物等横領罪の「占有を離れた他人の物」とは、占有(物を事実上支配する)者の意思に基づかずにその占有(事実上の支配)を離れた物で、誰の占有(事実上の支配)にも属していないもの、および、偶然に被疑者の方の占有(事実上の支配)に帰属したものをいうと考えられています。
そして、遺失物等横領罪の「遺失物」や「漂流物」は、上記「占有を離れた他人の物」の例であると考えられています。
つまり、遺失物等横領罪の「占有を離れた他人の物」のうち、占有(物を事実上支配する)者の意思に基づかずにその占有(事実上の支配)を離れた物で、誰の占有(事実上の支配)にも属していないものを「遺失物」といい、その中でも水面又は水中に存在するものを「漂流物」といいます。
その他、「占有を離れた他人の物」の例としては、誤配達された郵便物、隣家から飛んできた洗濯物、誤って多く渡された釣り銭などが考えられます。
これらは、占有(物を事実上支配する)者の意思に基づかずにその占有(事実上の支配)を離れた物で、偶然に被疑者の方の占有(事実上の支配)に帰属したものに該当します。
刑事事件例において、自転車は、本来Vさんが所有していたものであり、Aさん以外の何人かにより盗み取られ、愛知県名古屋市天白区内の路上に放置されていたものです。
これは、Vさんの意思によらずにその占有(事実上の支配)が離れ、何人かの乗り捨て行為を経て、まだ誰の占有(事実上の支配)にも属していないものであると考えられます。
よって、本件自転車は遺失物等横領罪の「遺失物」に該当すると考えられます。
遺失物横領事件では、示談交渉などの弁護活動が考えられます。
弁護士に事件の詳しい事情を話すことでより具体的な弁護活動を聴くことができますから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
遺失物等横領事件のような微罪処分対象事件を取り扱った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の遺失物等横領事件と微罪処分(後編)に続きます。
« Older Entries Newer Entries »