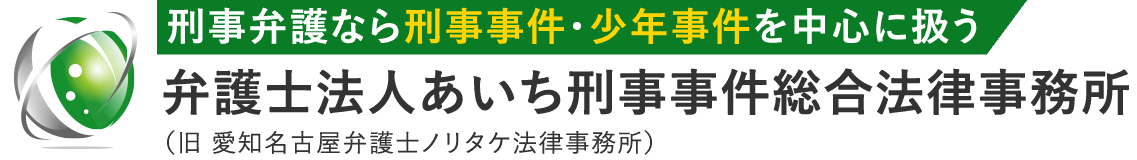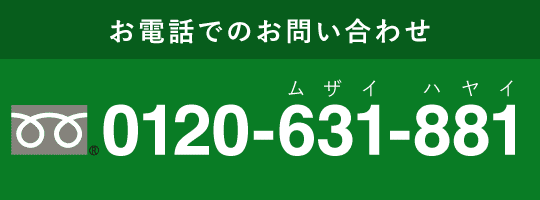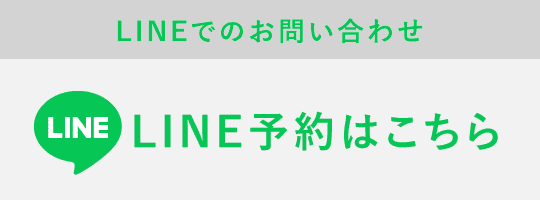Author Archive
弁護士との早期接見で不起訴
痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住むAさんは、満員のJRの快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)
~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。
もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。
~痴漢と逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。
上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。
早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
置引きと逮捕回避
置引きと逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県春日井市に住むAさんは、スーパーマーケットのトイレ内に忘れてあった財布から現金を盗み取りました。Aさんは現場からすぐに立ち去りましたが、警察に発覚するのではないかと不安な日々を過ごしています。Aさんは逮捕を回避することはできないかと考え、弁護士に相談することにしました
(フィクションです。)
~置引きはどんな罪に当たる?~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、「万引き」や「車上狙い」などと同様、窃盗の手口の一部です。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と占有離脱物横領罪では法定刑に大きな開きがありますから、内を基準に両者の適用が区別されるのか気になるところではにあでしょうか?この点、両者を区別するポイントは
被害者の財物(本件ではバッグ)に対する支配が及んでいるかどうか
という点につきます。支配が及んでいる場合にその財物を奪えば窃盗罪、支配が及んでいない場合にその財物を奪えば占有離脱物横領罪が適用されます。
そして、被害者の支配が及んでいるかどうかは、
・財物の特性
・被害者の支配の意思の強弱
・被害者が置き忘れた場所から取り戻しに行くまでの時間、距離関係
などを総合考慮して決められます。
本件では、Vさんのすぐ横にバッグが置かれていたということですから、Vさんのバッグ(やその中身)に対する支配は及んでいるといえるでしょう。したがって、これを持ち去る行為は窃盗罪に当たります(本件では、Vさんが酔いつぶれて意識を失っていた点は考慮する必要はないでしょう。)
~逮捕を回避するには~
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
= 被害者と示談する =
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
= 警察に出頭(自首)する =
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
息子が万引きで逮捕
万引きと留置場での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中川区に住む大学生のA君はスーパーで万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を中川警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは警察官とともに警察署へ行き、留置場へ収容されてしまいました。他方、A君の母親は警察署刑事課の警察官から「A君を万引きで逮捕した。」という連絡を受けました。逮捕の連絡に驚いたA君の母親でしたが、息子が元気でいるか確かめたいと思い、警察官に「息子と接見(面会)したい」と申し出たところ、断られてしまいました。そこでA君の母親は今すぐA君と接見してくれる万引き・刑事事件に詳しい弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 万引きと窃盗 ~
万引きは窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
万引きが発覚すれば逮捕される可能性は大いにあります。
なお、法律上、現行犯逮捕に限り私人(警察官などの司法関係者以外の者)でも可能です。
今回、A君は保安員により現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕されるとその場から警察署に連行され、警察署内の留置場に収容されてしまいます。
~ 留置場とは ~
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
~ 逮捕後の接見(面会)は可能? ~
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制わいせつと出頭拒否
強制わいせつ事件の出頭拒否について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市に住むAさんは、瑞穂警察署から強制わいせつ罪で出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否していたところ逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条で
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
と規定されており、罰則が6月以上10年以下の懲役と比較的重たい罪です。また、出頭→逮捕された場合は日常生活にも支障をきたしますから「できれば出頭したくない」と思うのも当然なことでしょう。
出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、被疑者(Aさん)の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。
被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。
~逮捕と早期釈放に向けて~
仮に逮捕された場合の最策のシナリオを見ていきます。
逮捕後の流れは
①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定
と進んできます。
①逮捕は突然やってきます。
警察は親切にも「今から逮捕に行きます」と教えてくれるわけではありません。
逮捕の際は逮捕状を呈示され、手錠を嵌められます。
その後、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(②)。
そして、警察署で「弁解録取」という手続きを受けます(③)。
その上で警察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
なお、警察官は逮捕の必要があると判断して自ら逮捕したわけですから、その警察官が被疑者を釈放するということは特段の事情がない限りは通常考えられません。
送検後は検察官の元でも「弁解録取」という手続きを受けます(⑤)。
その上で検察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、勾留請求されたと考えましょう(⑥)。
勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られて(送検)から24時間以内です。
勾留請求後は、裁判官による「勾留質問」を受けます(⑦)。
その上で裁判官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。
勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③あるいは⑤の後になると思われます(なお、弁護人以外のご家族などは⑧までは、逮捕された方と接見することができません)。
早期釈放を目指す場合は、接見に引き続き、弁護士と委任契約を締結していただく必要があります。
そうすれば、弁護士は検察官や裁判官に被疑者を釈放するよう働きかけを行うことが可能となります。
勾留されれば10日間という身柄拘束が待っていますから(ただし、不服申し立てにより早期釈放は可能)、勾留前の早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士へご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪と示談
傷害罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市に住むAさんは、Vさんと口論となり、Vさんの顔面や腹部等を足蹴にするなどの暴行を加え、Vさんに加療約1か月間を要する傷害を負わせた傷害罪で久留米警察署に逮捕されてしまいました。逮捕後、Aさんは自分のしたことをひどく後悔し、Vさんに謝罪した上、示談したと考えています。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
まず、傷害罪の規定から分かることは、傷害の対象者は「人」の身体だということです。つまり、「人」以外の動物などを傷害しても傷害罪に問われることはありません(この場合は、器物損壊罪(刑法261条)に問われることになります)。また、「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。打撲、骨折、創傷が「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、めまい、嘔吐をさせる、病菌を感染させるなども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどがその典型といえるでしょう。暴行の故意とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われ得ることになります。他方、傷害の故意とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われ得ることになります。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、例えば、暴行行為により被害者に骨折を負わせたとされても、暴行行為の前に、被害者が別の原因で骨折していたということが判明した場合は、「その行為がなくても結果は発生していた」といえますから因果関係は否定されることになり、傷害罪は成立しないことになります。
本件では、幸いにもVさんの一命は取り留められたようですが、仮に、その後Vさんが死亡した場合、Aさんはどんな罪に問われるのでしょうか?
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これは傷害致死罪と呼ばれる罪名の規定で、Vさんが死亡した場合、Aさんは傷害致死罪に問われる可能性が出てきます。有期懲役の上限は20年(刑法12条1項)ですから、傷害罪に比べると格段に刑は重くなっています。また、裁判員裁判対象事件であるため、起訴されれば一般人が裁判員としえ裁判に参加することになります。ただし、傷害致死罪の場合も、行為(暴行行為、傷害行為)と死亡との間に因果関係があることが必要です。したがって、Vさんの入院中に、医師の手術が原因でVさんが死亡したという場合は、傷害致死罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
~示談とは~
「示談」とは、裁判外(話し合い)で、紛争の当事者同士の合意によって事件を解決することをいいます。広い意味で和解といいます。
示談を成立させると、当事者は合意した内容に法的に拘束されます。
つまり、たとえば「BさんがAさんに対して金10万円を払う」という内容の合意をした場合は、AさんはBさんに10万円を支払う義務が生じます。そして、示談書を公正証書で作成した場合、仮にAさんがBさんに10万円を支払わなかった場合は、Aさんはこの示談書を基に財産を強制的に差押えられるなどの強制執行を受ける可能性もあるのです。他方で、上記内容は、「AさんがBさんから合意した金額以上の額を請求されることはない。」という意味も含まれています。
なお、傷害罪の示談金は10万円から50万円が相場ですが、被害者の怪我の程度などにより上記の金額以上となることもあります。
示談は紛争当事者話し合いによって解決するものですから、示談交渉は紛争の当事者同士(加害者、被害者)で進めていくことも可能です。
しかし、Aさんのように身柄を拘束されている場合は物理的に示談を行うことは不可能です。また、Aさんが釈放され物理的に示談が可能となった場合でも、法律の素人である当事者同士では、そもそも感情の縺れなどから示談交渉を進展させることが難しいでしょうし、仮に進展させることができたとしても、有効に示談が成立したかどうかも不明な場合もあります。これではのちのちのトラブルにも発展しかねません。
示談交渉を円滑、適切に進めていくためには弁護士の力を借りた方が無難でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
準強制わいせつ罪と不起訴
準強制わいせつ罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
名古屋市北区に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、北警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが北警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~不起訴~
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。
起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。
不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合、まずは犯人に猛省していただき、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。
不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは痴漢事件、刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春と勾留
児童買春と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市在住のAさんはSNSで知り合った高校2年生のVさんと食事をしました。その後,AさんはVさんをホテルに誘いましたが、Vさんから拒否されませんでした。AさんはVさんに性交渉の見返りとして3万円を手渡し,その日は解散ました。後日,Aの自宅に愛知県瑞穂警察署の警察官がAさんの家に来て,Aさんは愛知県瑞穂警察署に児童買春の疑いで逮捕、勾留されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)」で禁止されてます。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
略
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
Aさんは高校2年生,すなわち18歳未満であるVさんに対して3万円を供与して性交渉をしていますのでAさんの行為は児童買春となってしまうでしょう。
ただし,児童買春は故意犯ですので,児童買春の成立には性交等の相手が18歳未満であるとの認識が必要です。
そのため,相手が18歳未満でないと認識していた場合には児童買春は成立しません。
ただし,相手が「18歳未満かもしれない」という認識でも児童買春は成立してしまいますので,年齢を知らなかったことを主張するにはそれなりの根拠が必要となるでしょう。
たとえば,相手が家族の身分証を使って18歳以上であると詐称していたというような場合には児童買春は成立しないでしょう。
~ 勾留 ~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、令和3年1月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~ 勾留と釈放 ~
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県津島市で強制わいせつ
強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県津島市に住むAさんは,自宅で友人の女性Vさんと飲んでいました。お酒が回ってきたAさんはおふざけのつもりでVさんの太ももを触りはじめました。Vさんが嫌がるそぶりを見せないことから行為はエスカレートし,お尻や胸を揉むなどした上,無理矢理キスしようとしたところで突如Vさんが激怒し,そのまま通報されてしまいました。Aさんは愛知県津島警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは不起訴処分を得たいと考えています。
(フィクションです)
~強制わいせつ~
AさんはVさんの太ももを触り,ついでお尻や胸を揉み無理矢理キスしようとしました。
この行為は強制わいせつ罪(刑法第176条)に問われる可能性があります。
刑法第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「わいせつな行為」とは,被害者の意思に反して他人から触れられたり見られたくない身体の一部に触れたりするなどして被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことをいいます。
具体的には,陰部や乳房,お尻や太ももなどに触れたりもてあそぶ行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
強制わいせつ罪が成立するためには,わいせつな行為を行う手段としての暴行・脅迫が必要です。
この暴行・脅迫は被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければなりません。
ここで注意したいのは,実際に反抗されたとしても,客観的に反抗することが著しく困難であったと認められる限り強制わいせつ罪の成立は妨げられないということです。
強制わいせつ罪を含む性犯罪ではわいせつな行為と手段としての暴行・脅迫が必ずしも別個に存在しません。
例えば,陰部をもてあそぶというわいせつな行為に当たる行為が手段としての暴行としての性格をもつとして,強制わいせつ罪が成立するということもあります。
今回のケースでも,AさんがVさんに行った太ももを触る行為に始まる一連の行為は,強制わいせつ罪にいうわいせつな行為に当たるおそれがあります。
さらに,Vさんの置かれた状況などを考慮した結果,手段として反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行・脅迫の存在が認められれば,Aさんが強制わいせつ罪に問われることが考えられます。
~不起訴~
不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。以下,具体的にみていきましょう。
不起訴は,検察官が下す終局処分の一種です。したがって、不起訴を決めるは警察官でもなければ,裁判官でもなく,検察官です。検察官の元には,警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には,被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば,有利な証拠も含まれています。したがって,検察官は,それらの証拠を総合的に判断して,事件を起訴するか,不起訴にするか判断できる立場にあるのです。
上記のとおり,起訴するか,不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから,その判断の時期も検察官の判断(裁量)に委ねられます。
検察官は,捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし,証拠の収集には一定程度時間を要しますから,終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし,身柄事件の場合は時間的制約がありますから,在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり,その分,終局処分を下す時期も早くなります。
上記のとおり、検察官の元には捜査で収集した様々な証拠が集まります。検察官はそれらの証拠に基づき、起訴・不起訴の刑事処分を判断します。
ここで、検察官が
「証拠関係から裁判(起訴)しても勝てるけど、被疑者を許してやるか~」
と判断した場合は起訴猶予による不起訴となる可能性が高くなります。検察官ときくと感情がない冷徹なイメージかもしれませんがやはり人間です。情はもっています。
そこで、検察官の元に「被疑者を許してやるか~」と思わせるような証拠が集まれば起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性があがります。
「被疑者を許してやるか~」と思わせるような証拠としてインパクトが大きいのがやはり示談書です。したがって、強制わいせつ罪で起訴猶予による不起訴を獲得するためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に示談を締結し、示談書を検察官に提示する必要があります。
なお、検察官が
「証拠関係から裁判(起訴)しても勝てない」
と判断した場合は嫌疑不十分による不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
警察署に自首
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山警察署は犬山市内で発生した人身自動車事故について過失運転致傷事件として捜査を行っていましたが、未だ犯人を特定するに至っていませんでした。
この事故を起こしてしまったAさんは、自首すべきかどうか1人でずっと悩んでいましたが、ついに意を決して弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自首~
自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前にみずから進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告しその処分にゆだねる意思表示のことをいいます。
自首は刑法第42条第1項によって刑の減軽事由とされています。
ちなみに、刑法第42条第2項によって、親告罪については告訴権者に自己の犯罪事実を申告しその措置にゆだねた場合(首服といいます)も減軽事由とされています。
自首や首服は刑の減軽事由ですが、任意的減軽事由にすぎないため、自首等を行ったからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
Aさんは自身が事件の犯人であると発覚される前に自己の犯罪事実を申告しようとしていますが、この場合も「捜査機関に発覚する前」として自首に当たります。
もちろん、犯罪事実がまったく捜査機関に発覚する前に発覚する前であっても自首が成立します。
この他には、捜査機関による質問や取調べの段階で捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合なども自首に当たります。
ただし、被疑者となっている犯罪事実について自身の犯行を認めるような場合は「捜査機関に発覚する前」に当たらなかったり自発的申告でないとして自首が成立しません。
自首の要件である自発性や「捜査機関に発覚する前」に当たるかどうかはかなり厳しく考えられていますので、自首するつもりで警察などに出頭した場合でも実は自首が成立しないといった事態も大いにあり得ます。
このように、自首したところで必ずしも自首減軽が適用されるわけではなかったり、そもそも自首が成立しない場合もあるといったことから、これらをリスクと捉え自首することに消極的になる方が少なからずいらっしゃることかと思います。
しかし、発覚を免れようと逃げ回っていると、万が一にも発覚した場合には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうリスクが高まり、起訴されてしまった際には量刑にも悪影響を与えかねません。
逆に、自首の成否にかかわらず自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容なども考慮しなければなりませんが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となりうるほか、たとえ自首減軽として適用されなくても被疑者に有利な情状として不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
自首することには慎重にならないといけませんが、自首が成立するかどうかという点や自首した後に踏まれることが予想される刑事手続など、どのように対応したらよいのかといったアドバイスを事前に弁護士に相談して受けておくことが望ましいです。
犯罪を犯してしまった方以外でその不安があるにすぎないという場合も、刑事事件に強い弁護士に相談していただくことで疑問や不安を解消することができるかもしれません。
ただし、なるべく早めに対応しなければ捜査が進んで自首が成立しない段階になってしまったり、示談その他の解決に向けた手段をとることが現実的でなくなったりすることもあり得ますので、お早めにご相談していただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
暴行から傷害致死罪へ発展
傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住むAさんは、Vさん、Wさんと同市内の居酒屋で飲んだ後、カラオケに行くことになりました。しかし、カラオケ店に行く途中、AさんとVさんはお金の貸し借りのことで喧嘩となりました。Aさんは、もともとVさんが一向にお金を返さないことに不満を抱いており、さらに今回のVさんとの言動からVさんがAさんにお金を返す気がない、と思いました。Aさんは、そんなVさんがカラオケ代までおごってくれ、と頼んできたことから、Vさんに対する怒りが頂点に達し、「お前いいかげんにしろ!」と言って両手でVさんの胸を勢いよく押したところ、Vさんは酔った勢いも加勢して仰向けに転倒させてしまいました。その結果、Vさんの後頭部を道路の縁石に打ちつけさせ意識不明の状態に陥らせてしまいました。Aさんはパニック状態となっていたため、Wさんの119番通報により、Vさんは駆け付けた救急隊員により病院へ搬送されましたが搬送先で死亡してしまいました。その後、Aさんは、警察に傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 傷害致死罪 ~
傷害致死罪は刑法205条に規定されています。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
本罪は傷害罪(刑法204条)の
結果的加重犯
です。
結果的加重犯とは、
一定の基本となる犯罪(基本犯)の構成要件を実現した後、犯罪行為から行為者(Aさん)の予期しない重い結果が生じたときに、その重い結果について刑が加重される犯罪
のことをいいます。
~ 傷害罪(基本犯) ~
では、傷害致死罪の基本犯である傷害罪をみていきましょう。
同罪は、刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、他方で、傷害致死罪は「3年以上の有期懲役(上限は懲役20年)」ですから、確かに刑が加重されている(重くなっている)ことが分かります。
傷害罪が成立するためには(構成要件)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
~ 「予期しない重い結果が生じたこと」 ~
傷害致死罪が成立するには、さらに、上記要件に加えて
予期しない重い結果(人の死)が生じたこと
が必要です。
「予期しない」という点がポイントで、予期していた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立します。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
予期していたか、予期していなかったかで法定刑に大きな開きがあることがお分かりいただけるかと思います。
~ 因果関係が必要 ~
傷害罪では、暴行行為や傷害行為と傷害との間に因果関係が必要とされましたが、傷害致死罪でも同様に、
傷害と人の死との間に因果関係が必要
とされます。
仮に、因果関係が認められない場合は、行為者に人の死についての責任を問うことはできませんから、傷害罪が成立するにとどまります。
~ ちょっとした暴行でも傷害致死罪に! ~
これまでご説明してきたことからすると、傷害致死罪は、パターン1によっても成立する可能性があるということになります。
つまり、ちょっとした暴行でも、それによって相手方を死亡させ、その暴行と死亡との間に因果関係が認められる場合は、傷害致死罪に問われることがあるということです。
~ 傷害致死罪は裁判員裁判対象事件 ~
傷害致死罪は、一般人も裁判に参加する裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判対象事件で適切な事実認定、量刑をお求めの方は、ぜひ私選の弁護人選任もご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。