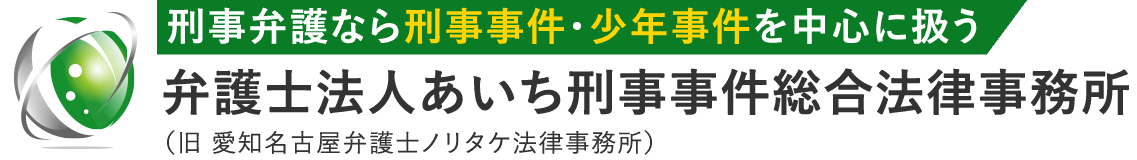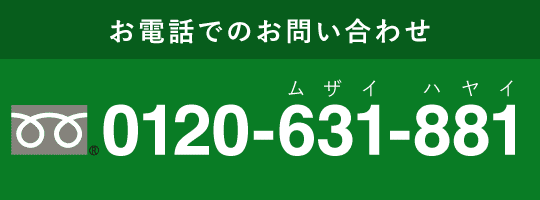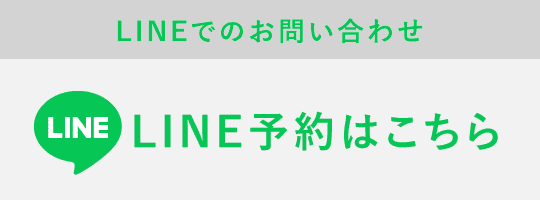Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
スピード違反と赤切符
スピード違反と赤切符について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
Aさんは名古屋市北区の制限速度40km/hの道路を時速85km/hで運転していました。
その道路では、愛知県北警察署の警察官がスピード違反の取り締まりをしており、Aさんの車は停められました。
Aさんは数年前にもスピード違反で止められたことがあり「今回も青い紙をもらって反則金を払うのかな。」と思っていたところ、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので後日警察署に来るように言われました。
(フィクションです)
【Aさんが渡された青い紙と赤い紙】
Aさんが渡された青い紙と赤い紙とは何でしょうか。
青い紙とは青切符、赤い紙とは赤切符のことを指しています。
刑事事件となるのは基本的には赤切符の場合です。
スピード違反の場合について、青切符、赤切符について見ていきましょう。
・青切符
比較的軽い違反に対して交付され、30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の違反です。
青切符も違反ですので本来は刑事上の責任が課されますが、違反を認め通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われず、前科になることはありません。
・赤切符
比較的重い違反に対して交付され、30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の違反です。
赤切符の刑事上の責任については、裁判が行われ、その結果で罰金刑や懲役刑となります。
赤切符の場合違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われます。
【スピード違反の罰則等は?】
スピード違反は正式には速度超過といい、条文はつぎのようになっています。
(道路交通法第22条)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(道路交通法第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
となっています。
【交通事案例について】
Aさんは今回、45km/hの速度超過で検挙されました。
30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度超過の違反であるため、赤切符を交付されました。
数年前のスピード違反の時は青切符だったということですが、その時は30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度超過だったのでしょう。
【スピード違反の弁護活動について】
大幅なスピード違反は、重大な死亡事故・人身事故の原因となる、とても危険な違反です。
スピード違反で裁判になった場合は、スピード違反の危険性についてしっかり自覚し、二度とスピード違反をしないことや、交通ルールに対する意識を改め、贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなどの更生への取り組みを行い、裁判官に反省の気持ちを伝えることになります。
贖罪寄付や反省文の作成をはじめとした更生への取り組みにつきましては、刑事事件や交通事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のスピード違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がスピード違反や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年が共同危険行為の疑いで逮捕されてしまった
少年が共同危険行為の疑いで逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説いたします。
~ケース~
16歳のA君は、知人ら数名と誘い合わせ、愛知県瀬戸市内の県道において、原動機付自転車を大きく蛇行させて運転するなどしていたところ、パトカーで駆け付けてきた愛知県瀬戸警察署の警察官により道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は、少年事件に詳しい弁護士から今後の対応についてアドバイスを受けようと考えています。
(フィクションです)
~共同危険行為とは?~
道路交通法第68条は、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」としています。
これに違反し、有罪判決が確定すると、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第117条の3)。
~少年であるA君の場合はどうなる?~
A君は16歳の少年であるため、少年法の適用があります。
少年事件では、原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送致された後、必要に応じて保護処分を受けることにより事件が終了します。
保護処分には、①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります(少年法第24条1項1号~3号)。
審判が開かれた場合は、A君に対して保護観察処分、または、少年院送致が言い渡される可能性が高いでしょう。
保護観察処分が、在宅で保護観察官及び保護司による指導、支援を受けながら更生を目指す保護処分であるのに対し、少年院送致は、少年院に少年を収容した上で更生を目指す保護処分となります。
少年院に収容された場合は、特別の場合を除いて外出することができませんので、A君にとって負担の重い保護処分と考えることもできるかもしれません。
弁護活動を行う場合は、A君の将来を考慮し、過度に負担のかかる処分にならないよう、適切な処分の獲得に向けて活動していくことになるでしょう。
~少年院送致を避けるために必要な活動とは?~
例えば、最終的に少年院への送致を避けようとするのであれば、A君を少年院に収容するのではなく社会内で更生させる方が妥当であることを裁判官に納得してもらう必要があります。
今回のケースの場合は、家庭での監護態勢、A君の交友関係を見直し、改善していくことが必要となるでしょう。
ケースの状態のままでは、A君が社会に戻ったのち、再び今回の共同危険行為をした知人らと非行をしてしまうのではないかと予想されるからです。
家庭における監護態勢が十分でない場合や、今回のような非行を行う仲間との関係が続くと思われるのであれば、少年院送致などの処分によって、そういった環境から強制的に切り離す措置が取られる可能性が高まります。
もっとも、上記のような環境調整は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、十分な時間をかける必要のある弁護活動です。
少年が1人の人間である以上、両親との関係や、ケースの非行を行った仲間との関係を見直すためには、弁護士を始め、周囲の支援が重要となります。
十分な時間をかけるためには、逮捕された段階からでも環境調整を行うべきです。
少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、少年審判に備えて活動を行うことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
お子様が共同危険行為の疑いで現行犯逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
ひき逃げ、当て逃げの違い
ひき逃げ、当て逃げの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、ひき逃げ事故を起こしたとして過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさん妻は、交通事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ひき逃げと当て逃げの違い~
「ひき逃げ」は、①車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合(交通事故のうち人身事故があった場合)において、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(以下、救護義務)にもかかわらず、救護義務を果たさなった場合、あるいは、②①の場合において、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるのに、救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です(道路交通法72条1置く)。①の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、②は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条2項)です。
①と②との法定刑は大きく違います。なぜ、このように違いがあるかというと、②の場合は「人の死傷が当該運転者の運転に起因」した場合の救護義務違反の規定で、①の場合よりも悪質であるからです。これが①と②の大きな違いです。例えば、道路脇の影から子供が突然飛び出し(当該車が適法に走っていた際のスピードの制動距離範囲内に飛び込んできた)、怪我を負わせたあるいは死亡させたとします。この場合、通常、子供の死傷が「当該運転者の運転に起因」したとは認められません。よって、この場合、救護義務違反をすれば①が適用されることになります。
言い方を変えれば、自己に過失なく人を死傷させた場合でも救護義務は発生します!から注意が必要です。
なお、よく、ひき逃げと同時に処理される罪として過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)、危険運転致傷(15年以下の懲役)、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)などがあります。危険運転致死傷罪には罰金刑がありませんから、同時に起訴されれば、ひき逃げでも懲役刑を選択されます。過失運転致死傷罪で罰金刑を選択された場合は、ひき逃げでも罰金刑が選択されますが、①の場合、150万円(100万円+50万円)以下の罰金、②の場合、200万円(100万円+100万円)以下の範囲ので刑が科されます。
「当て逃げ」は、交通事故のうち物損事故があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
~ひき逃げ、当て逃げの弁護方針~
ひき逃げの場合も当て逃げの場合も、交通事故を起こしたなどたことの認識(「人を怪我させた死亡させた」、人を怪我させたかもしれない、死亡させたかもしれない」など)がなければ成立しません。そこで、運転者本人から交通事故に至るまでの経緯、交通事故の状況等を詳しくお聴き取りをする必要が出てくる場合もございます。
また、上記のとおり、運転者本人の運転に起因するかどうかで法定刑が異なりますから、客観的証拠から事故の状況を詳しく検討する必要が出てくる場合もございます。
ひき逃げ、当て逃げいずれの場合も、被害者への謝罪、被害弁償が必要である点はいうまでもありません(罪を認める場合)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ、当て逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。ひき逃げ、当て逃げを起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警察署に自首
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山警察署は犬山市内で発生した人身自動車事故について過失運転致傷事件として捜査を行っていましたが、未だ犯人を特定するに至っていませんでした。
この事故を起こしてしまったAさんは、自首すべきかどうか1人でずっと悩んでいましたが、ついに意を決して弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自首~
自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前にみずから進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告しその処分にゆだねる意思表示のことをいいます。
自首は刑法第42条第1項によって刑の減軽事由とされています。
ちなみに、刑法第42条第2項によって、親告罪については告訴権者に自己の犯罪事実を申告しその措置にゆだねた場合(首服といいます)も減軽事由とされています。
自首や首服は刑の減軽事由ですが、任意的減軽事由にすぎないため、自首等を行ったからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
Aさんは自身が事件の犯人であると発覚される前に自己の犯罪事実を申告しようとしていますが、この場合も「捜査機関に発覚する前」として自首に当たります。
もちろん、犯罪事実がまったく捜査機関に発覚する前に発覚する前であっても自首が成立します。
この他には、捜査機関による質問や取調べの段階で捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合なども自首に当たります。
ただし、被疑者となっている犯罪事実について自身の犯行を認めるような場合は「捜査機関に発覚する前」に当たらなかったり自発的申告でないとして自首が成立しません。
自首の要件である自発性や「捜査機関に発覚する前」に当たるかどうかはかなり厳しく考えられていますので、自首するつもりで警察などに出頭した場合でも実は自首が成立しないといった事態も大いにあり得ます。
このように、自首したところで必ずしも自首減軽が適用されるわけではなかったり、そもそも自首が成立しない場合もあるといったことから、これらをリスクと捉え自首することに消極的になる方が少なからずいらっしゃることかと思います。
しかし、発覚を免れようと逃げ回っていると、万が一にも発覚した場合には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうリスクが高まり、起訴されてしまった際には量刑にも悪影響を与えかねません。
逆に、自首の成否にかかわらず自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容なども考慮しなければなりませんが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となりうるほか、たとえ自首減軽として適用されなくても被疑者に有利な情状として不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
自首することには慎重にならないといけませんが、自首が成立するかどうかという点や自首した後に踏まれることが予想される刑事手続など、どのように対応したらよいのかといったアドバイスを事前に弁護士に相談して受けておくことが望ましいです。
犯罪を犯してしまった方以外でその不安があるにすぎないという場合も、刑事事件に強い弁護士に相談していただくことで疑問や不安を解消することができるかもしれません。
ただし、なるべく早めに対応しなければ捜査が進んで自首が成立しない段階になってしまったり、示談その他の解決に向けた手段をとることが現実的でなくなったりすることもあり得ますので、お早めにご相談していただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
忘年会と飲酒運転
忘年会と飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、会社の新年会に参加し、ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り3杯、日本酒約1合を飲みました。その後、Aさんは体がかなり火照っていることを認識し、飲酒運転がいけないことだとわかっていながら、車を運転して自宅に帰る途中、交差点の赤色信号表示に従って車を停止させたところ、お酒の影響でその場で寝てしまいました。Aさんが次に目を覚ましたのは、現場に駆け付けた愛知県緑警察署の警察官に声をかけられたときでした。Aさんは、青色信号になってもなかなか発進しなかったため、この様子を見て飲酒運転を疑った後方の車の運転手に110番通報されたようでした。Aさんは、警察官の飲酒検査の結果、「酒酔い運転」と判断され、その場で道路交通法違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻がAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 忘新年会のシーズンには飲酒運転に気を付けて ~
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。酒気帯び運転に呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば酒酔い運転に問われることはない、と勘違いされている方もおられます。
しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に勘案して決められるのであって決して具体的数値を基準として決められるのではありません。
また、飲酒運転によって人身事故を起こした場合は、道路交通法違反(酒気帯び運転若しくは酒酔い運転)に加えて過失運転致傷罪が適用されるのが通常です。しかし、アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして、人身事故を起こしてしまったと判断された場合は、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。危険運転致傷罪の法定刑は、非常に厳しく「15年以下の懲役」で罰金刑の規定はありません。
これから忘新年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思われます。
飲酒運転をしないよう、ハンドルキーパーを確保するなどして、会場までの行き方、会場からの帰宅方法には十分気を払う必要があります。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
無免許運転の人身事故
無免許運転の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。そうしたところ、名古屋市内の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)
~ 無免許運転 ~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運転を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
~無免許過失運転致死傷罪の弁護活動~
先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。
上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽や執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。
以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
飲酒運転の処分
飲酒運転の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ名古屋市中川区在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、中川警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から中川警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒運転~
飲酒運転が発覚する経緯としては、
・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合
はもちろん、
・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合
など様々です。
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
飲酒運転と人身事故
飲酒運転と人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市千種区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた千種警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。
罰則も異なります。
「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
初犯の飲酒運転の場合は罰金刑で済む場合もあります。
しかし、Aさんのように飲酒運転の前科がある方の場合、再び飲酒運転で検挙されるとほぼ間違いなく正式起訴され、裁判で有罪となれば懲役刑を受ける可能性が高くなるでしょう。
~飲酒運転で人身事故を起こした場合~
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪なども問われ、罰則もさらに厳しくなります。
ともに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定され、前者は法律5条に、後者は法律2条に規定されています。
(過失運転致死傷罪)
法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(危険運転致死傷罪)
法律5条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
過失運転致死傷罪の場合、被害者の怪我がよほど軽くないかぎり、正式起訴され懲役刑を受けるでしょう。危険運転致死傷罪の場合、被害者の化外の程度にかかわず正式起訴され、実刑判決の可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
無免許運転中に人身事故
無免許運転中の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊田市に住むAさん(40歳)は、長年無免許のまま軽乗用車を運転していました。ところが、ある日、Aさんは同市内で自動車を運転中、前方不注意のために自分の前を走っていたVさん(25歳)の車に後ろから追突してしまいました。その結果、Vさんには全身むち打ちになるなどの加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで愛知県足助警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~無免許運転~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運手を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
今回のAさんは、一番最後の「無免許運転過失致傷罪」に問われています。
~無免許運転過失致傷罪の弁護活動~
無免許運転過失致傷罪の弁護活動は被害者に発生した損害を賠償することです。
任意保険に加入されているのであれば、基本敵にまずはその保険会社に対応を委ねることになります。
もっとも、被害者対応を保険会社任せにしておくと被害者の感情を損ね、示談交渉が進展しない、処罰感情が悪化して刑事処分や量刑が重たくなるなどの悪い結果へとつながってしまおそれがあります。
そのため、加害者自らも被害者に対する謝罪、お見舞いなどの対応が必要となってくる場合があるでしょう。
なお、謝罪やお見舞いは義務ではなく、すべてのケースにおいてしなければならないというわけではありません。弁護人とよく話し合って、アドバイスを受けながら行うかどうか、行うとしてどのようなやり方が適当かを決めるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年の無免許運転事件
少年の無免許運転と弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
名古屋市東区に住む16歳の高校生A君は、不良仲間のA2くんらを誘い、自家用車を運転していたところ、愛知県東警察署の警察官の検問により止められ、無免許運転が発覚してしまいました。A君らは任意で取調べを受けた後、親が身元引受人となって帰宅することができましたが、Aくんの親は今後どうなってしまうのか不安に感じています。
(フィクションです)
~無免許運転~
Aくんの行った行為は「無免許運転」という犯罪行為です。
無免許運転は道路交通法という法律に規定されている罪です。
道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお、無免許運転といってもその態様は様々で、
・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転
があります。これらは全て無免許運転となります。
~少年に対する処分~
少年に対してはまずその更正を図ることが目的のため、無免許運転を行ったからといって、ただちに上記の刑罰を科されることは稀です。
通常は、
警察→検察→家庭裁判所
へと事件が送られます。
そして、家庭裁判所において少年審判開始決定がなされた場合、少年院送致、保護観察などの保護処分か、そもそも保護処分を下さない不処分を言い渡されます。
保護観察処分は在宅で行われますが、保護観察所の指導監督・補導援護を受けなければならないので、少なからずAくんにも負担がかかります。
不処分を獲得できれば、上記の様な負担がかかりません。
関係者によるAくんへの働きかけ(説諭、訓戒)や、Aくんの交際関係などを見直したことが家庭裁判所に評価され、保護処分の必要がないと認められれば、不処分となる可能性が十分あります。
まずは、少年事件を得意とする弁護士のアドバイスを聞き、Aくんの将来に及ぼす悪影響が最も少ない、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お子様が無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »