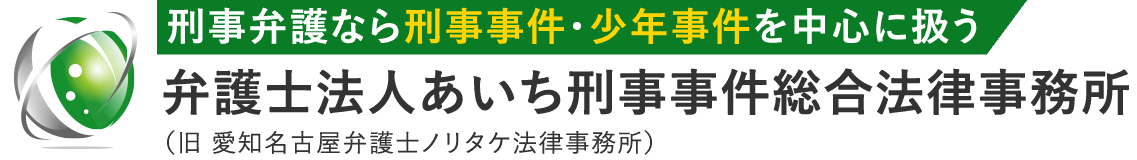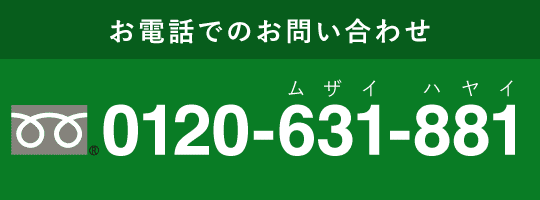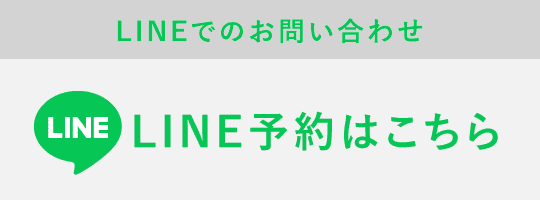Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
物を持ち去っても窃盗罪にならない場合
物を持ち去っても窃盗罪にならない場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは生活に困ったため、刑務所に入りたいと考えていました。
そこでAさんは、誰かの物を持ち去り、すぐに自首して有罪になり、刑務所に入ることを思いつきました。
ある日の夜、Aさんは愛知県犬山市の路上で音楽ライブをしていた、VさんのCDを持ち去り、そのまま50メートル離れた愛知県犬山警察署の交番に持って行って、警察官に「窃盗罪をしたので自首をします」と言いました。
(フィクションです)
【刑事事件について】
AさんはVさんのCDを持ち去っているので、一見窃盗罪が成立するように見えます。
しかしこの場合は窃盗罪は成立しません。
理由などをみていきましょう。
まず、窃盗罪は刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とあります。
窃盗罪が成立するには不法領得の意思が必要とされていますが、不法領得の意思とは、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として」、「その経済的用法に従い利用、処分する意思」のことと言われています。
事例の場合は、Aさんは罪を犯して有罪となり、刑務所に入る目的でCDを持ち去っています。
しかし、一般的にはCDは音楽を聴くためのもの(経済的用法は音楽を聴くこと)です。
Aさんは、CDを持ち去った後は、自首するまでこれを交番に持っていくだけが目的でした。
また、Aさんが目指している「刑務所に入る」という目的は、Aさんが有罪判決を受けて実現するもので、CDを聴いて実現するものではありません。
よって、AさんにはCDを経済的用法に従って利用したり処分する意思が無く、いわゆる不法領得の意思が欠けているのでAさんには窃盗罪が成立しない可能性があります。
ただし、AさんがCDを持ち去った後、自首せずCDを捨ててしまった場合は、CDが使用できなくなるなるため、器物損壊罪が成立する可能性が有ります。
【自首とはどのようなことですか】
Aさんが交番で警察官に伝えた「自首」とはどのようなことか見ていきましょう。
自首とは、事件の犯人が警察等の捜査機関に、自発的に窃盗の事実を申告して処分を求めることです。
自首が成立するには、①捜査機関に窃盗事件が発覚していないこと、②捜査機関に自発的に自己の犯罪を申告すること、が必要です。
この条件が欠けている時は、警察に出向いたとしても自首は成立しません。
自首を行った場合の刑法上のメリットは、刑が減刑される可能性があるというものです。
ですので、必ずしも刑が減刑されるわけではなく、自首による減刑は裁判所の自由な裁量によりなされます。
しかし、自首をすることによって逮捕される可能性が低くなる可能性はあります。
事件ごとに判断され、自首をしたからといって逮捕されなくなるわけではありません。
また、警察など捜査機関がすでに事件や犯人を把握している場合に、捜査機関の呼び出し等に応じて犯人が出向くことを任意出頭といいます。
任意出頭は、自首とは異なり刑法上、刑の減刑等の効果は定められていません。
ですが、任意出頭をするということは、犯人の反省の情を示す事情として判断される可能性があり、有利な情状として取り扱われる可能性があります。
窃盗事件を起こして自首をしようと考えているが、自首をした方がよいのか、そうではないのか、など自首の事でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や自首に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪を起こしてしまった、捜査機関に自首をするべきか悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【名古屋の建造物侵入・窃盗事件】市役所に侵入し、現金を盗む
【名古屋の建造物侵入・窃盗事件】について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
事案:2021年11月、東海市役所に侵入し、現金48万円あまりを盗むなどした事件(メーテレ「市役所に侵入・現金を盗んだなどの罪に問われた男 懲役3年、執行猶予5年の判決 名古屋地裁」(2022年3月28日)より引用)。
【窃盗罪と不法領得の意思】
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定め、刑法38条本文は「罪を犯す意思」すなわち当該犯罪に対する故意を犯罪の成立要件としています。
もっとも、窃盗罪が成立するためには、条文(刑法)に書かれざる要件として「不法領得の意思」が必要であると解されています。
判例(最判昭和26年7月13日)によると、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は書部する意思」がその内容とされています。
本件では、「建造物」たる市役所に無断で「侵入」した上で(刑法130条前段)、報道によるとギャンブルでつくった借金を返済する目的で現金を盗んでおり、上記不法領得の意思が認められることは明らかな事案だと考えられます。
【窃盗事件における弁護活動】
本件で名古屋地裁半田支部は、男に「懲役3年、執行猶予5年」の判決を言い渡しています。
窃盗罪は財産犯ですから、被害弁償によって生じた被害を回復させることがまずは何よりも重要な弁護活動の一つと考えられています。
実際に本件の報道にもあるように、本判決を言い渡すにあたって、酌むべき情状として「被害弁償を行い、前科もない」ことが考慮されていることからも、弁護活動として被害弁償を行うことの重要性は裏付けられていると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
窃盗で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。
借金のかたのカードの使用と詐欺罪
借金のかたのカードの使用と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
AさんはBさんに現金を貸していましたが、その担保としてBさんの母名義のクレジットカードを受け取りました。
その後Bさんから、返済期日までに返済がなかったことから、AさんはBさんとBさんの母に対し、担保にしているBさんの母名義のクレジットカードを使って、返済にあてると伝え、BさんもBさんの母もこれを了承し、クレジットカードの暗証番号を伝えました。
その後Aさんは愛知県清須市にある電気店に行き、Bさんの母名義のクレジットカードを店員に示し、サインを求められたためBさんの母の名前を署名して提出し、パソコンを購入しました。
後日、電気店の店員が、Aさんが男性なのに署名が女性名義なのを不審に思い、愛知県西枇杷島警察署に通報し、Aさんは詐欺罪で愛知県西枇杷島警察署で話を聞かれることになりました。
Aさんは、BさんにもBさんの母にもクレジットカードを使う許可をもらっているのに、何が悪いんだろうと考えています。
(フィクションです)
【詐欺罪は成立するのでしょうか】
今回の場合、AさんがBさんの母名義のクレジットカードを使うことを、Bさんの母が許可している場合に、AさんがBさんの母になりすまして、電気店からパソコンを手に入れていることが詐欺罪にあたるかどうかが気になるところです。
まずは詐欺罪についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条に規定があり
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
とあります。
これは、
「欺く行為」→「錯誤に陥る」→「財産的処分行為」→「財物の交付など」
が、それぞれ関連がある状態で発生することで、詐欺罪となるといわれています。
今回の場合は、クレジットカードというものは、名義人の信用に基づいてその使用が認められているものとされており、結局クレジットカードを使えるのはその名義人に限定されています。
よって、クレジットカードの名義人になりすまして、クレジットカードを使用することは、店舗の間で許可されることはありません。
つまり、クレジットカードの名義人になりすまして、クレジットカードを提示することは、先に述べた「欺く行為」にあたり、詐欺罪が成立することになるのです。
【文書偽造罪については成立しますか】
Aさんがパソコンを購入する際に、Bさんの母の名前を署名していることから、文書偽造罪等も成立すると思われるかもしれません。
しかし、今回の場合は、文書偽造罪等は成立する可能性が低いと思われます。
というのも、文書偽造罪等は、文書の社会的な信頼を保護するのが目的とされています。
つまり、名義人が知らない文書が社会に出回ることを防ぎ、文書の信頼性を保護するためのものです。
今回の場合、文書の名義人(Bさんの母)が、自分の名義の文書の作成(サイン等)を許しているので、実際には文書の名義人が自ら製作した文書と変わらず、基本的には文書の信用性を害することにはならないとされます。
よって、文書等偽造罪が成立する可能性は、ほぼないと思われます。
【刑事事件に強い弁護士への相談】
Aさんのように、自分は特に悪いこと、犯罪になるようなことをしていないと思っていても、実はそれが犯罪になり、いきなり捜査機関から呼び出しを受けるということは、あり得ることです。
もし、そのようなことになった時は、刑事事件に強い弁護士にすぐ相談をしてください。
今後の事件の流れや、取調べへの対策などについて、相談内容をしっかり伺った後、最適なアドバイスをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人のクレジットカードを使用した、自分のしたことが犯罪になると思わなかったとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは違法薬物の売人であるVさんに対し、待ち合わせ場所の愛知県春日井市の路地裏で代金を支払う意思がないのに「ヘロインを売ってくれ」と頼みました。
AさんはVさんからヘロインを受け取りましたが、Aさんは代金支払いを免れるために出刃包丁でVさんの腹部を刺し逃走しました。
Vさんは通行人に救助され一命をとりとめましたが、Aさんは強盗殺人未遂罪と麻薬及び向精神薬取締法違反で愛知県春日井警察署に逮捕・勾留され、その後起訴されていますが、Aさんの家族はAさんが刑務所に行く前に一度自宅に帰ってきてほしいと考えています。
(フィクションです)
【ヘロインとはどのようなものですか?】
ヘロインとは、けしを原料とした薬物のことで、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られており、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。
モルヒネになる前のあへんとは、けしから採取した液を凝固させたもののことです。
原料であるけしの栽培やあへんの採取、あへん及びけしがらの輸出入、所持などは「あへん法」により規制されています。
ヘロインは、強い精神的・身体的依存が特徴の薬物で、ヘロインを使用すると強い陶酔感や快感を覚えます。
しかし、2~3時間ごとに摂取しないと、体の激しい痛み、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状が起こります。
また大量に摂取すると死に至ります。
ヘロインについては、医学的な使用も一切禁止されています。
ヘロインの所持については、麻薬及び向精神薬取締法に規定があり
営利目的が無ければ、法定刑は10年以下の懲役です。
営利目的があれば、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
【強盗殺人未遂罪について】
このような事例については既に判例があり、
「違法薬物をだまし取った後に、代金支払いを免れるために殺人を行おうとしてこれが未遂に終わった場合、代金支払いを免れるという財産上不法の利益をえるためにされたものである以上、この行為は詐欺罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。」とあります。(最高裁判所昭和61年11月18日判決)
※2項強盗とは、刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち直接的な「財物の強取」ではなく、代金の支払い拒否などの「経済的利益を不当に奪い取る」ことを目的として行われる強盗行為のことを言います。
強盗罪が規定されている刑法第236条の「第2項」に規定されているため「2項強盗」と呼ばれています。
【Aさんは自宅に帰ることができるのか】
警察署に留置され、起訴されているAさんが自宅に帰るには「保釈」という制度を利用することになります。
保釈とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度です。
保釈には、必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類がありますが、いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈請求が行われた場合、刑事訴訟法第89条に記載されている事項を除いて、裁判所は保釈を許さなければならないとしています。
刑事訴訟法第89条には
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
とあり、つまりこれに該当しない時は保釈が認められるということです。
ただし、薬物事件においては上記の③と④に該当すると判断される可能性が高いため、特に薬物事件において保釈を希望されるときは弁護士にしっかり主張してもらうのがよいでしょう。
また、上記の89条の保釈が認められなくても、刑事訴訟法第90条に基づく保釈を請求することができます。
刑事訴訟法第90条に基づく保釈とは、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとしていることで、裁判所の裁量により行われる保釈です。
しかし、裁判所の職権で保釈の判断がされるため、これもやはり弁護士に裁判所に対ししっかりと主張してもらうことが大切です。
また、保釈請求が認められたとしても、保釈金を裁判所に預り金として支払わなくてはなりません。
保釈金は仮に後の裁判で有罪判決を受けたとしても裁判所から返還を受けることができますが、保釈金の金額については、人それぞれですので、一概に金額を見積もることは困難です。
また、薬物事件の場合は再犯率や逃走の恐れの観点から、保釈金は高額になる傾向があります。
最後に職権保釈についてですが、職権保釈とは刑事訴訟法第91条に基づいた、勾留による拘禁が不当に長くなった場合には、保釈を許さなければならないというものです。
保釈を希望される方は、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件や強盗殺人未遂罪で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
恐喝罪で示談(謝罪や弁償)をしたい
恐喝罪で示談(謝罪や弁償)をすることを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
17歳のAさんが愛知県瀬戸市の駅前広場を徘徊していたところ、酔っぱらった会社員のVさんが「このガキ、さっさと家に帰れ。」と絡んできました。
これに腹を立てたAさんがVさんに対し「この野郎、ぶち殺すぞ。」と脅迫したところ、身の危険を感じたVさんが自分の懐から財布を取り出し「これで見逃してくれ。」と言いました。
AさんはVさんから財布を受け取り、逃走しました。
後日Aさんは愛知県瀬戸警察署で恐喝罪の疑いで話を聞かれることになり、Aさんの両親はVさんに謝罪や弁償をしたいと考えていますが、Vさんの連絡先も分らず困っています。
(フィクションです)
【恐喝罪、強盗罪と窃盗罪の関係について】
恐喝罪は刑法第249条に
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
Aさんには今回恐喝罪が成立すると思われますが、Vさんを脅迫しているので強盗罪になるのでは?と思われるかもしれませんし
Vさんが差し出した財布を受け取ったので窃盗罪になるのでは?と思われるかもしれません。
それぞれの違いについて見ていきましょう。
①恐喝罪と強盗罪の区別
・恐喝罪が成立する場合
暴行・脅迫の程度が、相手の反抗を抑圧するまでに至らない程度であった場合には恐喝罪となります。
・強盗罪が成立する場合
暴行・脅迫の程度が、相手の反抗を抑圧する程度であった場合には、強盗罪となります。
②窃盗罪と恐喝罪または強盗罪の区別
・窃盗罪が成立する場合
恐喝(強盗)目的以外で暴行・脅迫を加え、その後に暴行・脅迫を加えることなく財物を窃取した場合は、窃盗罪となります。
・恐喝罪・強盗罪が成立する場合
財物を得るために暴行・脅迫を行った場合はもとより、相手の畏怖(恐れおののくこと)を利用して財物を交付させた場合にも成立します。
今回の場合は、脅迫の程度が相手の反抗を抑圧するまでには至らなかったものの、相手の畏怖を利用して財物を交付させているため恐喝罪が成立するのです。
【謝罪や弁償をしたいのに被害者の連絡先がわからない…】
少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談したり謝罪をしたりすることは大切なことの一つです。
示談とは、犯罪の被害者に対して示談金を支払うこと等によって、当事者間で事件を解決することです。
例えば、加害者が被害者に対し謝罪の意思を示すとともに、損害や慰謝料を賠償することによって、被害者が寛大な心で犯罪を許すことなどをいいます。
被害者の方と示談交渉をするためには、まず捜査機関(警察や検察)から被害者の連絡先を聞く必要があります。
しかし、捜査機関から被害者の連絡先を聞けるのは、基本的には弁護士のみです。
加害者やそのご家族の方が、直接捜査機関に被害者の連絡先を教えて欲しいと伝えても、それはとても難しいことでしょう。
ですので、弁護士をつけなければそもそも示談交渉を始めることすら難しいのです。
もちろん弁護士であっても、被害者の連絡先を伝えても良いかどうかは被害者自身が判断しますので、加害者には連絡先を教えたくないと言われることもあるでしょう。
しかし、加害者やその家族ではなく、加害者についている弁護士にならば連絡先を教えても良いと被害者が判断されることも多いのです。
その後の謝罪を含めた示談交渉も、少年事件・刑事事件に強い弁護士にぜひお任せください。
被害者と示談が成立すれば
①事件を早期に解決することが可能となる(事件化する前の場合)
②家庭裁判所での審判の際の判断において有利な事情となる可能性がある
③釈放の可能性が上がる(身柄を拘束された場合)
④損害賠償請求など民事裁判になる可能性を引き下げ、事件の完全解決につながる
など様々なメリットがあります。
被害者との示談をご希望されている方は、少年事件・刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が恐喝罪で話を聞かれることになった、被害者と示談をしたいが連絡先がわからないなどお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
占有離脱物横領罪と示談
占有離脱物横領罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市中村区にある百貨店の7階にある休憩所のソファにカバンが置いてあるのを見つけ、周りに誰もいないことからそのカバンを持ちさりました。
このカバンはVさんのもので、Vさんは7階の休憩所のソファにカバンを置いたものの、そこで地下2階の食料品売り場で買い忘れたものがあることに気付きました。
Vさんはカバンのことをすっかり忘れて、地下2階に向かったのですが、10分後にカバンを置き忘れたことに気付き、すぐに7階に戻ったものの、カバンはすでにAさんに持ち去られた後でした。
後日、Aさんの自宅に愛知県中村警察署から「百貨店の防犯カメラを確認しました。占有離脱物横領罪で話を聞かせてください。」と電話がかかってきました。
Aさんは家族に迷惑がかかるし、被害者に謝罪して示談にできないかと考えています。
(東京高等裁判所平成3年4月1日判決を参考にしたフィクションです)
【Aさんの行為は泥棒だから窃盗罪ではないのですか】
Aさんは確かにVさんのカバンを泥棒しているので窃盗罪が成立するように見えます。
しかし今回、Aさんの行為は占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
それでは窃盗罪と占有離脱物横領罪について詳しく見ていきましょう。
【窃盗罪】
それでは窃盗罪についてみていきましょう。
条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
です。
窃盗罪は
①犯行の主体は、特に制限はなく、誰でも行えます。
②犯行の対象は、他人の占有する財物です。
③行為は窃取することで、財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
④結果は占有を取得することです。
⑤不法領得の意思が必要です。
【占有離脱物横領罪】
続いて占有離脱物横領罪についてみていきましょう。
条文は
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法第254条)
です。
占有離脱物横領罪は
①犯行の主体は、特に制限はなく、誰でも行えます。
②犯行の対象は、他人の占有を離れた他人の財物で、例としては「遺失物」「漂流物」があります。
※「遺失物」…占有者の意思に基づかずに占有を離れ、いまだ誰の占有にも属しないもの
※「漂流物」…占有者の意思に基づかずに占有を離れ、いまだ誰の占有にも属しないもので、水面または水中に存在するもの
③行為は横領することで、不法領得の意思をもって、占有を離れた他人のものを自己の事実上の支配内に置くことをいいます。
④結果は占有を取得することです。
⑤不法領得の意思が必要です。
【窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い】
この2つの罪で大きく違うところは、犯行の対象です。
よって泥棒の行為をした時に、他人の占有があるか否かでどちらの罪になるかがほぼ決まります。
なおここでいう他人の「占有」とは、物を持っているというだけではなく、物に対する「事実上の支配」、つまり持ち主が物を目に見える形など客観的に支配しているだけではなく
例えば持ち主の自宅内にある物など、持ち主が物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態も含みます。
さらに物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態にあるか否かは
①支配の事実の観点(置き忘れてから気づくまでの時間的場所的な近さ)
②占有の意思の観点(存在していた場所をどれくらい認識していたか)
で判断される傾向があります。
【刑事事件例について】
Vさんがバッグを置き忘れ、気が付くまでには約10分程度でしたが、置き忘れた場所と気付いた場所はそれぞれ百貨店の地下と7階でした。
それは気付いた時点で置き忘れたあ署にすぐに戻って取り戻せることができる時間的場所的な近さにあったとはいえず、
Vさんはカバンを取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態にあったとはいえません。
よってカバンの占有はVさんから離れて遺失物と認められるため、Aさんは遺失物であるVさんのカバンを持ち去って自己の物としたため占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
【被害者と示談がしたい】
窃盗罪であっても、占有離脱物横領罪であっても、被害者がいる事件には変わりありません。
Aさんは被害者に謝罪し、示談がしたいと思っていますが、当事者同士で示談を行うのは大変難しいことです。
刑事事件に強い弁護士を通して、被害者に謝罪や弁償を行い、示談を成立させていくことになるでしょう。
示談が成立すれば、Aさんのように警察が介入している場合は起訴猶予による不起訴処分を目指していくことも可能ですし、不起訴処分となれば前科にはなりません。
また、警察が介入する前に示談が成立すれば事件化する前に解決することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や占有離脱物横領罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や占有離脱物横領罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
詐欺罪と資格の制限
詐欺罪と資格の制限について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんが名古屋市天白区のV音楽ショップを通りかかったところ、店の前にBさんあてのCD引き渡し証を拾いました。
AさんはV音楽ショップに入り、レジ奥に「B様渡し」とあるCDが置いてあるのを確認したうえでレジにいた店主のVさんに対して「Bです。CDを受け取りに来ました。」と伝えました。
VさんはAさんに対し、Bさんに引き渡すはずのCDを渡しました。
Aさんは後日詐欺罪で愛知県天白警察署において話を聞かれることになりましたが、Aさんは社会福祉士の試験を控えており、影響が出るのではと心配しています。
(フィクションです)
【Aさんの行動は詐欺罪にあたるのか】
詐欺罪は
1人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(刑法第246条)
と規定されています。
Aさんは、V音楽ショップに入り、店主のVさんに対して拾ったBあての引き渡したうえで「Bです。CDを受け取りに来ました。」と話しています。
これは、実際には引き渡しを受ける権利を持っているBさんではないAさんが、Bさんになりすまして、CDの引き渡しを求める嘘をついています。
つまり、財産的処分行為(CDの引き渡し)に対して欺く(Bであると嘘をつく)行為を行なっていることから、詐欺罪が成立する可能性は高いと思われます。
【罪に当たる行為をすると資格に影響がでますか】
裁判で有罪判決を受けると、資格に影響する場合があります。
有罪判決とはいわゆる前科のことで、前科となる処分は懲役刑や禁錮刑以外にも罰金刑や科料があります。
また、先に述べた通り詐欺罪には罰金刑の規定はありませんので、起訴をされて裁判となれば前科がつく可能性は非常に高くなります。
前科がつくと絶対的に制限されてしまう資格は
①国家公務員、地方公務員、自衛隊員など( 実刑の場合、実刑期間の満了まで制限されます)
②社会福祉士、介護士、保育士など(実刑の場合、実刑期間とその後2年間制限されます)
③公認会計士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士など(実刑の場合、実刑期間とその後3年間制限されます)
④警備員、宅地建物取引士、貸金業者など(実刑の場合、実刑期間とその後5年間制限されます)
⑤学校教員、弁護士など(実刑の場合、実刑期間とその後10年間制限されます)
があります。
Aさんは社会福祉士の試験を控えていますが、社会福祉士は上記の通り、実刑の場合、実刑期間とその後2年間は資格の取得が制限されます。
ただし、執行猶予付き判決の場合は、執行猶予が取り消されることなく猶予の期間を経過した場合、刑の言渡しの効力を失いますので、それ以降は資格に制限はなくなります。
つまり、前科がつかない処分=起訴猶予による不起訴処分を目指す、若しくは少しでも欠格期間を短くするために執行猶予付き判決を目指していくことになるでしょう。
不起訴処分を目指すためには、被害者の方との示談が大切になります。
執行猶予付き判決を目指すためには、検察官に対し、十分な反省をしており再犯防止のための環境が整っていること、また示談が成立していればその旨を主張していくことになります。
そのためにもお一人で、またご家族だけで悩むことなく、刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、資格に影響がでるのか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
バイク窃盗と自首
バイク窃盗と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市中川区の路上で警察官から職務質問を受け、その場から走って逃走しました。
1分ほど走ったところ、コンビニエンスストアの駐車場でエンジンのかかっていた原付バイクを見つけたので、職務質問から逃げる目的でその原付バイクに乗りました。
その後自宅近くのマンション駐車場に原付バイクを乗り捨て帰宅しましたが、Aさんは急に怖くなり窃盗罪で愛知県中川警察署に自首しようかと思っています。
(フィクションです)
【盗んだバイクを運転して、乗り捨てても泥棒になりますか?】
物を盗むのは、その物を自分の物にしたい、と思って盗むことが多いと思います。
しかし、自分の物にするつもりではなく、一時的に逃げるために盗んだ時も泥棒になる(窃盗罪が成立する)のでしょうか?
事件例も「バイクを少し借りただけ」に見えるかもしれませんが、この場合はどうなるのかみていきましょう。
窃盗罪の条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
とあります。
他人の所有する物を勝手に持ち去るとき、窃盗罪が成立するかどうかの分かれ目は
他人の物を持ち去る時点で、持ち去った物を経済的用法に従って利用したり、処分したりする意志があるかどうかです。
経済的用法とは、その物を本来予定されている用法どおりに用いることを指すもので、例えば自転車やバイクなら運転するなどです。
仮にAさんが原付バイクを見つけた時、逃走のために乗るのではなく、むしゃくしゃした気分を晴らすために原付バイクを自宅に持ち帰り破壊した場合は、経済的に用法に従って利用するとは思っておらず、Aさんには窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立することになります。
今回Aさんは、エンジンのかかっている原付バイクに乗車してマンション駐車場まで実際に運転して移動しています。
これは原付バイクを経済的に利用する意思があると認められるので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
【自首について】
窃盗罪の自首とは、窃盗罪の犯人が警察等の捜査機関に自発的に窃盗の事実を申告して処分を求めることです。
自首が認められた場合の効果は、刑が減軽される可能性があるというものです。
ですが自首が成立するには、警察など捜査機関に窃盗事件が発覚していないこと、捜査機関に自発的に自己の犯罪を申告することが必要です。
この条件を満たさなければ、窃盗罪で警察に出向いたとしでも自首は成立しません。
Aさんについては、Aさんが原付バイクを盗んだことが既に警察に発覚している可能性もありますので、慎重な判断が必要と思われます。
ご自分で判断されることなく、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、自首をしたいが不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市熱田区のコンビニに入ってお金を払う気もないのに、たばこを店員Vさんから受け取った後に「財布を忘れました。自宅に帰って財布を持ってきます。念のため運転免許証をお渡しします。」と言い、店員のVさんはそれを信じて分かりました、と回答したため、Aさんは外に出てそのまま逃げました。
実はこの運転免許証は、Aさんの双子の弟のBさんのものでした。
後日Bさんのところに愛知県熱田警察署より「近所であった詐欺事件のことで少し話を聞かせて欲しい」と連絡が入り、全く心当たりのないBさんは非常に不安な気持ちになっています。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
詐欺罪は刑法第246条に規定があり
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
詐欺罪が成立するには
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつ①~④は連続していることが必要です。
また、財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
コンビニの店員は財物を処分できる権限を有する者とされていますし、なおかつ今回は①~④が連続している状況であるため、詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
【冤罪対策について】
事例では、詐欺事件の犯人はBさんではなくAさんなのですが、捜査機関はBさんを詐欺事件の犯人として話を聞いてくる(取調べをしてくる)可能性があります。
犯人として取調べをしてくるということは、とても厳しい、威圧的な取調べを受けてしまう可能性が有ります。
自分は何も犯罪をやっていなくても、威圧的な取り調べや長時間の厳しい取調べに心が折れてしまい、やってもいない犯罪をやりましたと自白してしまう可能性も全くないとは言えません。
自白だけで有罪になることはありませんが、それでも自白が現在でも重要な証拠にはなるのです。
こうして、冤罪(えんざい、と読み、無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことです)が起こってしまうのです。
冤罪が起こるのを防ぐには
①取調べについての適切なアドバイスを受ける
②違法・不当な取調べを阻止する
③違法・不当な取調べがあったこと(自白は虚偽であること)を裁判所で主張する
④有利な証拠を探して無実・無罪を主張する
等の方法があります。
③のように「違法な取調べを受けて虚偽の自白をした」ことを主張することも大切ですが
まずは①、②のように「違法な取り調べを受けて虚偽の自白をしないこと」がとても大切です。
具体的には、「黙秘権」「署名押印拒絶権」「調書の増減変更申立権」などの被疑者・被告人に保障された権利を適切に行使することや、捜査機関から「長時間の取調べを受ける」「暴力的、威圧的な態度で取調べを受ける」「取調官が嘘を言って自白を誘導してくる」などの違法、不当な取調べを受けないように、または受けてしまった場合に弁護士を通じて抗議するなど適切な対応をすることが大切です。
自分は何もしていないのに犯罪の嫌疑をかけられている、取調べを受ける予定がある方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が取調べをうけることになった、何もしていないのに犯人扱いを受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
住居侵入罪と泥棒
住居侵入罪と泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは深夜、貴重品を盗む目的で、名古屋市千種区のVさん宅の施錠されていない裏口から中に忍び込みました。
懐中電灯で周りを照らして廊下を歩いていたところ、Vさんに見つかり何も盗らずにそのまま逃走しました。
その後、Aさんは愛知県千種警察署に住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【何も盗んでいなくても泥棒のために侵入したのですよね?】
確かに泥棒のために他人の家屋に侵入したのだから、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
しかし、状況によっては窃盗未遂が成立せず住居侵入罪にとどまる場合もあります。
窃盗罪と窃盗未遂罪と住居侵入罪について見ていきましょう。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
【窃盗未遂罪(など)】
(刑法)第235条から第236条まで、第238条から第240条までおよび第241条第3項のの罪の未遂は、罰する。(刑法第243条)
【住居侵入罪】
正当な理由が無いのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
【窃盗未遂罪が成立する状況とは】
実際に財物を窃取されていなくても、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なった時点で実行の着手が認められ、窃盗未遂罪が成立します。
ですので、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なわなければ、窃盗未遂罪も成立しません。
具体的危険が発生する行為か否かは、対象となる財物の大きさなどの形、犯行日時(昼か夜か)、犯行場所の状況、犯行の具体的態様などの状況を総合して判断します。
例えば
・一般住宅の場合は、物色行為があった段階で実行の着手があるとされています
・土蔵や金庫室の場合は、侵入行為に着手した段階で実行の着手があるとされています
【刑事事件例について】
Aさんは深夜、Vさん宅に忍び込んでいるものの、Vさんの住居内は様々な部屋があり、様々な物品が混在している場所です。
Aさんは懐中電灯で廊下を歩き、盗む品を探していた途中で発見されています。
つまり、財物の占有を侵害する具体的危険性が発生したといえる物色行為には至っていないと判断され、窃盗の実行の着手は認められず、よってAさんには窃盗未遂罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する可能性が高いと思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
Aさんは現在逮捕されている状態です。
逮捕後、警察は48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をします。
その後、警察から容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留(引き続き留置場に身柄を置くこと)の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。
その後、検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って容疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、容疑者はまず10日間は留置場や少年鑑別所等の施設に勾留されることになります。
刑事事件に強い弁護士は、Aさんが今どの段階にあるのかを適切に判断し、各状況に応じた身柄解放活動を行っていきます。
また、窃盗罪、窃盗未遂罪が成立しないとはいえ、住居侵入罪は被害者の方がいらっしゃる犯罪です。
ですので、早急に刑事事件に強い弁護士を通して、被害者の方との示談交渉や被害弁償を行い、示談を成立させ処分が重くならないようにしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。