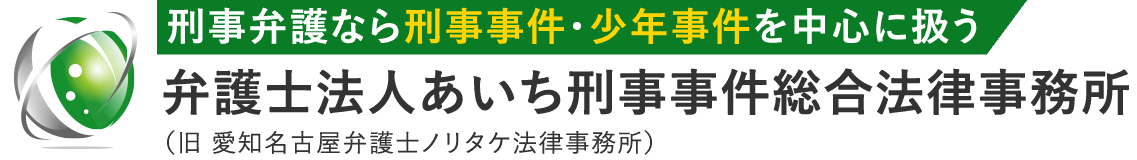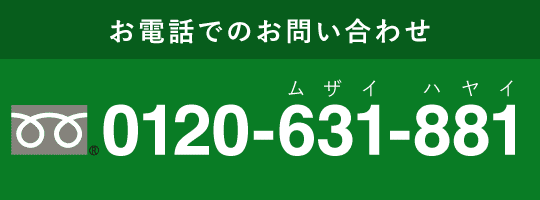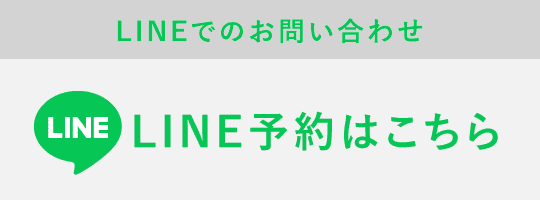Author Archive
自宅にデリヘル呼んで盗撮
自宅での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさん(40歳)は、性的サービスを受けるため、自宅マンションにデリヘル嬢を呼びました。そして、Aさんは、その際、隠しカメラでデリヘル嬢の裸の姿などを盗撮しました。そうしたところ、Aさんは、デリヘル嬢に隠しカメラを発見されてしまいました。その後、Aさんは店の店長から罰金50万円の請求を受け、デリヘル嬢からは被害届を出すなどと言われています。
(フィクションです)
~Aさんが問われる罪~
Aさんが問われる罪は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例(条例)、あるいは軽犯罪法違反です。
条例は全国各都道府県単位で定められています。各都道府県によって規定の内容が異なりますから、詳しくはインターネットなどで条例を検索して確認していただきたいのですが、盗撮行為が禁じられる「場所」は、概ね共通して
1 公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所
とされていることが多いかと思います。公衆の目に触れるような場所としては、「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が挙げられます。また、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所としては「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げらます。
次に、盗撮行為の「内容」ですが、これも概ね共通して、
1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している「下着」を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下、写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
とされています。1②、2②からわかるように、写真機等を設置するだけでも処罰の対象となり得ることが分かります。
罰則は、通常の盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として盗撮した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされていることが多いと思われます。
軽犯罪法違反(窃視の罪)は、軽犯罪法1条23号に規定されています。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し、軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており、しかも条例が「公共の~、公衆~」と規定していたのに対し、軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。
のぞき見るとは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており、方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん、カメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話、スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では、カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し、行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法などで撮影し、その後、記録媒体を回収してから再生するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点、直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも、被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく、むしろ、カメラ等で撮影された場合の方が、繰り返し何度も見られたり、第三者にデータが渡ったりする危険があり、プライバシー侵害の程度が高いのであるから、人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは、カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり、撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは、後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります。
罰則は、拘留又は科料です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪
器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、世界遺産に登録されている寺社の山門の壁に油性ペンで落書きをしたとして器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。これを聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
刑法第261条の条文は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者」について器物損壊罪が成立するとしています。
ここでいう「前3条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)のことをいいます。
そうすると、器物損壊罪が想定する「他人の物」とは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の物であるといえます。
上の事案では、寺社の山門の壁が目的物となっています。
ここで、寺社は建物であることからその山門の壁については「建造物等」であり、器物損壊罪における「他人の物」にあたらないのではないかが問題になります。
建造物等損壊罪における「建造物」とは、屋根があり、壁や柱で支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能な家屋や建築物をいいます。
そして、建築物そのものではなく、ドアや壁など建築物に付随する物が「建造物」に当たるかどうかは、その物と建築物がどの程度接合しているのかやその物が建造物においてどの程度重要であるかなどを総合して判断されます。
過去の裁判例において「建造物」に当たると判断された物の例としては、天井版や屋根瓦、住居玄関ドアなどがあります。
他方で、「建造物」に当たらないと判断された物の例としては、ガラス障子や雨戸、竹垣や畳などがあります。
上の事案の寺社の山門の壁については、寺社という建造物の一部としてではなく、別個独立した物であると判断されたことから「建造物」ではないとされたものであると考えられます。
したがって、建造物損壊罪の「建造物」ではなく、器物損壊罪における「他人の物」にあたると考えられるのです。
器物損壊罪における「損壊」とは、財物自体の形状を変更したり滅尽させたりする典型的な破壊行為のみならず、事実上・感情上その物を本来の用途に従って使用できなくして本来の効用を失わせることをいいます。
典型的な破壊行為としては、例えば、他人の壺を割るという行為が考えられますが、これが「損壊」に含まれることに疑いはありません。
他方で、上の事案のような壁に落書きをする行為は、壁を破壊したわけではないので典型的な破壊行為とはいえません。
しかしながら、過去の裁判例においては、公園の公衆トイレにスプレーで落書きしたという事案について、落書きをしただけでは公衆トイレの効用を喪失させるとまではいえないものの、「建物の外観・美観を著しく汚損し、そのままの状態で一般の利用に供することを困難にするとともに、再塗装を要するなど原状回復に相当の困難を生じさせた」として器物損壊罪の成立を認めた裁判例もあります。
この裁判例に従うと、寺社の山門の壁に油性ペンで落書きをした場合、その壁の外観を著しく汚損することになりますし、油性ペンという簡単には消せないペンで落書きをしたことは原状回復に相当の困難を生じさせたとして、「損壊」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。
この場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります。
~文化財保護法~
「損壊」の対象が、単に「他人の物」にとどまらず「特別に保護されているもの」に当たる場合、文化財保護法違反となります。
「特別に保護されているもの」には、たとえば有形・無形文化財や民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物や国宝などが含まれます。
上の事案の寺社は世界遺産に登録されているとのことで、「特別に保護されているもの」に当たる可能性があります。
そうすると、一般法である器物損壊罪ではなく、より刑の重い器物損壊罪の特別法である文化財保護法違反に切り替えて捜査が進められる可能性があります。
文化財保護法違反となった場合には、5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
書類送検
書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、SNS上で知り合ったVさん(17歳)に頼んで、Vさんの全裸の写真画像を撮ってもらい、それを自身のスマートフォンに送信してもらって楽しんでいました。そうしたところ、ある日、Vさんのスマートフォンをチェックした母親が、Vさんが見知らぬ男に裸の写真画像などを送っていたっことを知りました。Vさんの母親はVさんとともに警察へ相談に行きました。後日、捜査の結果、Aさんは児童ポルノ(製造罪)の被疑者として調べを受けることになり、事件は名古屋地方検察庁へ書類送検されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪の製造罪~
児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
~書類送検~
書類送検とは在宅事件(身柄を拘束されていない事件)が検察庁へ送検されたことを意味しています。
書類送検の根拠は刑事訴訟法246条に求めることができます。
刑事訴訟法
第二百四十六条(司法警察員から検察官への事件の送致)
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。
司法警察員は、当該事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。
書類送検された後の流れは以下のとおりです。
① 書類送検
↓
② 担当検察官が決まる
↓
③ 担当検察官から電話OR文書で出頭要請を受ける
↓
④ 出頭&取調べを受ける
↓
⑤ 刑事処分
書類送検された(①)後、2~3日で担当検察官が決まります。担当検察官が決まると、担当検察官(又は補助の検察事務官)から電話OR文書で検察庁へ出頭するよう要請を受けます。要請を受けるタイミングは決まっておらず、検察官の判断に委ねられます。検察官は在宅事件と同時に身柄事件も同時に処理しており、身柄事件の方が時間的制約があるため、どうしても在宅事件よりも身柄事件の方の処理を先行しがちです。したがって、検察官が身柄事件の処理に追われるなどして時間を取られていると、出頭要請は遅れる可能性があります。①から数か月程度経って出頭要請を受けるということも少なくありません。出頭後は、検察官の取調べを受け、捜査を終えた段階で刑事処分が決まります(⑤)。正式起訴された場合は、後日、裁判所から起訴状謄本などの書類が送達されてきます。略式起訴される場合は、取調べ時に略式裁判を受けるかどうかの同意を求められます。不起訴となった場合は、検察官から通知する制度はありませんが、請求すれば不起訴にした旨の文書を発行してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
少年事件の弁護人
少年事件の弁護人ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
A君の母親は息子が万引きの件で逮捕されたため、少年事件の弁護士が所属する法律事務所に電話したところ、弁護士は早速少年との接見などの弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~弁護人の弁護活動~
少年とは20歳未満の男女のことをいいます。少年にとって逮捕という手錠をはめられ身柄を拘束されることは精神的にもかなりショックなことだと思います。また、そのご家族にとっても同じことが言えるのではにでしょうか?そんなとき、弁護人、付添人は少年にどんなことができるのでしょうか?今回は、弁護人逮捕された少年のためにできることを中心に紹介していきたいと思います。
前置きはこれくらいにして早速本題に入りたいと思います。まず、今回は、家庭裁判所送致前、つまり、弁護人の弁護活動についてご紹介いたします。ただし、ここでご紹介する弁護活動はあくまで一般的なもので、その内容は個別事案により異なってきますことを予めご了承ください。
= 接見 =
まずは、少年との面会(接見)が基本の活動となります。精神的にまだまだ未熟な少年にとっては弁護士の存在は心強いでしょう。接見では、事件の認否によって具体的なアドバイスをさせていただくことができます。取調べへの対応方法のアドバイス、事件の見通しなどをお伝えすることも可能です。また、少年が学生・生徒であれば、学校との橋渡し役を務めることも可能です。
= 釈放に向けた活動 =
ご依頼された時期により異なりますが、勾留前であれば、警察官、検察官、裁判官に釈放するよう、また勾留の理由、必要がないことを意見書などにまとめて訴えることによって早期釈放を促します。また、勾留決定後、または観護措置決定後であれば、その決定に不服申し立てを行うなどして早期釈放に努めます。
= 示談交渉 =
示談交渉は弁護士にお任せください。示談交渉をはじめるには、捜査機関(警察、検察)から被害者の氏名、連絡先、住所などの個人情報を取得する必要がありますが、個人情報を取得できるのは弁護士しかいません。また、示談交渉にあたっては相手方を条件を詰めていく必要がありますが、それには知識や経験が必要となります。示談が成立すれば早期釈放に繋がることもあります。
= 家庭裁判所への意見書の提出 =
勾留決定後は最大20日間、身柄拘束されます。そして、家裁送致後は家庭裁判所の観護措置という決定が出れば、今度は少年鑑別所に収容されてしまいます。そこで、弁護人としては家庭裁判所に対し、観護措置は必要でない旨の意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ひき逃げ、当て逃げの違い
ひき逃げ、当て逃げの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、ひき逃げ事故を起こしたとして過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさん妻は、交通事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ひき逃げと当て逃げの違い~
「ひき逃げ」は、①車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合(交通事故のうち人身事故があった場合)において、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(以下、救護義務)にもかかわらず、救護義務を果たさなった場合、あるいは、②①の場合において、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるのに、救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です(道路交通法72条1置く)。①の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、②は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条2項)です。
①と②との法定刑は大きく違います。なぜ、このように違いがあるかというと、②の場合は「人の死傷が当該運転者の運転に起因」した場合の救護義務違反の規定で、①の場合よりも悪質であるからです。これが①と②の大きな違いです。例えば、道路脇の影から子供が突然飛び出し(当該車が適法に走っていた際のスピードの制動距離範囲内に飛び込んできた)、怪我を負わせたあるいは死亡させたとします。この場合、通常、子供の死傷が「当該運転者の運転に起因」したとは認められません。よって、この場合、救護義務違反をすれば①が適用されることになります。
言い方を変えれば、自己に過失なく人を死傷させた場合でも救護義務は発生します!から注意が必要です。
なお、よく、ひき逃げと同時に処理される罪として過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)、危険運転致傷(15年以下の懲役)、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)などがあります。危険運転致死傷罪には罰金刑がありませんから、同時に起訴されれば、ひき逃げでも懲役刑を選択されます。過失運転致死傷罪で罰金刑を選択された場合は、ひき逃げでも罰金刑が選択されますが、①の場合、150万円(100万円+50万円)以下の罰金、②の場合、200万円(100万円+100万円)以下の範囲ので刑が科されます。
「当て逃げ」は、交通事故のうち物損事故があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
~ひき逃げ、当て逃げの弁護方針~
ひき逃げの場合も当て逃げの場合も、交通事故を起こしたなどたことの認識(「人を怪我させた死亡させた」、人を怪我させたかもしれない、死亡させたかもしれない」など)がなければ成立しません。そこで、運転者本人から交通事故に至るまでの経緯、交通事故の状況等を詳しくお聴き取りをする必要が出てくる場合もございます。
また、上記のとおり、運転者本人の運転に起因するかどうかで法定刑が異なりますから、客観的証拠から事故の状況を詳しく検討する必要が出てくる場合もございます。
ひき逃げ、当て逃げいずれの場合も、被害者への謝罪、被害弁償が必要である点はいうまでもありません(罪を認める場合)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ、当て逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。ひき逃げ、当て逃げを起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
共同正犯と錯誤
共同正犯と錯誤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
AさんはBさんから、Vさん宅に立ち入って盗みをすることを持ちかけられこれを承諾しました。そして、Aさんは犯行日当日、BさんがVさん宅に立ち入って盗みをする間、警察などが来ないかどうか外で見張りをしていました。ところが、後日、警察にAさんとBさんによる犯行であることが発覚し、Aさんは住居侵入、窃盗罪、Bさんは住居侵入、強盗罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~共同正犯とは~
2以上共同して犯罪を実行した場合を「共同正犯」といいます。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
正犯あるいは正犯者とは、犯罪(基本的構成要件)に該当する行為(実行行為)を行う者のことをいいます。刑法60条は、意思の連絡(共謀)の下に複数の者が関与した事案において、自己の犯罪を犯したと評価し得る重要な関与者を正犯とし、他人(Bさん)の実行行為及び結果につき、共同して行えば全て帰責される(刑事責任を負わされる)とう「一部行為の全部責任の原則」を認める規定です。
~共同正犯の成立要件~
それでは、共同正犯が成立するためにはいかなる要件が必要なのでしょうか?言い換えれば、他人が行った行為及びそれによって作出された結果を仲間内である共犯者にも帰責させるための要件とはいかなるものなのでしょうか?
共同正犯が成立するためには、主観的要件としての「共同実行の意思(意思の連絡=共謀)」、客観的要件としての「共同実行の事実」が必要です。
共同実行の意思とは、共同して実行行為をしようという意思のことをいいます。共同加工の意思ともいわれます。共同実行の意思は、2人以上の行為者全員が相互に持たなければなりません。したがって、甲がVに暴行を加えている間、甲の知らない間に乙がVの財布を盗んだという場合、窃盗罪(あるいは暴行罪)の共同正犯は成立しません。
共同実行の事実とは、共謀した行為者が実行行為を分担することであり、共同加功とか行為の分担ともいわれています。
~共犯正犯の錯誤とは~
ところで、本件では、Aさんは窃盗罪、Bさんは強盗罪と異なる罪で逮捕されています。
これは、Aさんは窃盗をする意思があった、Bさんは強盗をする意思があったという共犯者の認識の違いが原因です。
このように、共犯者(Aさん)が認識していた事実の内容(窃盗罪)と、正犯者(実行行為者)の実行(強盗)との間に食い違いがある場合を「共犯の錯誤」と呼んでいます。
では、「共犯の錯誤」があった場合、実務ではどのように処理、解決されているのでしょうか?
この点、判例は、共同行為者相互間の認識の不一致が同一構成要件内にあるとき、共同正犯の故意は阻却されないとしています。
他方、共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるときは、原則として共同正犯の故意は阻却され、ただ、それぞれの構成要件が重なり合うときのみ、その重なりあう限度で共同正犯が認められるとしています。
本件の場合、後者の「共同行為者間の認識の不一致が異なる構成要件にまたがるとき」に当たります。構成要件とは、ここではとりあえず「罪」と理解してください。そして、Aさんは窃盗罪の認識、Bさんは強盗罪の認識であることから両者の認識に不一致が生じています。したがって、強盗罪の共同正犯の故意は阻却されますから、強盗罪の共同正犯は成立しません。次に、窃盗罪と強盗罪の違いは、その手段として暴行、脅迫を用いるか用いないかの違いだけで、後は同じです。つまり、両者は窃盗罪の範囲で重なり合っているといえます。したがって、共同正犯は窃盗罪の範囲でのみ成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢と欠格
痴漢と欠格について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
看護師を目指して看護学校に通うA君は、数か月前、JRの電車内で痴漢をしたとして逮捕され、起訴され、昨年12月の裁判で、懲役4月、3年間執行猶予の有罪判決を受けてしまいました。A君は、今年5月に看護師試験を控えており、試験を受験することが可能か、仮に合格した場合、看護師免許を取得することができるかどうか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~欠格事由~
欠格とは、要求されている資格を欠くこと、欠格に当たる理由(事由)のことを「欠格事由」といいます。国家公務員、地方公務員、国家資格を必要とする職業は、職責が重く、国民からの高度な信頼も必要とされることから、法律で欠格事由が定められています。
では、看護師の欠格事由はどう定められているのでしょうか?
この点、保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)に次の定めが設けられています。
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの
4 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
1号の「罰金以上の刑」とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことをいいます。「刑に処せられた」とは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。また、執行猶予付き判決を受けた場合も「刑に処せられた」に当たります。
~看護師試験を受験することが可能か?~
以上の規定を踏まえた上で、A君のご質問に回答します。
まず、欠格事由は、看護師免許を与えるか与えないかの判断の際に考慮されるもので、試験の受験とは無関係です。
したがって、試験の受験自体に制限がない限り「可能」と考えます(受験要領などで確認してください)。
~看護師免許を取得することは可能か~
次に、仮に、A君が試験に合格しても、A君はいまだ「執行猶予中」だと思います。
そして、前述のとおり、「刑に処せられた」には執行猶予中の場合も含まれますから、A君は看護師の免許を取得できない可能性があります。
免許を与えるかどうかは、最終的には厚生労働大臣の判断に委ねられます。
なお、執行猶予期間中、何事もなく経過すれば、執行猶予を言い渡した刑の効力は失われます(刑法27条、だたし前科は残ります)。
つまり、Aさんは「罰金以上の刑に処せられた者」ではなくなり、免許を取得することができます。
刑法27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
窃盗と微罪処分
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、スーパーで万引きし、警察官に事情を聴かれることになりました。Aさんから依頼を受けた弁護士は、微罪処分獲得に向けてお店側と示談交渉を始めました。
(フィクションです)
~微罪処分とは~
微罪処分とは、警察が事件を検察庁を送致せず、被疑者への厳重注意、訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。本来、警察が立件した事件は警察→検察へと送致することが基本です(刑事訴訟法246条本文)。しかし、「検察官が指定した事件」については例外的に送致する必要がありません(刑事訴訟法246条但書)。
~微罪処分の対象事件と対象基準 ~
あくまで微罪処分は例外措置ですから、どんな事件でも対象となるわけではありません。微罪処分の対象事件については、各都道府県で異なるとも思われますが、通常、窃盗罪、横領罪、占有離脱物横領罪、暴行罪などは対象とされていることと思います。なお、万引きは窃盗罪に当たりますから、万引きは微罪処分の対象事件ということになります。
しかし、微罪処分の対象事件だからといってすべての事件が微罪処分となるわけではありません。概ね以下の基準を満たす必要があります。
1 犯罪事実(犯情)が極めて軽微か
→窃盗罪、横領罪であれば被害額が2万円以下、暴行罪であれば凶器を使用していないことが基準となります。よって、同じ万引きであっても、被害額が2万円を超える万引きについては微罪処分の対象とはなり得ません。
2 被害弁償、示談ができているか
3 被害者が処罰を望んでいないか
4 前科、前歴がないか
微罪処分を決するのは検察庁や裁判所でもなく警察です。警察の犯罪捜査に関する規範について定めた犯罪捜査規範198条には次のようにかかれています。
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる
ただし、警察の自由裁量で何から何まで微罪処分にできるものではありません。ここに書かれてあるとおり、犯罪事実が軽微であり、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたもの、である必要があるのです。
~微罪処分とした場合の流れ、手続き~
では、警察がある万引き事件を微罪処分としたとしましょう。その後はどのような流れ、手続きになるのでしょうか?この点、まず、犯罪捜査規範200条をみると、微罪処分により事件を送致しない場合は次の処置を取るものとされています。
1号 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること
2号 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を微すること
3号 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと
これからすれば、微罪処分となったとしても、少なくとも1回は警察署まで出頭する必要があるでしょう。また、同時に被疑者を監督すべき方も同様です。
そして、警察は、これらの処置が終わると、被疑者の氏名、年令、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨(以下、氏名等といいます)を記載した微罪処分事件報告書によって、検察官に事件の報告をします(犯罪捜査規範199条)。報告書1枚につき4、5名ほど、同じように微罪処分となった方の氏名等が記載されています。この報告の手続は刑事訴訟法246条本文にかかれてある「事件の送致」ではありませんから、この報告書に証拠書類や証拠物は付けられていません。また、「事件が送致」された場合と異なり、検察庁から呼び出しを受けることはありません。要は、警察署で警察官から厳しい御咎めを受けて終わりということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
現住建造物等放火で逮捕
現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します.
会社員Aさん(35歳)は、亡父から相続した一軒家(築60年)に妻と二人で暮らしていました。ある日、お金に困っていたAさんは、自宅の築年数が古いことから、自分の家に放火して火災保険金を騙し取ることを思いつき、アパートを借りて、しばらくの間は、そのアパートで生活することにしました。そして、引っ越しを終えて荷物を運び出した後に、和室の畳に灯油をまき、火のついたタバコをその近くに放置して、しばらくすると灯油に引火して火災が発生するように仕掛けをして家を出ました。幸いなことに、火災が発生した直後に、近所の住民が火災に気付いて消火したため、畳一枚を焼損するにとどまったのですが、Aさんは非現住建造物等放火罪で逮捕されてしまいました。Aさんはその後の起訴されましたが保釈による釈放を希望しています。
(フィクションです)
~非現住建造物等放火罪~
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等を焼損した場合には、非現住建造物等放火罪が成立します。
非現住建造物等放火罪は、その客体を他人所有と自己所有とに分け、自己所有に係る非現住建造物等への放火については「公共の危険」が生じなかった場合には罰しない旨が規定されています(第2項)。
そうすると、上の事案において、Aさん自宅の周囲に人がおらず、他に建物などもない場合であれば、「公共の危険」がないとして、非現住建造物等放火罪が成立しないようにも思えます。
もっとも、刑法第115条は、非現住建造物等放火罪における物が自己所有に係るものであっても、差押えを受けたり、賃貸されたり、保険に付されたりしている場合には、他人の物を焼損した者の例によると規定します。
そうすると、たとえAさん所有の自宅であっても、これが保険に付されている以上、他人所有の非現住建造物を焼損したことになり、「公共の危険」が生じずとも、Aさんには、他人所有の非現住建造物等放火罪が成立する可能性があるのです。
他人所有の非現住建造物等放火罪の罰則は「2年以上の有期懲役」で、自己所有の非現住建造物等放火罪の罰則は「6月以上7年以下の懲役」です。
~保釈による身柄解放~
放火罪は重大な犯罪であるため、捜査機関に発覚すれば逮捕および勾留の可能性はかなり高いと言えます。
そして、もし勾留中に起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、最低でも2か月は身体拘束が伸びてしまいます。
そうした事態に陥った際、身柄解放を実現する有力な手段として保釈の請求が考えられます。
保釈とは、裁判所に保釈金を納付することで、一時的に被告人を釈放する手続を指します。
保釈の最大の強みは、起訴前に釈放を実現できなかった事件において釈放を実現できる可能性がある点です。
保釈金は、逃亡を防止するための担保金の役割を果たします。
そして、罪が重くなればなるほど逃亡するおそれが大きいと判断されますから、罪が重たくなればなるほど保釈金も高くなる傾向にあります。
保釈されるためには、その前段階として保釈請求が許可される必要があります。
保釈請求に当たっては、法律の専門家である弁護士の視点が重要となることは否定できません。
ですので、保釈を目指すのであれば、保釈請求を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童ポルノで逮捕
児童買春・ポルノ禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、SNSを通じて知り合った高校生Bさん(16歳)に対して、Bさんの裸体を撮影させたうえでその写真を送信させ、この写真を暴露すると言って脅し、さらに路上を全裸で歩く動画を撮影させて送信させたとして、中村警察署の警察官により児童買春・ポルノ禁止法違反(単純製造)及び強要罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~児童買春・ポルノ禁止法~
児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童買春行為や児童ポルノの所持や提供、製造等の行為を禁じる法律です。
まず、児童買春・ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳に満たない者をいい、男女を問いません。
上の事案におけるBさんは16歳ですので、男女のいかんを問わず、児童買春・ポルノ禁止法における「児童」に該当することになります。
次に、「児童ポルノ」とは、①児童を相手方とし、又は児童同士の性交や手淫・口淫など性交に類似した行為、②他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、逆に児童が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で、殊更にその性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出又は強調されており、性欲を興奮させ又は刺激するものといった児童の姿態を視覚で認識できる方法により描写したものをいいます。
上の事案においては、撮影された対象がBさんの裸体とBさんが全裸で路上を歩く姿であるため、③に該当する可能性があります。
これを写真や動画で撮影した場合には、この写真や動画を視覚で認識できる方法により描写したものであると考えられます。
これは、加害者が自ら撮影した場合のみならず、被害者本人に撮影させた場合についても同様です。
したがって、上の事案でAさんの指示により撮影されたBさんの写真や動画は「児童ポルノ」に当たると考えられます。
「児童ポルノ」については、自己性的目的所持、提供、提供目的製造等、不特定多数への提供、公然陳列等が禁止されています。
上の事案のAさんのように、撮影の対象であるBさん本人に自ら撮影させるるという行為は「製造」として禁止されています。
この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
~強要罪~
Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反のほか強要罪でも逮捕されています。
強要罪は、生命、身体、自由、名誉、若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨害した場合に成立します。
まず、強要罪における「脅迫」は、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、脅迫罪のいう「脅迫」と同義であると考えられています。
ここでの「害悪」の内容は、強要罪の条文にも書かれていますが、相手方又はその親族の生命、自由、名誉、財産に対し害悪を加えることに限定されています。
上の事案では、AさんがBさんに対して、Bさんが全裸で路上を歩く動画を撮影して送信しなければBさんの全裸の写真を暴露するという旨の脅迫を加えています。
これは、Bさんの自由や名誉に対して向けられた「害悪の告知」であると考えられますので、Aさんの行為は強要罪における「脅迫」に当たると考えられます。
次に、「義務のないことを行わせ」るとは、行為者に何らその権利・権能がなく、したがって、相手方にも義務がないのに、相手方に作為・不作為又は認容を余儀なくさせることをいいます。
ここでいう義務の内容は、恐喝罪(刑法第249条)、強盗罪(刑法第236条)、逮捕・監禁罪(刑法第220条)、職務強要罪(刑法第95条第2項)などのように他の犯罪に該当しないものをいい、これらの犯罪が成立する場合には、別途強要罪は成立しません。
上の事案では、AさんはBさんに対して、全裸で路上を歩く姿を撮影させるという「義務のないこと」を行わせていますので、この点について強要罪が成立する可能性があります。
この場合、3年以下の懲役に処せられることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。