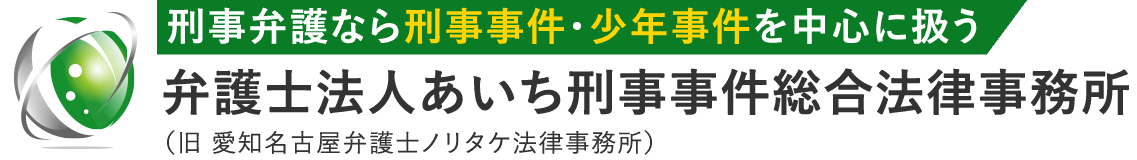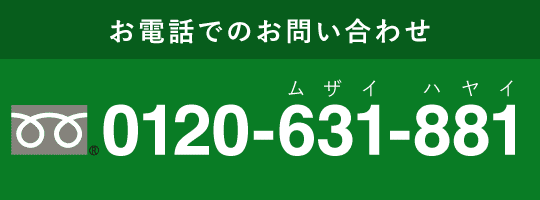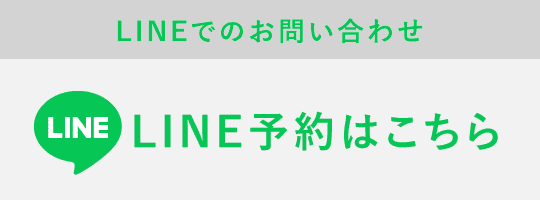Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
~発作による事故で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
孝田町在住のAさんは、孝田町内の国道を走行中、持病であるてんかんの発作を起こしてしまった。
そのため、Aさんは車を正常に運転することが出来なくなり、近くを歩いていた歩行者Vと接触し、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
そして、通報を受けて駆け付けた愛知県警察岡崎警察署の警察官により、Aさんは逮捕された。
その後、取り調べの中でAさんにはてんかんの持病があること、数年前にもてんかんの発作で事故を起こしていたこと、今回の事故当日はてんかんの薬を服用していなかったことが判明したため、危険運転致傷罪の容疑で捜査が進められることとなった。
危険運転致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分を軽くすることが出来ないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(この事件はフィクションです)
~危険運転致死傷罪とは~
危険運転致死傷罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死傷させた場合に適用される罪です。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。
そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死傷罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
・赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為
また、第3条2項において、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
と規定されています。
そして、政令で規定されている病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害が会挙げられます。
~危険運転致死傷罪になり得るケース~
上記のケースのように、てんかんを持病として持っており、かつ服薬等症状を抑える手立てがあるにもかかわらずそれを怠り、発作を起こして正常な運転ができない状態で起こした事故については、危険運転致死傷罪として厳しく罰せられる可能性があります。
今回は、病気に起因した死傷事故で危険運転致死傷罪に当たるかどうかが争われたケースを紹介させていただきます。
(札幌地裁平成26年2月28日)
被告人は、普通乗用自動車を運転し、駐車場から発進しようとしました。
しかしながら、被告人は糖尿病に罹患しており、低血糖症状による意識障害が生じました。
低下した意識状態のまま進行させた結果、停車中の自転車に衝突し、自転車に乗っていた被害者を死亡させました
なお、被告人はかねてより糖尿病による低血糖症状によって意識障害に陥る恐れがあることを認識していました。
このような事情の下、裁判所は次の通り判断しました。
・被害者は追突されたばかりでなく、被告人運転車両の下敷きとなる痛ましい事故であったこと
・意識障害に陥って運転すれば重大な人身事故を起こしかねないため、自動車の運転を差し控えるべきであったこと
・被告人は、事故の前年に4回も低血糖症状による意識障害に陥っており、前兆なく意識障害に陥ることを認識していたこと
・被告人は5か月前にも、運転中に意識障害による事故を起こしていたこと
などを理由に、被告人の責任は重大だとして、禁錮2年となりました。
病気を起因とする事故を起こしてしまった場合は、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
いかに説得的に被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張できるかどうかで、危険運転致死傷罪の成否及び最終的な処分が大きく変わるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、危険運転致死傷罪を始めとする刑事事件に強い法律事務所です。
危険運転致死傷罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
碧南市でひき逃げをしてしまったら
碧南市でひき逃げをしてしまったら
~ケース~
碧南市在住のAさんは,乗用車で碧南市内の住宅街の狭い道を走行中,脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんとぶつかり怪我をさせてしまった。
AさんはVさんが飛び出してきたのが悪いと考え,そのまま走り去った。
その後,Vさんから被害届が出され,防犯カメラにAさんの運転する車が映っていたため,Aさんは愛知県警察碧南警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
まず,Aさんは自動車を運転中に過失によりVさんに怪我をさせてしまっているので過失運転致傷罪が成立します。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金となっています。
なお,傷害が軽い場合には情状により刑が免除できる旨の規定があります。
これは最徐行して走行していても歩行者の飛び出しなどで交通事故は発生してしまうものであり,そのような場合にまで処罰するのは過酷であるという考えによるものと思われます。
しかし,必ず刑が免除されるわけではなくあくまでも情状により刑が免除できるという裁量免除規定となっています。
この情状には事故発生時の状況,対応,被害者の処罰感情などが総合的に判断されると思われます。
さて,今回のケースでAさんはVさんとぶつかったものの,そのまま走り去っています。
人身事故が起きた場合,車両の運転者には道路交通法第72条1項により負傷者の救護義務,道路における危険防止義務が発生します。
これらの義務に違反すると道路交通法第117条違反となります。
なお,人身事故が当該運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金,運転者の運転に起因しない場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる行為は上記の救護義務および危険防止義務に違反することをいいます。
ひき逃げは,特に運転者に起因する事故の場合,相手の怪我が軽い場合であってもひき逃げ行為が強い非難の対象となります。
そのため,刑の免除がされうる程度の軽い怪我であっても起訴され,刑事裁判となる可能性もあります。
また,ひき逃げをした場合,過失運転致傷事件では治療費や慰謝料の支払いといった示談交渉をすることで過失運転致傷罪自体は不起訴となるような事件であっても起訴され刑事裁判となってしまう可能性もあります。
しかし,示談交渉をしていれば不起訴となる可能性もあります。
重要なのは被害者の宥恕条項(相手を許すという条項)となります。
宥恕条項があり,怪我の程度が軽く,事故の原因となった過失も大きく無い場合には起訴猶予となる場合もあります。
なお,起訴された後に示談が成立した,起訴されてしまった以上,原則として無罪とはならず罰金額が少なくなるといった量刑に影響するという効果しか見込めません。
したがって,不起訴を目指すための示談交渉は起訴される前に行うことが必要です。
ところで,国選弁護人は原則として起訴された後にしか選任されませんので,起訴前に示談をしようと考えた場合,私選の弁護士に依頼する必要があります。
また,なるべく早く対応することによって被害者の方も示談に応じようと考えられる場合もあります。
ひき逃げを起こしてしまった場合には迅速に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はひき逃げ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げをしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、豊田市内の国道で普通自動車を運転していたところ、スピード違反で愛知県警察豊田警察署のパトカーに止められた。
その際、Aさんは警察官よりAさんの車が無車検・無保険であると告げられ、無車検車運行罪及び無保険車運行罪の容疑で愛知県警察豊田警察署まで任意同行を求められた。
同署での取り調べ後、Aさんは今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)
~無車検車運行罪~
そもそも無車検車とは、車検証の有効期限が切れた自動車(自動二輪車も含む)のことを言います。
そして、車検とは道路運送車両法に定められている車の安全性や公害防止などの保安基準に適合しているかを検査する自動車検査のうち、一般的に継続検査のことをいいます。
ミニカー・小型特殊自動車・250cc以下の自動二輪車を除くすべての自動車に検査が義務付けられているため、車検切れの車は安全性の担保がない危険な車だということになります。
その為、車検切れの車を運転した場合、無車検車運行罪として6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります(道路運送車両法第58条)。
しかし、車検が切れていることを知らなかったのであれば、このような罰則を受けることはありません。
~無保険車運行罪~
自賠責保険(正式名称 自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法1条に基づき、交通事故が発生したとき、被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
したがって、自賠責保険が切れているにもかかわらず自動車を運転した場合は自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります(無保険車運行罪)。
無保険車運行罪の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法第5条、第86条の3の1号)。
また、自賠責保険の補償期間は、車検の1ヵ月後に満了になるように設定されているため、無車検車運行罪に問われるケースの多くは、自賠責保険の補償期間も切れていることがほとんどのため、無保険車運行罪にも問われることが多いです。
仮に、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方が成立した場合、併合罪となります。
併合罪については刑法第47条に規定されており、2つ以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、重い方の刑期の1.5倍が適用されると定められており、罰金については2つの罰金の合計以下が科せられると定められています。
したがって、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方に違反した場合、1年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金となります。
~弁護活動~
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、初犯であれば罰金処分で済むことも多いです。
また、無車検、無保険であったことを知らなかった場合、刑事罰に問われることはありません。
しかし、無車検車運行罪、無保険車運行罪の前科がありながらこれを繰り返している場合や執行猶予期間中であった場合には実刑判決がでる可能性があります。
その為、無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に主張してもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、交通事故・交通違反における刑事処分に関しても安心してご相談いただけます。
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
~ケース~
仕事帰りに春日井市内にある居酒屋で飲酒したAさんとBさんは、店を出た後近くに止めてあったBさんの車に乗り、Bさんの運転で帰ろうとした。
帰り道で飲酒検問に引っかかり、呼気検査をされた結果、Bさんからは基準値以上のアルコール濃度が検出された。
その為、AさんとBさんは愛知県警察春日井警察署に任意同行を求められ取調べを受けた際、AさんはBさんと飲酒していたことを話したため、飲酒運転同乗罪にあたると言われた。
今後どのような刑事処分をうけることになるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転同乗罪とは~
道路交通法では飲酒運転が禁止され、違反した場合の罰則が定められていますが、運転者だけではなく、その同乗者にも罰則が定められています。
いわゆる飲酒運転同乗罪については、道路交通法第65条第4項において、
「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
と規定されています。
そして、飲酒運転同乗罪の罰則は、運転者が問われる罪名によって変わります。
運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、上記のケースにおいて、Bさんの車ではなくAさんの車でBさんに運転させていた場合は、更に罰則が重くなります。
飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した場合、飲酒運転をした本人と同等の罰則を受けることになります。(酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転:5年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
そして、飲酒運転同乗罪が成立するためには、運転者が飲酒していたことに対する認識が必要になります。
上記のケースでは、AさんはBさんと一緒に飲酒した後同乗していますので、Bさんが飲酒していたことに対する認識は争いようがありません。
しかし、運転者が飲酒していることを知らずに同乗してしまった場合、その認識が無かったことをしっかりと主張することが大切です。
ただし、捜査機関からの取調べでは、上記の認識があったと供述するよう迫られたり、本人は否認しているつもりでも認めているような内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
その為、飲酒運転同乗罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
運転者が飲酒していることを知っていた場合であれば、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことで、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、上記の認識が無かった場合には、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、飲酒運転同乗罪に関しても安心してご相談頂けます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
当て逃げで不起訴処分を目指すなら
当て逃げで不起訴処分を目指すなら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、北名古屋市内の駐車場で車を停めようとした際、停車中の他の車にぶつけてしまった。
気が動転してしまったAさんは、車から降りることなくその場を立ち去った。
後日、愛知県警西枇杷島警察署から電話があり、当て逃げ事件の件で話を聞きたいので愛知県警察西枇杷島警察署に来てほしいを言われた、
どう対応すべきか不安で堪らないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~当て逃げとは~
そもそも、物損事故を起こしてしまったとしても、刑事責任や行政責任を問われることはありません。
ただし、物損事故を起こしたのに現場から逃げてしまった場合、当て逃げとして逃走行為について刑事責任を問われることになります。
今回は、どういった行為が当て逃げにあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、事故を起こした場合には、人損事故・物損事故に拘わらず、以下の措置をとらなければなりません(道路交通法第72条)。
・運転の停止
・負傷者がいる場合はその救護
・道路における危険を防止する措置
・警察への事故報告
上記の措置をとり、通常の物損事故として処理された場合は、被害を賠償する責任は生じますが、刑事責任を問われることはありません。
しかし、上記の措置をとらずに事故現場から立ち去ってしまった場合、人身事故の場合はひき逃げに、物損事故の場合は当て逃げに問われることになります。
当て逃げは、ひき逃げに比べると法定刑は軽く、起訴されたとしても罰金刑で終わるケースが多いですが、罰金刑でも前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、例え罰金刑だったとしても、職魚によっては欠格事由に当たってしまったり、出国する手続上不都合が出る可能性があります。
~示談で不起訴処分を目指す~
当て逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
当て逃げをおしてしまいお困りの方、示談をして不起訴処分を目指す方は、刑事事件にお強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
煽り運転・傷害行為に対して正当防衛主張なら
煽り運転・傷害行為に対して正当防衛主張なら
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市千種区内の道路で後方からVにいわゆる煽り運転をされた。
しばらくして,信号待ちで停車したところ車から降りて来たVによって運転席の窓ガラスを叩かれ「おい,開けろや」などと怒声を浴びせられた。
怖くなったAさんは,信号が青になった瞬間に,Vから逃げようと車を発進させた。
その際,ドアミラーを掴んでいたVが転倒し,全治2週間程度の怪我を負った。
後日Aさんは傷害罪の疑いで愛知県警察千種警察署において事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
今回のケースでVは怪我をしていますので,傷害罪の構成要件に該当します。
~正当防衛ではないのか~
しかし,AさんはVに煽り運転をされ,その後降りてきて運転席の窓ガラスを叩くなどの行為をされたことによって怖くなって逃げようと車を発進させています。
そのため,Aさんには正当防衛(刑法36条1項)が成立しないでしょうか。
正当防衛の条文は「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」となっています。
正当防衛が成立するには急迫不正の侵害が前提条件となっています。
侵害とは,権利すなわち法益を侵害する危険をもたらすものをいい,不正とは違法であることを意味します。
そして不正の侵害は急迫したものでなければいけません。
つまり,被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要です。
この点,Aさんは煽り運転を受けており,停車したところVから運転席の窓ガラスを叩かれるといった有形力の行使(=暴行)を受けていたと考えることが出来ます。
そのため,Aさんには急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
また,Aさんは怖くなってVから逃げるために車を発進させたのですから防衛のためにした行為であるといえるでしょう。
それでは「やむを得ずした」とはどのような場合をいうのでしょうか。
正当防衛は緊急避難(刑法37条)と異なり,法益保護のために他に手段がないことまでは要求されていません。
そして,防衛行為の結果生じた法益侵害が,それによって回避した法益侵害よりも,侵害性において大であっても,そのことによって正当防衛は否定されません。
しかし,「防衛の程度を超えた」過剰防衛が刑法36条2項に別途規定されていることから,許容される防衛行為には限度があります。
~Aさんに正当防衛は成立するのか~
では,今回のケースでAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
Aさんは特に怪我などしていない一方,Vは怪我をしてしまっていることが問題となるでしょう。
この点について,判例は,反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上,反撃行為によって生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても,その反撃行為が正当防衛でなくなるものではないとしています(最判昭和44・12・4刑集23巻12号1573頁)。
最近の裁判例では,車内に手を入れられ,急発進させ,相手方の頭を轢き死亡させてしまったという事案で,裁判所は正当防衛の成立を認めています(東京地裁立川支部平成28・9・16)。
今回のAさんの場合も,似たような事案ですので正当防衛が認められる可能性は高いでしょう。
しかし,正当防衛が認められるには,正当防衛となることを適切に主張する必要があります。
正当防衛を正しく主張するには刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
あおり運転に対する行為で罪に問われ,正当防衛の主張をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
正当防衛となりうるのかといった見通しなどの無料法律相談・警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。
江南市でひき逃げ事件なら
江南市でひき逃げ事件なら
~ケース~
江南市在住のAさんは、江南市内の市道を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を右から左に渡っていたVさんの自転車と接触した。
接触自体は、Aさんの車の右前方のタイヤと、Vさんの自転車のっ前輪が軽く接触したのみであった。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは足を擦りむいている様子だったが「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんがその交差点を通りかかった際、ひき逃げ事件の目撃情報を求める立て看板が立っており、事故の日時がAさんがVさんと接触した日時と同じであった。
まさか自分がひき逃げ事件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~ひき逃げとは~
ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限りひき逃げに問われることになります。
また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります。
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げの罪に問われることになる可能性があります。
そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げとなります。
~ひき逃げをしてしまったら~
ひき逃げは、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げで公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。
その為、早期釈放や刑の減軽を目指すためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
無免許運転、人身事故で早期釈放なら
無免許運転、人身事故で早期釈放なら
~ケース~
刈谷市在住のAさんは、免許取消中にもかかわらず刈谷市内の一般道を走行していました。
そして、Aさんは交差点で信号無視をし、歩行者に接触する人身事故を起こしてしまった。
その後、駆け付けた愛知県警察刈谷警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕された。
Aさんは無免許運転で以前罰金刑を受けていることもあり、Aさんの今後が心配でたまらないAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~無免許運転とは~
無免許運転については、道路交通法第64条において
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
と規定されています。
そして、無免許運転には以下の4種類があります。
【純無免】
一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転すること
【取消無免】
免許の取り消し処分を受けた後に運転すること
【停止中無免】
免許の停止処分中に運転すること
【免許外運転】
一部の免許はあるが、運転しようとする車種に応じた免許を取得せずに運転すること(車の免許のみで、大型バイク等を運転する行為)
~無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合~
また、上記のケースのように、無免許運転という危険で悪質な運転によって人が死傷されるケースは厳罰化すべきという世論の高まりから、無免許運転により人を死傷させた場合は、自動車運転死傷行為処罰法によって処罰されることになりました。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法により、
⓵過失運転致死傷罪の懲役刑の上限は7年→無免許の場合には10年
➁危険運転致傷罪の懲役刑の上限は懲役15年→無免許運転の場合には20年
と刑が加重されます。
このように、無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、刑が加重されているだけではなく、身柄拘束を受けることも多いため、早期の釈放を求める場合には弁護士の力が不可欠です。
弁護士であれば、警察や検察官、裁判官に釈放を求めることができ、仮に、身柄拘束が継続しているとしても準抗告という制度によって釈放を勝ち取ることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や交通違反でも刑事処分に対する弁護活動のみ行っておりますので、無免許運転や人身事故を起こしてしまった場合でも安心してご相談いただけます。
無免許運転や人身事故で逮捕されてお困りの方、早期の釈放をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
名古屋市熱田区で運転過失建造物損壊罪なら
名古屋市熱田区で運転過失建造物損壊罪なら
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさん(60代)は、コンビニエンスストアの駐車場でアクセルとブレーキを踏み間違え店舗に突っ込んでしまった。
幸い,怪我人はいなかったが,店舗の駐車場に面するガラスが割れてしまった。
Aさんは、その場で愛知県警察熱田警察署の警察官に事情を聴かれただけだ逮捕等されることはなかったが,ゆくゆくは刑務所に行かなければならないのかと不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~刑事手続きの流れ~
刑事事件を起こしてしまった場合,一般的には逮捕されて刑務所に入れられるというイメージがあると思います。
しかし,実際には道交法違反を含む刑法犯の場合,起訴されるのは全体の33%程度となっています。
不起訴の多くは起訴猶予であり,初犯で軽微な犯罪であれば起訴猶予となる事が多くなっています。
刑事手続きでいう「逮捕」とは身柄拘束の一種であり,逃亡や罪証隠滅のおそれなどがある場合に認められます。
被疑者を逮捕した場合には48時間以内に検察官に事件を送致(送検といいます)する必要があり,送致を受けた検察官は被疑者を勾留するかどうかを決定します。
勾留は原則10日間,場合によってはさらに10日間の勾留延長がなされます。
ただし,勾留は逮捕に比べて身柄拘束期間が長くなりますので,逮捕に比べ要件の審査は厳格になっています。
勾留された場合,勾留満期の時点で検察かは起訴するかどうかを決定します。
したがって,勾留される事件は基本的に起訴される可能性が高いと考えられます。
~Aさんの場合~
今回のケースで、Aさんにはどういった罪が成立するのでしょうか。
Aさんは店舗のガラスを割ってしまっていますので器物損壊罪(刑法261条)が考えられます。
しかし,器物損壊罪は故意でなければ罰せられません。
Aさんは故意に店舗に突っ込んだわけではないので器物損壊罪とはならないでしょう。
また,店舗のガラスを割っているので建造物損壊罪(刑法260条)も考えられますが,こちらも故意でなければ罰せられません。
しかし,道路交通法第116条は「車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り,又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは,六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています(運転過失建造物損壊罪)。
運転過失建造物損壊罪の場合,条文からも明らかなとおり,過失であっても罰せられます(故意の場合は通常の建造物損壊罪となります)。
ここでいう「業務上」とは社会生活において反復・継続して行う活動をいいます。
今回のケースでAさんは、アクセルとブレーキを踏み間違えるという業務上必要な注意を怠っていますので、道運転過失建造物損壊罪に問われる可能性が高いです。
上述のように、刑事事件を起こしてしまい逮捕されるのは逃亡や罪証隠滅のおそれなどがある場合になります。
今回のケースで、Aさんはその場で逮捕されることはなかったのですから,後から逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕するという事は考えにくいでしょう。
ただし,警察からの取調べの出頭要請などを無視し続けたというような場合には逮捕されてしまう可能性は高くなります。
~刑務所に行かなければならないのか~
今回のケースで、Aさんが刑務所に行くことはあるのでしょうか。
刑務所は起訴され刑事裁判によって懲役または禁錮を言い渡された場合に行くことになります。
したがって,不起訴となった場合や罰金刑や執行猶予付きの判決の場合には刑務所に行くことは原則としてありません。
検察官が起訴するかどうかは犯罪の重大性,前科の有無,犯罪後の情状などによって総合的に判断されます。
今回のケースでは、怪我人が出ていないので成立する犯罪は運転過失建造物損壊罪のみであると考えられます。
運転過失建造物損壊罪の場合,被害店舗に建物の修繕費や休業補償などの被害弁償をすることによって、国家があえて刑罰を科す必要がないと考えられ不起訴となる可能性が高くなります。
一方で,修繕費などを一切支払わない場合には犯罪後の情状が芳しくないと判断され,起訴されてしまう可能性も高くなるでしょう。
起訴された場合,前科がなければ罰金刑となると思われますが,罰金が払えない場合には労役場留置といい,刑務作業をしなければなりません。
厳密には異なりますが,罰金刑であっても罰金を支払えない場合には刑務所に行くのとほぼ同様になります。
また,罰金刑となった場合でも店舗の修繕費の支払い義務など民事上の責任は負うことになります。
したがって,不起訴処分とするためにも早い段階で被害弁償をすることが重要です。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
自動車で何らかの事故を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
犯人隠避罪で情状弁護なら
犯人隠避罪で情状弁護なら
~ケース~
豊橋市在住のAさんは、自宅の外で大きな音がしたので、慌てて外に出てみると、Aさんの内縁の夫Bさんが運転する車が家の前の電信柱に衝突し止まっていた。
Bさんから酒を飲んでいることを聞かされたAさんは、Bさんが逮捕・処罰されてしまうのを避けるため、通報により駆け付けた愛知県警察豊橋警察署の警察官に対して、Aさんが運転をして事故を起こしたと虚偽の申告をした。
その後、Aさんは愛知県警察豊橋警察署に任意同行を求められ、取調べを受けた。
取り調べの中で、Aさんが運転していたという申告が虚偽であることが発覚し、Aさんは犯人隠避罪の容疑で捜査を受けることになった。
今後どうなるのか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~犯人隠避罪とは~
犯人隠避罪については、刑法第103条において「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ここでいう「隠避」とは、場所を提供して匿う以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為をいいます。
そのため、変装道具を渡す行為、逃走資金を与える行為、身代わり犯人を立てる行為も隠避にあたります。
また、犯人隠避罪における「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に罰金以上の刑罰が含まれている犯罪のことです。
したがって、犯罪のうち法定刑が拘留または科料だけが規定されている犯罪の場合、犯人隠避罪に問われることはありません。
そして、「罪を犯した者」の意味については、学説上様々な考え方がありますが、最高裁判例では、犯罪の嫌疑によって捜査中の者を含み、捜査開始前の真犯人も含むとします。
そのため、真犯人であっても、公訴時効が完成した者、親告罪の告訴期間が過ぎた者については、訴追・処罰の可能性がないため、犯人隠避罪の対象になりません。
ただし、不起訴処分を受けたにとどまる者、まだ親告罪の告訴がされていないだけの者については、訴追・処罰の可能性があるため、犯人隠避罪の対象になります。
上記のケースにおいて、Aさんは身代わり犯人として自身が犯人であると虚偽の事実を警察官に対して申し立て、その犯人捜査を妨害しているので、犯人隠避罪が成立する可能性が高いです。
~犯人隠避罪における弁護活動~
ただし、犯人隠避罪には親族に対する特例が設けられています。
刑法第105条において「前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」という規定があります。
これによれば、犯人の親族が犯人隠避行為をした場合にはその親族の刑を免除することができるとされています。
しかし、内縁関係にある者についてはこの制度は適用されないと一般的に考えられているため、Aさんにはこの特例の適用はありません。
ただし、親族に対する特例が設けられている趣旨としては、犯人や逃走者の親族が犯人蔵匿罪、犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情に由来するからだとされています。
そのため、例え内縁関係であったとしても、実際に生活を共にし、婚姻関係にある夫婦と何ら変わりのない関係性であったことが考慮されれば、Aさんにとって有利な情状となる可能性があります。
さらに、被疑者の反省の態度等を的確に捜査機関い伝えることが出来れば不起訴になる可能性を高めることに繋がりますし、仮に起訴された場合であっても、情状証人による嘆願などの情状弁護により、執行猶予付き判決や減刑を求めることも十分可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任し活動しておりますので、犯人隠避罪や情状弁護といった刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
犯人隠避罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。