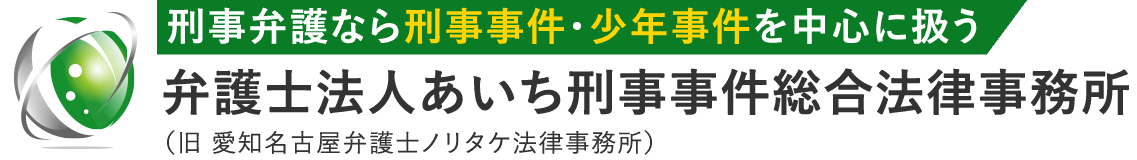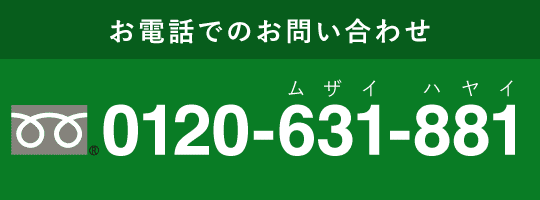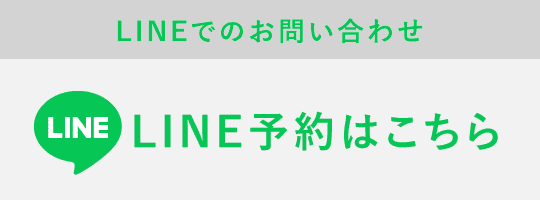Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
【解決事例】蒲郡市の器物損壊事件で勾留延長阻止と不起訴処分獲得
器物損壊事件で勾留延長を阻止し、不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、ゲームセンターで店員と口論になり、カウンターにあった時計を手でたたいて壊したとして、愛知県蒲郡警察署に器物損壊罪で逮捕・勾留されました。
奥様は、「ご迷惑をお掛けしたゲームセンターに謝罪をしたく電話をしたのですが、謝罪は受けないと言われました。これからどうしたらよいのでしょうか。」と、相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害店舗様に対し、「加害者の奥様が、謝罪文を作成したので受け取って欲しい」旨を伝えたところ、「弁護士からでしたら構いません」とのお返事を頂き、加害者の奥様が書かれた謝罪文を被害店舗様に渡しました。。
その結果、被害店舗様より「①当ゲームセンターには二度と近づかないこと、②壊した時計代1万円を弁償すること、それができれば、被害届を取り下げます」とのお返事を頂きました。
被害店舗様より提示された条件で、示談が成立し、その結果、被害届は取り下げられることとなりました。
その後被害店舗様と取り交わした示談書、被害届取下げ書を検察庁に提出し、その結果、当日中にご本人様は釈放、不起訴処分となりました。
【まとめ】
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者が被害届や告訴を取り消すと、「親告罪の告訴の欠如」となり、加害者が処罰されることがなくなるのです。
ですので、器物損壊罪の場合は、示談が成立し被害者に被害届を取り下げてもらえれば、確実に前科になることを避けられるのです。
となれば、「一刻も早く被害者と示談がしたい!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、事例のように、加害者の家族等から直接被害者に示談を持ちかけようとしても、拒否されることも多く、「弁護士なら話を聴く」と被害者に言われることも多いのです。
また、直接当事者同士で示談をしようとすると、感情的になり難航したり、相場と大きく剥離した示談金の額を提示されたり、示談が成立したとしてもそれが法律的に無効で、後日事件を蒸し返されるケースもあるのです。
法律のプロである弁護士ならば、法律的な見地から、安全・確実に示談の成功率を上げることができるのです。
器物損壊事件で被害者と示談がしたい、不起訴処分になりたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。
【解決事例】不起訴処分の獲得による有利な事件解決
今回は、不起訴処分によって傷害事件を有利に解決する弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市にある居酒屋でお酒を楽しんでいたAさんは、隣席の客Vさんのマナーに立腹し、苦情を申し入れました。
ところが、不服に感じたVさんはAさんに反論し、AさんとVさんは口論となってしまいました。
カッとなったAさんは、手提げカバンでVさんの顔面を殴打したところ、Vさんは軽い擦過傷を負いました。
店主の通報によって駆け付けた安城警察署の警察官により、Aさんは傷害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【傷害罪について解説】
傷害罪とは、その名の通り、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
Aさんは手提げカバンでVの顔面を殴り、軽い擦り傷を負わせていますが、このような擦り傷も傷害罪にいう「傷害」に該当します。
暴行によって傷害を負わせてしまった場合には、Aさんにおいて被害者を傷害するつもりがなくても傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【ケースの事件を有利に解決する方法】
ケースの事件においては、①早く外に出ること、②刑罰を受けないようにすることが重要です。
①に対応する弁護活動として、身柄解放活動への着手が挙げられます。
そして、②に対応する弁護活動として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
まずは、身柄解放活動の説明のため、逮捕後の手続を概略することにいたします。
(逮捕後の手続)
Aさんに留置の必要があると認められた場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
【身柄解放活動とは】
身柄解放活動とは、早期の身柄解放を目指して行われる弁護活動です。
先述した逮捕後の手続には、Aさんの身体拘束を継続するか否かを判断する機会が複数存在します。
もし、早い段階(送致前や勾留請求前)で釈放されれば、社会復帰を円滑に遂げられる可能性が高まります。
【刑罰を受けないようにするためには】
ケースの事件が傷害被告事件として起訴され、有罪判決を受ける場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を言い渡されることになります。
懲役刑や罰金刑を受けた事実は前科となってしまいます。
このような事態を回避するためには、そもそも裁判にかけられないようにするために、「不起訴処分」の獲得を目指す弁護活動が考えられます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
有罪を立証する証拠が十分に収集できなかった場合や、事件後の被疑者の状況(事件の経緯、被害者への賠償の有無、反省の態度、身元引受人の状況)を考慮し、検察官が不起訴処分とする場合があります。
ケースの場合、不起訴処分を獲得するためにはVと示談をすることが考えられます。
Vに対して謝罪をし、生じさせた損害(治療費や慰謝料など)を賠償した上、示談を成立させることができれば、不起訴処分がなされる可能性が高まります。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
現住建造物等放火罪と逆送
現住建造物等放火罪と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
17歳のAさんは以前から火が大きく燃え上がるのを見てみたいと思っており、どこかに火をつけようとしていました。
ある夜Aさんは愛知県知多市のVさん宅の軒下にあるVさんの自転車のサドル部分にライターで火をつけ、炎が上がったのを確認して近くからそれを見ていました。
炎はVさん宅の軒下部分に燃え移り、軒下の一部が燃え始めましたが、AさんはVさん宅に燃え移っても別にいいと思っていました。
結局Vさん宅は全焼し、この家に住むVさんは亡くなりました。
Aさんは現住建造物等放火罪などで愛知県知多警察署に逮捕されましたが、Aさんの両親が少年事件について調べた結果、未成年でも刑事処分になることがあると知り、少年事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【放火の罪について】
放火の罪には様々な種類があります。
条文を見ていきましょう。
・現住建造物等放火(刑法第108条)
放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火(刑法第109条)
1放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の懲役に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建造物等以外放火(刑法第110条)
1放火して、前2条(108条、109条のこと)に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
(対象物は、自転車、バイク、航空機、門、塀、橋、畳、机、椅子、ゴミ箱などです。)
いわゆる「放火の罪」の条文はこのようになっていますが、
放火はしたものの「公共の危険」が発生しなかった時は器物損壊罪となります。
※「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命、身体、財産に危険を生じさせる状態のことをいいます。
判断基準は、火力の程度、他人の住居などの隣接状況、当時の風向き、風速、気温などの気象状況、昼間か夜間化などの事情によります。
【放火の罪のそれぞれの違い】
①現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪を分けるものは、「現に人が使用している(人とは犯人以外の一切の人のこと)」または「人が現在している(現在とは放火の当時犯人以外の者が中にいること)」かそうではないかです。
②建造物等以外放火罪と現住建造物等放火罪を分けるものは、現住建造物等の一部でも焼損したか否かとその故意を有していたかです。
【逆送とは】
Aさんの両親が調べた、「未成年でも刑事処分になることがある」とは「逆送」のことです。
逆送とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致することです。
このことを検察官送致決定といい、「逆送」といわれています。
家庭裁判所から刑事処分相当として検察官に送致された場合、検察官は、公訴提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思慮するときは起訴しなければならないとされています。
逆送される理由は2つあり
①年齢超過を理由とする(年齢超過逆送)
②刑事処分相当を理由とする(刑事処分相当逆送)
があります。
①の年齢超過を理由とするについては、審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は逆送しなければなりません。(犯行時、逮捕時の年齢ではありません。)
②の刑事処分相当を理由とするについては、家庭裁判所は、死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。
また、犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にあたる事件の場合には、原則として検察官に送致しなければならないとされています。
なお14歳未満の者は刑事責任能力がないとされているため、逆送されることはありません。
上記の理由により、Aさんに対しても逆送される可能性は高いと思われます。
しかし、少年事件に強い弁護士は逆送をされないために様々な弁護活動を行っていきます。
具体的には、家庭裁判所の裁判官に対し、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していきます。
まず「刑事処分が相当である」とは、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みがない場合(「保護不能」といいます。)があります。
それに加え、事案の性質、社会感情、被害者感情等から、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合(「保護不適」といいます。)があるといわれています。
つまり、少年は保護処分により更生できることを主張を家庭裁判所の裁判官に主張し、更に事案の性質、社会感情、被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを、具体的な事情を踏まえて主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、放火の罪、現住建造物等放火罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が放火の罪、現住建造物等放火罪で話を聞かれることになった、または逮捕されてしまった、逆送を防ぎたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
器物損壊罪と環境を整えること
器物損壊罪と環境を整えることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(18歳)は愛知県一宮市にあるV株式会社に勤務していましたが、暴走族や不良仲間との付き合いがあることや素行不良等を理由に、最近解雇されました。
Aさんがこれを不良仲間に話すと、「会社に何か仕返しをしてやれよ。」と言われたので、AさんはV株式会社の看板を壊してV株式会社に嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんはある日の夜中にV株式会社の看板を外して持ち去り、約500メートル先の広場でその看板をハンマーでたたき割って逃げました。
翌日、広場で愛知県一宮警察署の警察官が割られたV株式会社の看板を発見し、器物損壊罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです)
【看板を持ち去っていても器物損壊罪?】
Aさんは看板を「持ち去って」いるので、泥棒=窃盗罪になるのではと考えるかもしれません。
しかし、窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。
「不法領得の意思」とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用しまたは処分する意思」のことです。
つまり、持ち去ったものを経済的に用法に従って利用、処分する意思があれば窃盗罪が成立するということです。
Aさんは持ち去った看板を利用する意思が全くなく、不法領得の意思は無いと思われるので、窃盗罪ではなく器物損壊罪(叩き割っている)が成立すると思われます。
器物損壊罪(刑法第261条)
前3条に規定するもの(公用文書や私有文書、建造物)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがある→窃盗罪
・他人の物を持ち去る→経済的に利用、処分するつもりがない→器物損壊罪
【環境を整えること】
少年事件の場合は家庭環境、生活環境を整えることも大切になります。
Aさんの場合は、犯行のきっかけの一つに、不良仲間に「仕返しをしてやれよ。」と言われたことがあります。
このように、暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が重要となります。
生活環境を改善するためには、ご家族や保護者の協力が不可欠となることから、ご家族や保護者には日常生活の中で本人を監視監督してもらうことになるでしょう。
生活環境が改善したかどうかは、少年が起こした事件への適切な処分が出されるかどうかに大きく関わってきます。
お子様が事件を起こしてしまったなど、少年事件でお困りの方は逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、ぜひ少年事件、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
少年事件の流れ、刑事処分の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など「こんなことも聞いていいのだろうか…」と思うことなく、何でもお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が器物損壊罪で話を聞かれることになった、子供が事件を起こしたけれど家庭環境、生活環境を整えたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈
ヘロインと強盗殺人未遂罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは違法薬物の売人であるVさんに対し、待ち合わせ場所の愛知県春日井市の路地裏で代金を支払う意思がないのに「ヘロインを売ってくれ」と頼みました。
AさんはVさんからヘロインを受け取りましたが、Aさんは代金支払いを免れるために出刃包丁でVさんの腹部を刺し逃走しました。
Vさんは通行人に救助され一命をとりとめましたが、Aさんは強盗殺人未遂罪と麻薬及び向精神薬取締法違反で愛知県春日井警察署に逮捕・勾留され、その後起訴されていますが、Aさんの家族はAさんが刑務所に行く前に一度自宅に帰ってきてほしいと考えています。
(フィクションです)
【ヘロインとはどのようなものですか?】
ヘロインとは、けしを原料とした薬物のことで、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られており、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。
モルヒネになる前のあへんとは、けしから採取した液を凝固させたもののことです。
原料であるけしの栽培やあへんの採取、あへん及びけしがらの輸出入、所持などは「あへん法」により規制されています。
ヘロインは、強い精神的・身体的依存が特徴の薬物で、ヘロインを使用すると強い陶酔感や快感を覚えます。
しかし、2~3時間ごとに摂取しないと、体の激しい痛み、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状が起こります。
また大量に摂取すると死に至ります。
ヘロインについては、医学的な使用も一切禁止されています。
ヘロインの所持については、麻薬及び向精神薬取締法に規定があり
営利目的が無ければ、法定刑は10年以下の懲役です。
営利目的があれば、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
【強盗殺人未遂罪について】
このような事例については既に判例があり、
「違法薬物をだまし取った後に、代金支払いを免れるために殺人を行おうとしてこれが未遂に終わった場合、代金支払いを免れるという財産上不法の利益をえるためにされたものである以上、この行為は詐欺罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。」とあります。(最高裁判所昭和61年11月18日判決)
※2項強盗とは、刑法に「強盗罪」として規定される行為のうち直接的な「財物の強取」ではなく、代金の支払い拒否などの「経済的利益を不当に奪い取る」ことを目的として行われる強盗行為のことを言います。
強盗罪が規定されている刑法第236条の「第2項」に規定されているため「2項強盗」と呼ばれています。
【Aさんは自宅に帰ることができるのか】
警察署に留置され、起訴されているAさんが自宅に帰るには「保釈」という制度を利用することになります。
保釈とは、身柄拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度です。
保釈には、必要的保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類がありますが、いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈請求が行われた場合、刑事訴訟法第89条に記載されている事項を除いて、裁判所は保釈を許さなければならないとしています。
刑事訴訟法第89条には
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
とあり、つまりこれに該当しない時は保釈が認められるということです。
ただし、薬物事件においては上記の③と④に該当すると判断される可能性が高いため、特に薬物事件において保釈を希望されるときは弁護士にしっかり主張してもらうのがよいでしょう。
また、上記の89条の保釈が認められなくても、刑事訴訟法第90条に基づく保釈を請求することができます。
刑事訴訟法第90条に基づく保釈とは、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとしていることで、裁判所の裁量により行われる保釈です。
しかし、裁判所の職権で保釈の判断がされるため、これもやはり弁護士に裁判所に対ししっかりと主張してもらうことが大切です。
また、保釈請求が認められたとしても、保釈金を裁判所に預り金として支払わなくてはなりません。
保釈金は仮に後の裁判で有罪判決を受けたとしても裁判所から返還を受けることができますが、保釈金の金額については、人それぞれですので、一概に金額を見積もることは困難です。
また、薬物事件の場合は再犯率や逃走の恐れの観点から、保釈金は高額になる傾向があります。
最後に職権保釈についてですが、職権保釈とは刑事訴訟法第91条に基づいた、勾留による拘禁が不当に長くなった場合には、保釈を許さなければならないというものです。
保釈を希望される方は、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件や強盗殺人未遂罪で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
【解決事例】愛知県豊田市の軽犯罪法違反事件で不送致処分を獲得
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は、車のトランクに角材を隠し持っていたとして、警察官から職務質問をうけ、その後軽犯罪法違反の容疑で取調べを受けていました。
ご本人様は、「角材については、トランクが開かないように車屋さんがとりつけてくれたものです。それなのに警察官は、『けんかをする時に、武器として使用するために角材を車のトランクに入れていた』という内容の供述調書にサインをさせようとしてきました。これからどうしたら良いのかとても不安です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様に対し、被疑者には①取調官の質問に対し、無理にこたえなくても良い権利(黙秘権)がある、②供述調書の内容に納得できないときには、署名押印を拒否すること(署名押印拒否権)も認められている、③供述調書の内容を修正して欲しい場合、取調官に調書の修正を求めること(増減変更申立権)ができる、ことを伝え、また、もし取調官から、違法・不当な取り調べを受けた際は、すぐに弁護士を呼ぶことも伝えました。
また、警察に対し、トランクに角材を取り付けたいきさつ等について説明し、ご本人様は、軽犯罪法第1条2項にある「正当な理由が無くて刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯する者」にはあたらない旨を主張した結果、ご本人様は不送致処分となりました。
【まとめ】
捜査機関(警察署や検察庁)は、取調べで自白が取れると、後の捜査や裁判がやりやすくなるので、積極的に自白を取ろうとしてくることもあります。
そのため、中には違法、不当な取り調べをしてでも、自白をさせようとする取調官がいる可能性もゼロではありませんし、長時間の取調べや、場合によっては暴力によって自白をさせようとすることもあるやもしれません。
もちろん、このようなことがあれば、弁護人より取調べの録画を申し入れたり、捜査機関に抗議を行うなど、適切に対応することも可能です。
違法、不当な取調べを受けた、やってもいないことをやったという供述調書を作られた、など、取調べでご不安なことがあれば、取調べ対策に強い弁護士に早急にご相談ください。
違法、不当な取調べを受けた、不送致処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。
髪を切ることと暴行罪
髪を切ることと暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
18歳のA君は海外から帰ってくる恋人のVさんに会うため、名古屋市中村区にある駅の待合室にいました。
しかし、VさんはA君に会うなり、「Bさんと結婚するから別れてくれ」と言い、A君とVさんは口論となりました。
A君はVさんに恥をかかせてやろうと思い、駅構内のコンビニエンスストアでハサミを購入した後、Vさんの髪をつかみ、購入したハサミでVさんの髪を無理矢理切り落としました。
A君はVさんの悲鳴を聞いて駆けつけた、愛知県中村警察署の警察官に取り押さえられ、「暴行罪で話を聞かせてもらう」と言われました。
A君の両親は、今まで警察に一度もお世話になったことはないし、どうしたらいいのかわからないと思い少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
【髪を無理矢理切るのは暴行罪になりますか】
暴行罪とは、人の身体に対し、有形力を行使したが、人の生理機能に障害を与えなかったり、健康状態を不良にしなかった場合に成立します。
条文は
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。(刑法第208条)
となります。
A君はVさんに対し、ハサミで無理矢理髪を切るという有形力の行使を行いました。
しかし、髪を切り落とされても、生理機能や健康状態を傷害・不良にすることはないとされますので、暴行罪となる可能性があります。
有形力の行使とは、殴る、蹴る、投げ飛ばす、服をつかんで引っ張る、人の前を狙って石を投げる、拡声器を使い耳元で大声を出す、などがあります。
また、生理機能に障害を与えるとは、怪我をさせる、精神衰弱症にさせる、睡眠障害を負わせる、急性アルコール中毒にさせる、などがあります。
ただし、Vさんに治療を必要とするPTSD(心的外傷後ストレス症候群)が見られた場合は傷害罪となる可能性があります。
【弁護活動について】
A君に対しては、より適切な処分を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。
【審判不開始決定】
審判不開始決定とは、少年事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは審判に付するのが相当ではない場合に審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます。
審判に付すことができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、審判に付するのが相当ではない場合とは、事案が軽微であったり、家庭裁判所に送致された段階で少年が十分に反省しており要保護性がなくなったりしている場合のことです。
審判不開始処分となった場合は、その時点で事件は完結し、少年審判が開かれることはありません。
ですので、少年事件に強い弁護士は少年が更生していることや、少年の家庭環境、生活環境に問題がないことなどを家庭裁判所に伝え、審判不開始決定となるように働きかけることになります。
【不処分決定】
不処分決定とは、少年事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所における調査の結果、保護処分に付することができない場合、また保護処分に付するまでの必要がない場合に、審判で保護処分に付さない決定をすることをいいます。
保護処分とは少年院送致や保護観察のことで、不処分決定がされると、それらを受けることなく事件が終了します。
保護処分に付することができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、保護処分に付するまでの必要がない場合とは、審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけにより、少年の問題点が改善され、再非行の危険性がなくなったと認められる場合のことです。
ですので、少年事件に強い弁護士は、調査官や裁判官と協議し、付添人としての少年に対する教育的な働きかけによって、問題点が改善され、再非行の危険性はないと家庭裁判所に主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、早急に弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、誰でも見ることができるインターネットの掲示板に「Vはクズな男だ、あんな奴なんで生きてるんだろう。」などとVさんの実名を挙げて書き込みをしました。
数週間後、Vさんが居住する愛知県豊山町を管轄する愛知県西枇杷島警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、Aさんは侮辱罪で愛知県西枇杷島警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【インターネットで他人を誹謗中傷することについて】
インターネット社会が発展するに伴い、他人を誹謗中傷する内容がインターネットの掲示板やSNSに書き込まれることが増加しています。
インターネットで不特定または多数人が閲覧できる場合、名誉棄損罪か侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪では次に述べますとおり、法定刑に大きな違いがあります。
【名誉棄損罪】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(刑法第230条第2項)
【侮辱罪】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。(刑法第231条)
※侮辱罪につきましては、厳罰化が検討されており、罰則を「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」とする予定があります。
【名誉棄損罪と侮辱罪の共通事項】
名誉毀損罪と侮辱罪には、共通している部分もあります。
以下ではその共通事項を確認してみましょう。
1 人の名誉
名誉毀損罪と侮辱罪の条文にある「人」とは、行為者以外の自然人、法人、その他の団体をいい、「名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の価値に対する社会的評価をいいます。
人の倫理的価値(品性)、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、身分、家柄など社会において価値があるとされるものが含まれますが、人の経済的な支払い能力に対する評価(信用)は、信用棄損罪の対象となります。
2 公然
「人」同様、名誉毀損罪と侮辱罪の条文には同じく「公然」という言葉が使われています。
これは、不特定または多数人の認識しうる状態をいい、「不特定」とは相手方が特殊な関係によって限定されたものでないことをいい、摘示の相手方は特定かつ少数であっても、伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれます。
3 親告罪
名誉棄損罪、侮辱罪とも親告罪です。
親告罪とは、被害者などの告訴権者が告訴をしなければ起訴できない犯罪のことをいいます。
【名誉棄損罪と侮辱罪の違い】
では、ここまで確認してきた名誉毀損罪と侮辱罪の共通事項に対して、2つの犯罪で異なる部分はどういった部分なのでしょうか。
1 事実の摘示について
名誉棄損罪は、「事実を摘示して、人の名誉を毀損する」ことで、人の社会的評価を低下させる恐れのある具体的事実を指摘、表示することをいい、単なる価値判断や評価は含まれません。
また、摘示される事実は、その真否を問わないし、公知の事実でもよく、また事実を摘示する方法に制限はなく、口頭、文書、写真(わいせつな写真と顔写真の合成)などがあります。
「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価を低下させる恐れのある状態を作ることをいい、現実に社会的地位が傷つけられたことは必要ではありません。
一方、侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、人を侮辱する」ことで、具体的事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断、批判を表現することをいいます。
表現補法に制限はなく、口頭、文書、動作などによってもかまいません。
2 故意
名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容が必要です。
侮辱罪は、事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することの認識・認容が必要です。
3 違法性の阻却
名誉棄損罪にのみ規定があり、①摘示事実が公共の利害に関する事実であること(事実の公共性)②その目的がもっぱら公益を図るためであること(目的の公益性)③摘示事実が真実であることの証明があったこと(事実の真実性)の場合に違法性は阻却されます。
【刑事事件例について】
Aさんは誰でも見ることができるインターネットの掲示板に(=公然)、「Vはクズな男だ」と具体的な事実ではなく、抽象的な評価を示して、Vさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしています(=事実を摘示することなく侮辱)。
よって、Aさんには侮辱罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
インターネットにおける誹謗中傷に関する犯罪は、名誉棄損罪であれ侮辱罪であれ、被害者が存在します。
よって、被害者との示談交渉が大変重要になってきます。
示談交渉とは、当事者同士で話し合って解決を模索することですが、加害者本人が示談交渉をすることはほぼ不可能ですし、ほぼ弁護士にしかできません。
被害者が刑事告訴を考えていた時、示談交渉をして刑事告訴をしないように働きかけることもできます。
名誉毀損罪や侮辱罪は上記のとおり親告罪ですので、示談交渉の前に被害者が刑事告訴をしていた場合でも告訴を取り下げてもらうことができれば不起訴になります。
ご自身やご家族がインターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい心配だという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊山町の名誉棄損罪や侮辱罪で話を聞かれることになった、またはインターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕されてしまったら
愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕されてしまったら
愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県一宮市内で、愛知県一宮警察署の警察官Vさんが交通違反の取締りをしている現場に遭遇しました。
Aさんは以前、Vさんに酒酔い運転で逮捕されたことがあり、それを恨んでいました。
そこでAさんはVさんに仕返しをしてやろうと思い、Vさんの背後に近寄りいきなり殴りつけましたが、近くにいたVさんの同僚のBさんに取り押さえられ、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第95条第1項)
1 意義
公務執行妨害罪にあたる行為とは、公務員が、その職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加える行為をいいます。
2 保護法益
公務執行妨害罪は、公務員を特別に保護する規定ではなく、公務そのものを保護するものです。
つまり、公務員という人個人を守っているわけではなく、その公務員が行う仕事(公務)が公務執行妨害罪の保護対象となっているのです。
3 構成要件
①主体
公務執行妨害罪の主体は何人でもよく、公務員と関係の無い第三者でも主体となります。
②客体
公務執行妨害罪の条文にいう「公務員」とは、官吏、公使、および法令により公務に従事する議員、委員、その他の職員を指し、一般にイメージされる「公務員」と大きな差はないと思われるかもしれません。
しかし、公務員という身分を有しませんが、法令により公務員とみなされた日銀、外国為替銀行の職員等も「公務員」に含まれるため、全く一般のイメージ通りということにならない場合もあります。
そして、公務執行妨害罪の「公務」とは、国または地方公共団体の事務をいい権力的性質を持っている必要はありません。
こうした「公務員」「公務」については、ある程度精神的知能的な判断を要する仕事に従事していることを必要とし、単純な肉体的機械的労務だけに従事しているものは含まれません。
③行為
公務執行妨害罪の条文中にある「職務を執行するにあたり」とは、立法・行政・司法上の「執務」であればよく、「執務に際して」とは、仕事場へ赴くときや休憩中はこれにあたりません。
ただし、仕事を開始しようとするとき、待機、雑談中のときは「職務を執行するにあたり」という状況に当てはまると解されていますから、公務執行妨害罪のいう状況に当たるか判断するためには、より詳細な状況を把握し検討する必要があります。
また、条文には「暴行または脅迫を加える」とありますが、これは直接的間接的に相手の身体に対する有形力を行使したり畏怖させるための害悪の告知を行ったりすることで、方法は明示、黙示、口頭、文書などの形を問いません。
さらに、これらの暴行・脅迫が加えられるタイミングは職務執行の際であることが必要で、現にその公務が妨害される必要はなく、また公務員に対し直接的に暴行・脅迫を加えることを必要とせず関係者に対するものでも行為にあたります。
【「公務」の適法性について】
1 「公務」は適法な職務執行であることが必要
公務執行妨害罪の行為者が公務員の適法な職務執行を違法であると誤信し、暴行・脅迫にでた場合には、判例はこの錯誤を法律の錯誤とし、故意は阻却しないとしています。
2 適法性の要件
公務執行妨害罪にいう「公務」は、公務員の行為が職務の範囲内であること、法律上の諸要件を具備していること、そして法律上の重要な法定の方式、手続きが正しく履行されていることが必要です。
なぜなら、公務執行妨害罪が保護しているのはあくまで適法に行われている公務であり、違法に行われた公務まで保護する必要はないからです。
3 誤逮捕の場合の適法性
例えば、「公務」にあたるものが逮捕であり、その逮捕が誤逮捕であったような場合、その時の状況に立ち返って、合理的な理由があって逮捕する対象者を間違えたのは仕方がないと評価されたときには、「公務」は適法となり、公務執行妨害罪が成立します。
【故意や既遂時期について】
公務執行妨害罪の成立には、暴行・脅迫自体の認識があればよく、妨害する意思までは必要とされていません。
また、客体が公務員であることを認識する必要があり、さらに職務執行中である認識も必要です。
そして暴行・脅迫を加えられることにより直ちに公務執行妨害罪の既遂となります。
【刑事事件例について】
Aさんは、Vさんに対し殴るという暴行を加え、Bさんに取り押さえられていることから、その暴行は公務の執行を妨害する程度だったといえます。
Aさんは、Vさんの交通取締りという公務の執行を妨害する意思はなかったかもしれませんが、Vさんが警察官という公務員であることを認識しており、さらにVさんが交通取締りという職務を執行しているに当たりそれに対し暴行を加えるという認識をしていることは間違いありません。
こうしたことから、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き10日間(延長されると最大20日間)に及ぶ勾留がなされる可能性があります。
更にAさんが勾留され、その後起訴された場合は裁判が終了するまで引き続き警察署の留置場もしくは拘置所において勾留されることになります。
弁護士の活動としては、Aさんが勾留されないように、また勾留されても釈放されるように、検察官の勾留請求や裁判所の勾留決定に対して意見を提出したり不服を申し立てることなどが考えられます。
仮に起訴された場合には、裁判所に対し保釈請求を行い、身柄解放を目指していくことも可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県一宮市の公務執行妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県南知多町の殺人事件を相談
愛知県南知多町の殺人事件を相談
愛知県南知多町の殺人事件を弁護士に相談するというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県南知多町にある海岸のすぐそばに住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ているところを発見しました。
Aさんは、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんをすぐ近くの海岸まで運んで放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
こうした状況から、Aさんの家族は、刑事事件に対応している弁護士に、事件のことを相談してみることにしました。
(フィクションです)
【殺人罪】
殺人罪とはどのような犯罪なのか確認してみましょう。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法第199条)
殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。
①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。
・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。
②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。
【未必の故意について】
未必の故意とは何でしょうか?
詳しく見ていきましょう。
未必の故意とは、計画的に犯罪を行おうとする意図はないが、結果として犯罪行為に及んでも仕方がないと思い犯行に及ぶ心理状況のことです。
「未必の故意」は、最初は犯行を希望していません。
つまり、当初は確定的な殺意や動機がないということです。
しかし、自分がこれから罪となる行為をしてしまい、また相手を傷つけてしまうという可能性を認識しながら、「結果的に犯罪に及んでも構わない、差支えない。」と思うことを指します。
犯罪となる事実が発生する危険性があると思いながら、もしそうなってもそれで良いと思うのが「未必の故意」です。
【刑事事件例について】
Aさんが「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思いVさんをすぐ近くの海岸に放置した行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識しています。
なおかつ、Aさんはそれを容認したものであるので、ここにおいて未必の故意が認められAさんは殺人罪の罪責を負うことになります。
【Aさんが早期に家族と会うには】
逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
また弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪で逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。