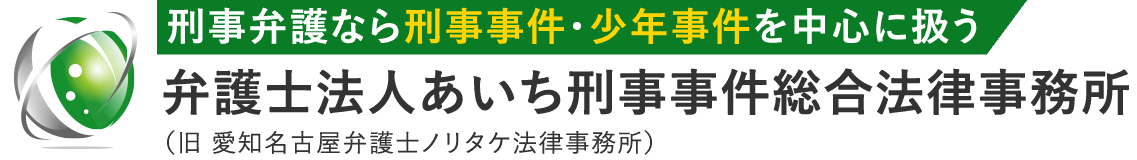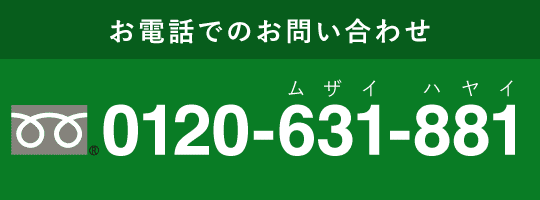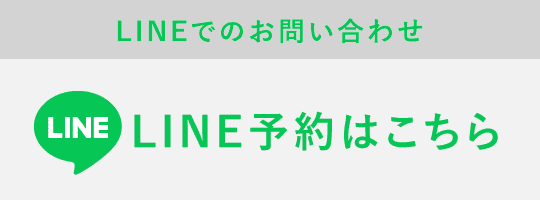Author Archive
スキミングで逮捕されたら
スキミングで逮捕されたら
~ケース~
小牧市在住のAさんは、お金に困っていることを高校時代の先輩であるBさんに相談したところ,Bさんから「このクレジットカードを貸してやるからしばらくはこのカードで生活すればいい」と言われクレジットカードを受け取った。
AさんはBさんから受け取ったクレジットカードを使い,日用品や食料品などを購入した。
後日,Bさんはクレジットカードのスキミングをしていた疑いで愛知県警察小牧警察署に逮捕された。
AさんがBさんから受け取ったクレジットカードは、スキミングにより作成されたクレジットカードであった。
そのため,Aさんも愛知県警察小牧警察署において事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~支払用カード電磁記録不正作出~
クレジットカードは、磁気情報によりカードを識別しています。
したがって,まったく同じ磁気情報をカードに登録することができれば、クレジットカードを作成できることになります。
そのため,クレジットカードを使用する際には、本人確認として暗証番号やサインなどが求められます。
支払用カード電磁記録の不正作出とはいわゆるスキミングのことを指します。
スキミングに関する条文は刑法163条の2から5までに規定されています。
163条の2は、スキミングをしてカードの不正な作成を禁止しており,これによって作られたカードの譲渡,貸与,輸入も禁止されています。
また,不正に作成されたカードの所持は163条の3によって禁止されています。
スキミング行為そのものは不正作出準備罪として163条の4に規定されており,未遂も罰せられます(163条の5)
今回のケースで、Bさんはクレジットカードを何らかの方法でスキミングしカードを不正に作成しAさんに譲渡していますから、支払用カード電磁記録不正作出罪および同譲渡罪(163条の2第1項および3項)が成立します。
~Aさんの罪状~
今回のケースで、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
Aさんは、Bさんが不正に作成したクレジットカードを受け取っていますので、不正電磁的記録カード所持罪(163条の3)が成立しそうです。
ただし、刑法は故意責任が原則となっており、刑法38条は「罪を犯す意思がない行為は,罰しない。」と定めています。
Aさんはカードの所持そのものは自分の意思で持っているといえますので故意がなかったということはできないでしょう。
しかしながら,AさんはおそらくBさんがスキミングによって不正に作成したカードであると知らなかったと思われますが,このような場合にも犯罪は成立してしまうのでしょうか。
判例は,違法性の意識は犯罪の成立要件ではないという立場をとっています(最判昭和25年11月28日刑集4巻12号2463頁)。
そのため,仮にAさんが違法でないと思い込んでいたとしても不正電磁的記録カード所持罪は成立してしまいます。
ただし,違法性の認識を欠いたことについて相当の理由が有る場合には故意を欠くので責任が阻却されるという下級審もあります。
今回のケースで、Aさんはクレジットカードを受け取っているわけですから,少なくとも違法性の認識がまったくなかったということは難しいでしょう。
また,Aさんは少なくとも自分の名義ではないクレジットカードを使用しているのですから詐欺罪が成立することも考えられます。
判例は,他人名義のクレジットカードを使用した時点で詐欺罪が成立するとしています(最二判平成16年2月9日刑集58巻2号89頁)。
なお,家族間でのクレジットカードの使用についても最高裁によると厳密には詐欺罪を構成することになりますが,現実的に被害が発生しておらず事件化しない場合が多いと思われます。
また,仮に事件化されたとしても家族間での使用である場合等は検察官は事件を不起訴とすると思われます。
~弁護活動~
今回のケースではAさんはBさんから受け取ったクレジットカードが不正作成されたものであったと知らなかったと思われますので,情状弁護としてその事情を主張していきます。
また,他人名義のクレジットカードによって買い物をした詐欺罪については,店舗もしくはカード会社または真正な名義人に対して被害弁償をすることが重要です。
詐欺事件では被害者への被害弁償の有無が執行猶予付きの判決となるかどうかに大きく影響します。
クレジットカードを借りて事件に巻き込まれてしまった場合には,できるだけ早くお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士が多数所属しています。
フリーダイアル0120-631-881で初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら
風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんは、尾張旭市内で自らが違法に営むソープランドにおいて、未成年の女性Vさんを働かせる目的で勧誘したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察守山警察署に逮捕された。
当日、愛知県警察守山警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの妻は、少しでも早く釈放して欲しいと言う一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~職業安定法とは~
そもそも、職業安定法とは、、「各人に職業に就く機会を与えることによって産業に必要な労働力を供給し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律」です。
つまり、①労働者を募集し、②職業を紹介すること(=労働力の供給)について定めた法律です。
そして、職業安定法では、有害職業の紹介が禁止されています。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
まず、ソープランドが「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかですが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業に当たります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
したがって、上記のケースにおいて、Aさんが営むような違法なソープランドは有害業務に当たるものと考えられます。
~早期釈放に向けた弁護活動~
刑事事件においては、弁護士が適切かつ早期に対応することが出来れば、事件の早期解決や早期の身柄解放の可能性を高めることが可能です。
上記のケースのAさんのように、逮捕直後の場合であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を取ることが出来ます。
身柄解放活動を行うに当たって、弁護士は接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張していきます。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
このように、早い段階で弁護活動を始めることが出来れば、弁護士としては弁護活動の幅が増えますし、結果として早期身柄解放の可能性を高めることに繋がります。
そのため、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、刑事事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、またはその御家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用 38,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
身代わり出頭で犯人隠避罪に問われたら
身代わり出頭で犯人隠避罪に問われたら
~ケース~
東海市在住のAさんは、不良グループに所属している。
ある日,不良グループの先輩であるBさんが、傷害事件を起こした。
Bさんは執行猶予中の身であり,今回の傷害事件が発覚すると刑務所に行かなければならなかった。
そのため,AさんはBさんから代わりに警察署に出頭してくれないかと頼まれた。
AさんはBさんの頼みを断り切れず、愛知県警察愛知警察署に出頭した。
その後,捜査が進んでいく内にAさんは犯人ではないことが発覚した。
それを踏まえてAさんの取調べを続けたところ,AさんがBさんに頼まれて出頭したことを自供した。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
Aさんには、犯人隠避罪が成立すると考えられます。
犯人隠避罪は、刑法103条において「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。
Bさんの犯した傷害罪は、法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので刑法103条の言う罰金以上の刑に当たります。
判例によると、蔵匿とは,官憲の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供することをいい,隠避とは,蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含むとされています(大判昭和5年9月18日刑集9巻668頁)。
犯人の身代わりとして自首する行為も隠避に当たりますので出頭であっても隠避に当たると言えるでしょう(最決昭和35年7月18日刑集14巻9号1189頁)。
隠避の対象が罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であるかどうかについて,法定刑の認識は不要で,軽微でない罪を犯した者であるとの認識があれば足りるとされています(最決昭和29年9月30日刑集8巻9号1575頁)。
罰金刑以上の罪とならない軽微な罪,すなわち拘留または科料となる罪として侮辱罪,軽犯罪法違反が考えられます。
しかしながら,これらの罪で逮捕されることはごく稀ですので「逮捕されそうだから」という状況では基本的に罰金以上の刑にあたる罪であると考えられるでしょう。
~Bさんの罪~
Bさんは傷害事件を起こしていますので傷害罪が成立することは間違いないでしょう。
また,BはAさんに依頼して犯人隠避罪を実行させているのですからBが犯人隠避罪の共犯(教唆)とならないかが問題となります。
犯人自身は発見・逮捕を免れるために自身を蔵匿・隠避することは当然であるため,証拠隠滅罪(刑法104条)も含めて不可罰とされています。
一方,判例は犯人が他人に依頼するなどして自身を蔵匿・隠避させた場合には防御の濫用として教唆罪の成立を認めています(最決昭和40年2月26日刑集19巻1号59頁など)。
これに対して学説では,自己による蔵匿・隠避が不可罰であるならば,共犯の場合も同様に不可罰とすべきという見解が主張されています。
したがって,Bさんには傷害罪と犯人隠避罪の教唆罪が成立することになるでしょう。
~Aさんに対する弁護活動~
犯人隠避罪の法定刑は上述のとおり3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
実刑や執行猶予付きの判決となるか罰金になるかは隠避した犯人が犯した事件の重大性や隠避の態様などによって判断されることになるでしょう。
今回のケースでは隠避したBさんの犯した罪は傷害罪であり軽微な犯罪とはいえませんが重大な犯罪とまでは言えないでしょう。
今回のようなケースでは執行猶予付きの判決もしくは罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただし,自動的に確実に実刑判決とならないというわけではありませんので,弁護士はAさんが犯人隠避に協力してしまった事情などを主張して情状弁護をしていきます。
~Bさんに対する弁護活動~
今回のケースでは、Bさんは執行猶予中ですが,一般的な執行猶予中でない場合の弁護活動を考えていきます。
傷害罪の場合,傷害の程度や暴行行為の態様にもよりますが,初犯であれば執行猶予付きの判決や罰金となる場合が多くなっています。
しかし,犯人隠避を依頼したような場合には犯行後の情状が悪いことや犯人隠匿罪の教唆犯との併合罪となりますので,初犯であっても実刑判決となってしまう可能性もあります。
弁護士は実刑判決とならないために,社会内での更生可能性や隠避を依頼するに至った事情などの情状弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
依頼されて犯人隠避をしてしまった方や犯人隠避を依頼してしまった場合などはまずは0120-631-881までご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強盗致傷罪で裁判員裁判対応なら
強盗致傷罪で裁判員裁判対応なら
~ケース~
大府市在住のAさんは、借金苦から強盗することを思い立った。
アルバイト先である大府市内のコンビニに赴き、店員Vさんの腕を包丁で腕を切りつけて脅し、レジから売上金を強奪した。
その後、Vさんの通報により駆け付けた警察官に見つかり、Aさんは逮捕された。
そして、Aさんは強盗致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署に留置され、後日勾留されることが決まった。
裁判員裁判になるかも知れないと考えたAさんは、面会に来た両親に刑事事件に強い弁護士を付けてほしいとお願いをした。
Aさんの母親は、Aさんの処分が少しでも軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗致傷罪~
上記のケースにおいて、Aさんは強盗致傷罪の被疑者として扱われています。
強盗致傷罪については、刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
強盗致傷罪で起訴された場合には、たとえ前科のない初犯であったとしても、犯行態様や被害者の被害の程度次第では実刑判決となる可能性が高いです。
その為、強盗致傷罪で起訴された場合、被告人が犯行の原因に向き合い、また被害者との間で被害弁償に基づく示談を成立させることなどにより、酌量減刑を求めて執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
~裁判員裁判~
そして、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民(有権者)が、裁判官らと一緒に判決へ参加する裁判のことを言います。
そして、裁判員裁判においては、裁判官も裁判員も書面ではなく法廷で実際に見聞きしたことに基づいて、事件についての心証を形成することになります。
そのため、裁判員裁判においては、法廷内での弁護活動が決定的に重要となり、裁判員に主張を理解してもらうには、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要となります。
というのも、裁判員は当然法律や刑事手続等についてのプロではありませんので、弁護士としては、そのことを念頭に置いた上で、なぜその事情が被告人にとって有利に考慮されるべきなのかという点について、より踏み込んで、より丁寧に論じる必要があります。
また、通常の刑事裁判とは異なる手続きの多い制度になりますので、手続きの面でも専門性を問われることとなります。
このような刑事弁護活動は、裁判員裁判の経験がある弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,強盗致傷罪といった裁判員裁判が予想される事案についての相談もお任せ下さい。
強盗致傷罪で裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方,またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
犬山市の富くじ発売罪なら
犬山市の富くじ発売罪なら
~ケース~
犬山市在住のAさんは、動画サイトで活動するいわゆる動画配信者である。
ある日,Aさんは自身の配信上で「視聴者参加型プレゼント企画」と称して1口500ポイントの抽選型プレゼント企画を実施した。
Aさんの配信する動画サイトでは、視聴者がポイントを購入し配信者に送ることで、一定の割合で配信者が現金を得られる仕組みになっていた。
Aさんは参加者それぞれに番号を割り振り,配信上で番号の抽選をし当選者に賞品を発送した。
後日,当該動画を見た愛知県警察犬山警察署の警察官がAさんの行為が富くじ発売罪に当たるのではないかと思い,Aさんから事情を聞くことにした。
(フィクションです)
~富くじ発売罪~
富くじ発売罪については、刑法187条1項において「富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
富くじとは,あらかじめ番号札を発売して購買者から金銭その他の財物を集め,その後抽選などの偶発的な方法によって,当選者のみが利益を得るという形で,購買者間に不平等な利益を分配する仕組みによるくじ札をいいます。
「くじ札」は有体物である必要はなく,電磁的記録,すなわちメールなどで送信される番号等も含まれると解されるべきでしょう。
富くじの特色として,①抽選の方法により勝敗を決すること,②財物等の所有権をその提供と同時に失う事,③購買者のみが財産的危険を負担し,発売者は財産的危険を負担しないことにあります(大判大正3・7・28)。
販売者も財産的危険を負担する場合には賭博罪となる可能性があります。
なお,当選しなかった者が拠出した金銭などの財物を失わない場合には,富くじ発売罪は成立しません。
余談になりますが、上で説明した富くじの定義は宝くじにそのまま当てはまります。
宝くじは富くじに該当しますが、当せん金付証票法という法律によって販売が許可されています。
宝くじは富くじですので外国の宝くじを購入することは富くじ授受罪(刑法187条3項)に該当すると考えられていますが,現在のところ裁判例はまだありません。
また、商店街などの福引の場合,「福引を直接購入できる」場合には富くじ発売罪になると考えられますが,福引はあくまでの何らかの商品購入などのおまけになりますので富くじ発売罪には当たらないとされています。
~詐欺罪~
また,くじに対する商品の抽選を公正に行った場合には富くじ発売罪となりますが,不公正な抽選であった場合などは詐欺罪に問われる可能性もあります。
詐欺罪は人を欺いて財物を交付させた場合に成立し,法定刑は10年以下の懲役となっています(刑法246条)。
詳しい構成要件については省略しますが,購入者は公正な抽選が行われていると信じて購入しますので,不公正な抽選であった場合,人を欺いて財物を交付させたといえるでしょう。
不公正な抽選とは,たとえば,意図的に特定の購入者に当選させる場合や,身内や架空の番号などに当選させ実際には利益を分配しないような場合が考えられます。
~検挙されてしまったら~
動画配信などで富くじ発売罪に問われるような場合,詐欺的なものである場合などの悪質なケースでなければいきなり逮捕されるという事はあまりないでしょう。
しかし,警察からの事情聴取等の出頭要請を無視し続けたような場合には逮捕されてしまう可能性もあります。
今回のようなケースの場合,富くじとしての販売金額がそれほど大きくなければ不起訴となる可能性もあります。
ただし,一度不起訴となったからといって,再度同じような行為をした場合には起訴されて有罪となり罰金刑などが科せられる可能性が非常に高くなります。
また,詐欺的なくじの販売で,富くじ発売罪ではなく詐欺罪として捜査された場合には起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
もっとも,購入者に購入代金を返還するなどの被害弁償をしていた場合には犯行後の情状を踏まえて不起訴となる可能性もあります。
当然ですが,この場合にも再度同じような行為をすれば起訴されて有罪となる可能性が非常に高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
日常生活で思わぬ罪に問われてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を受け付けています。
(愛知県警察犬山警察署の初回接見費用 38,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
飲酒運転の否認事件なら
飲酒運転の否認事件なら
~ケース~
知多市在住のAさんは、仕事帰りに居酒屋Xで飲んでいた。
Aさんは車で居酒屋Xまで行き,車通りの少ない路上に駐車していた。
Aさんは居酒屋Xで飲酒したのち,帰宅しようとしたが飲酒運転をするのはまずいと思い、エンジンをかけずに車内で寝ていた。
数時間後、Aさんはパトロール中をしていた愛知県警察知多警察署の警察官に起こされ、職務質問をされた。
その際,車内にお酒のにおいが充満していたため、Aさんは呼気検査を受けることになった。
呼気検査の結果0.18ml/LであったためAさんは飲酒運転の疑いで愛知県警察知多警察署に連行された。
(フィクションです)
~飲酒運転~
いわゆる飲酒運転は酒酔い運転と酒気帯び運転に分類されています。
酒気帯び運転となるかどうかは血中アルコール濃度が基準値(0.15ml/L)以上かどうかという形式的な基準で判断されます。
酒酔い運転はアルコール濃度の検知に関係なく,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。
具体的には,まっすぐ歩けるかどうか,呂律(ろれつ)がしっかりしているかなどから判断されます。
酒酔いかどうかは実質的に判断されますので、体質によっては酒気帯び運転に満たない程度の血中アルコール濃度であっても酒酔い運転となる場合もあります。
罰則は、酒酔い運転の場合,5年以下の懲役または100万円以下の罰金,酒気帯び運転の場合,3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
飲酒運転には刑事罰の他,免許の取消しなどの行政処分も課せられます。
酒気帯び運転(0.15ml/L以上0.25ml/L未満)の場合,13点となり前歴がなくても90日の免許停止になります。
他の交通違反などにより累計で15点以上となる場合には1年間の免許取消となります。
酒酔い運転の場合は35点となり3年間の免許取消となります。
~Aさんの場合~
今回のケースで、Aさんは呼気検査の結果0.18ml/Lでしたが、飲酒運転となってしまうのでしょうか。
ある行為を犯罪として処罰する場合,犯罪とされる行為の内容は明確に規定されていなければならないとされています(罪刑法定主義)。
飲酒運転の場合,道路交通法第65条によって「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
車両と運転は第2条に定義されていますが,世間一般で言う車両や運転とほとんど同じ意味になっています。
さて,Aさんの車が車両に該当するのは明らかですが,Aさんは元から駐車してあった車に乗り込み寝ていたのだけですので運転には該当しないでしょう。
したがって,Aさんの行為は飲酒運転とはなりません。
~弁護士として~
今回のようなケースでは、Aさんに飲酒運転は成立しません。
しかしながら,警察はそのような事情を把握しておらず,飲酒運転をしてきてその場で寝ていたと嫌疑をかけられる場合が少なくありません。。
取調べに際しても,そういった考えから,そのような調書にするための取調べをする可能性もあるかもしれません。
刑事事件において、起訴するか否かの判断は検察官がおこない、仮に起訴した場合、Aさんが運転していたことを立証する責任は検察官側にあります。
そのため,弁護士としてはAさんが運転していないこと,すなわち車がずっとそこにあったことを店員や通行人の目撃証言などから立証していきます。
そして,起訴される前の段階で上記のような主張を意見書として提出し、検察官に起訴しないよう訴えかけていくことも可能です。
今回のようなケースでは、適切な弁護活動によって不起訴となる可能性が極めて高いでしょう。
しかしながら,誤った取調べ対応をしてしまった場合などは飲酒運転に問われてしまう可能性もあります。
身に覚えのない事柄で逮捕されてしまったり警察署に連行されてしまった場合や,犯罪事実を否認したいような場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
飲酒運転で身に覚えのない容疑を掛けられてしまった場合や罪を否認したい場合は、0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察知多警察署の初回接見費用 37,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
麻薬取締法違反で控訴審なら
麻薬取締法違反で控訴審なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは,麻薬を使用していた疑いで愛知県警察豊田警察署に逮捕され、勾留期間満期で起訴されることとなった。
そして第一審においてAさんは、国選弁護人に弁護活動を行ってもらっていたが、10年以上も前のことであるが覚せい剤使用の前科があったことを重視されてしまい、実刑判決となった。
実刑判決となった第一審判決を不服に思ったAさんは、控訴審で執行猶予を獲得できないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~控訴審までの流れ~
Aさんは、麻薬及び向精神薬取締法(いわゆる麻薬取締法)違反の罪で逮捕・起訴され、第一審の裁判所では執行猶予の付かない実刑判決を受けています。
そこで、Aさんとしては控訴審で執行猶予を獲得することを目指しています。
今回は第一審判決後の控訴審までの流れ、そして控訴審においてどのような弁護活動が出来るのかについて考えてみたいと思います。
まず、実刑判決が出たとしても、その判決が確定するまでは、刑の執行がなされることはありません。
控訴が可能な期間中に、控訴したとすれば、控訴審の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されます。
そのため、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。
~控訴審における弁護活動~
控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
まず、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
実際、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。
弁護士としては、第一審において事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
しかし、実際控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高くないのが実情です。
ただし、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談し、いかに的確な主張をしてもらえるかが大切になります。
そのため、控訴審での刑事弁護については、控訴審の経験が多く、刑事事件の弁護活動のプロフェッショナルである弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,麻薬取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
控訴審で少しでも良い結果を出したいとお考えの方,またはそのご家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
DVで暴力行為処罰法違反に問われたら
DVで暴力行為処罰法違反に問われたら
~ケース~
西尾市在住のAさんは,妻Vさんと夫婦喧嘩をした際、怒りが抑えきれずに台所から包丁を持ち出して、Vさんの腕めがけてに切り付けた。
Vさんは辛うじてAさんの暴行から避難し、愛知県警察西尾警察署に駆け込んだ。
Aさんから事情を聞いた愛知県警察西尾警察署の警察官いよって、Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕された。
冷静さを取り戻したAさんは,面会に来た両親にVさんに謝罪をしたいと思っている旨伝えたが、VさんはAさんからの電話にも出てくれない状態で、帰省しているようだと伝えられた。
そこで,Aさんの両親は、Vさんに対する示談交渉をお願いするため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為処罰法~
暴力行為等の処罰に関する法律(いわゆる暴力行為処罰法)とは,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為についてを,刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為処罰法は,もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが,現在では,学校等の教育機関におけるいじめの事案や,上記のケースのような配偶者間での暴力行為についても適用されることがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは包丁でVさんに切りかかっているため、暴力行為処罰法第1条の2の「銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す」に問われることになります。
また、Vさんは傷害を負っていませんが、同条にあたる行為をした場合、未遂についても処罰されます。
~DVにおける示談交渉~
暴力行為処罰法違反の事実について争いがない場合、示談することが出来れば、早期の身柄解放や処分の軽減の可能性を高めることが可能です。
ただし、上記のような家庭内暴力事件(いわゆるDV)は、被害者が身内を言うこともあり、通常の示談交渉とは違う配慮が必要とされることが多いです。
例えば、謝罪金の支払いだけではなく,今後の夫婦関係をどうするかという問題があります。
また、妻からは,離婚に同意しなければ示談には応じられない,との返答がなされるケースも多いです。
もしそうなった場合、慰謝料や財産分与等の離婚の条件は後回しとしても,妻が自宅で夫と二人きりになることを避けたいという意向を示したり,場合によっては二度と顔を合わせたくないという意向を示したり擦することもあります。
また、妻と接触する場合は,第三者立ち会いの下に行うという条件が必要となる可能性もあります。
特にDV事件の場合、加害者と被害者が近親者であるがゆえに、こういった環境調整がしっかりとなされなければ再犯のおそれを拭うことが出来ず、示談交渉が前に進まないことも多く、場合によっては示談交渉が決レルしてしまうことも考えられます。
しかし、被害者側との示談を成立させ、被害者感情が薄れていること、再犯可能性が減退していることを的確に捜査機関や裁判所に主張することが出来れば、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり,早期に身柄が解放され職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
このように,DV事件ではより一層被疑者や被害者の希望に沿った形での弁護活動が求められますので,DV事件での示談経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件の弁護経験が豊富ですので,DV事件に関するご相談も安心して行って頂けます。
DV事件で示談をしたいとお考えの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 41,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪で保釈を目指すなら
傷害罪で保釈を目指すなら
~ケース~
江南市在住のAさんは、会社の飲み会の帰りに江南市内の路上を歩いていたところ、すれ違いざまVさんと肩がぶつかり、口論となった。
腹を立てたAさんは、先にVさんに殴りかかり、その後も一方的にVを殴り続け、愛知県警察江南警察署の警察官が駆け付けるまでAさんの暴行は続いた。
駆け付けた愛知県警察江南警察署の警察官にAさんは現行犯逮捕され、泥酔状態であったものの同署で取調べを受けることになった。
翌朝、目を覚ましたAさんは、自分がVさんに対して行ったことを覚えていなかったため、取調べにおいてひたすら黙秘をした。
そして、Vさんから全治2週間の診断書が愛知県警察江南警察署に提出され、その後Aさんは傷害罪の容疑で起訴された。
(事実を基にしたフィクションです)
~保釈とは~
日本の刑事制度では、起訴後においては保釈という形の身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
また、裁量保釈については刑事訴訟法第90条において、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定されて今う。
つまり、第89条に挙げられた要件に該当するため必要的保釈が認められない場合であたとしても、罪証隠滅の恐れが無く、保釈の必要性が高い事を説得的に裁判所へ主張することが出来れば、裁量保釈が認められる場合があります。
~保釈保証金について~
また、保釈保証金についても、できるだけ安くしてもらうよう裁判所と交渉を行うこともあります。
仮に裁判所が保釈を認めた場合でも、保釈保証金が準備できないことも想定されますが、このようなときは、一般社団法人日本保釈支援協会による保釈保証金の立替制度の活用が考えられます。
~身柄拘束が続くデメリット~
上記のケースのAさんのような暴行・傷害事件での被告人勾留は、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くことになります。
そして、起訴後の被告人勾留による被告人の身体拘束は原則2か月で、1ヵ月ずつの更新が認められているからです。
その期間は身柄拘束されているわけですから、被告人が解雇や退学処分をうけてしまうおそれは極めて高いといえます。
また、身柄拘束による被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きいものです。
したがって、起訴されてしまった場合には、なるべく早い段階で保釈に強い刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼し、保釈に向けて行動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,暴行・傷害事件における保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪の容疑で起訴されてお困りの方、保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県県警察江南警察署の初回接見費用 38.200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
春日井市で賭博開帳図利罪なら
春日井市で賭博開帳図利罪なら
~ケース~
Aさんは春日井市内でマージャン屋(雀荘)を経営している。
Aさんの経営する雀荘で行われている麻雀は、いわゆる賭け麻雀であり,レートは店が指定していた。
店が指定するレートには3種類あり,卓についた3人ないし4人の合意によってレートが決まっていた。
また,客同士の金銭トラブル防止を目的に,ゲーム前に一定金額をチップに交換するシステムとなっていた。
ある日,Aさんの経営する雀荘に愛知県警察春日井警察署によるガサが入り,Aさんは賭博開帳図利罪の疑いで逮捕された。
そこで、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
※風適法など他の法令違反はないものとします
~賭け麻雀~
雀荘や仲間内で麻雀をする場合,ほとんどの場合がお金を賭けて楽しまれることが多いでしょう。
テンピン(1000点で100円)やテンゴ(1000点で50円),管轄署のレート以下ならば賭博罪とならないといった俗説がありますが大きな誤解です。
実際に,テンピンやテンゴであっても摘発された事例もあります。
ただ,些細な賭け麻雀を摘発することは無用の反発を招くとされており,実際に(雀荘でしていた場合でも)仲間内の賭け麻雀が摘発されることはあまりありません。
実際に摘発されるお店は,風適法の無許可営業であったり,高レート営業であったり,反社会的勢力が関係している場合が多いようです。
賭博罪には単純賭博罪と常習賭博罪および賭博開帳図利罪があります。
単純賭博罪は50万円以下の罰金または科料ですが常習賭博罪の場合は3年以下の懲役となります(刑法185条および186条)。
また,賭博を主宰し利益を図ったものは賭博開帳図利罪(186条2項)が成立します。
法定刑は3ケ月以上5年以下の懲役となっています。
~賭博の主宰~
賭博開帳図利罪は「賭博の主宰」および「図利の目的」が要件となっています。
「賭博の主宰」とは賭博を管理支配していたということが必要になります。
雀荘の場合,4人(もしくは3人)が卓を借りるいわゆるセット打ちの場合には店側がレート等を指定する余地は基本的にありません。
しかし,個々の客が集まり賭け麻雀をするいわゆるフリー打ちの場合,基本的に店が指定するレートで賭け麻雀をすることになりますが,この事実を持って店が賭博を管理支配していたとまではいえないでしょう。
また,「図利の目的」とは「賭博をする者から,寺銭,または手数料等の名義をもって,賭場開設の対価として,不法な財産的利得をしようとする意思」をいいます(最判昭24・6・18)。
実際に雀荘の経営者が賭博開帳図利罪に問われた事件で,裁判所は
①レートを店側が決めていた
②レートごとにゲーム代が異なっていた
③レート及びルールを店が客に説明していた
④店が預り金を徴収していた
⑤店がトップになった者からトップ賞を徴収していた
という事情から店による管理支配および図利の目的を認め,賭博開帳図利罪の成立を認めました。
このうち,①③④は賭博の主宰,②⑤は図利の目的にあたるといえるでしょう。
特に,⑤に関しては,トップ賞すなわち勝者から金銭を徴収しているのですから「寺銭」に該当します。
寺銭とはカジノにおけるコミッションと同様に,賭博開帳者が対価として勝者から受取るものをいいます。
②に関しても,レートの異なる場を用意した手数料として対価を得ているとされたと思われます。
~Aさんの場合~
Aさんの場合,レートを店が指定していたことやゲーム前に一定金額をチップに交換させていたことから上記の①③④を満たしているといえるでしょう。
なお,店の用意したチップなどのやり取りであっても即座に換金可能であることから,当然に賭博罪となります(上記の通り摘発されないことが多いです)。
Aさんの場合,店が一定金額をチップに交換させていたとはいえ,レートは客が選択可能でありトップからトップ賞の徴収などの寺銭なども受け取っていませんでした。
そのため,賭博の多少の管理支配はあったとはいえ,その管理支配は客同士のトラブルを防止し,それによって客の入りをよくする(=ゲーム代での利益をあげる)目的であったといえますので賭博開帳図利罪とはならない可能性が高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
雀荘のみならず,風俗営業を営む方で逮捕されてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見や事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察春日井警察署の初回接見費用 38,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。