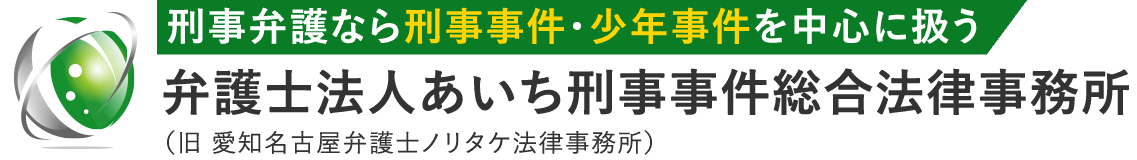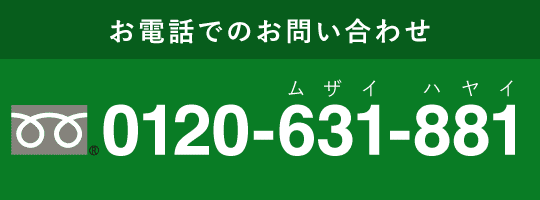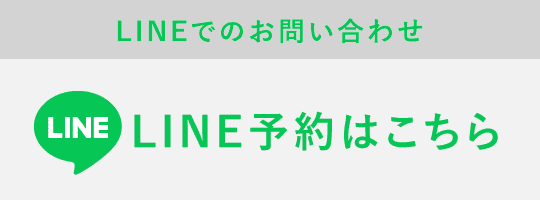Archive for the ‘未分類’ Category
検察官の不起訴とは
検察官の不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ ご相談内容 ~
私は、昨年の9月に痴漢をした件で不起訴処分(起訴猶予)を受けました。しかし、今年のの7月にまた痴漢をしました。現在はその件で検察庁から呼び出しを受けています。7月の件では起訴されても仕方ないと思っているのですが、9月の件でも起訴されてしまうのでしょうか??(フィクションです)
~ 不起訴って何? ~
不起訴とは、検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。以下、具体的にみていきましょう。
不起訴は、検察官が下す終局処分の一種ですから、不起訴を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく、
検察官
です。検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴にするか判断できる立場にあるのです。刑事訴訟法には不起訴について次の規定が設けられています。
上記のとおり、起訴するか、不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから、その判断の時期も
検察官の判断(裁量)
に委ねられます。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。
検察官は検察官が収集した証拠に基づき不起訴にするかどうか判断します。そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況
から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予す。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
不起訴になれば、
刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと
がなくなります。したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また、不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~ 今後、逮捕、起訴されることはないの? ~
裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。したがって、不起訴となったからといって、
逮捕、起訴されないという保証はありません
証拠が足りなくて不起訴となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、再度、逮捕、起訴されることがあります。前者のケースは少ないと思われますが、後者のケースは十分にあり得ることです。したがって、起訴猶予で不起訴となった場合は、それだけで安心せず、その後の生活態度には十分気を付ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯
児童ポルノ単純所持と発覚の経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、自分で鑑賞するため、観賞用に、自宅に、児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ、Aさんは、愛知県中川警察署の家宅捜索を受け、児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日、Aさんは、愛知県中川警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは、今後のことが不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」7条に規定されています。
法律7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
= 児童ポルノとは =
「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。
法律2条3項
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク、BL・DVD・CD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー、ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり、児童ポルノとは、1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。
= 成立要件 =
児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには、
・児童ポルノを所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること
という要件に加え、児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。
* 自己の性的好奇心を満たす目的 *
自己の性的好奇心を満たす目的とは、平たくいえば、「児童の裸などを見たい、触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは、あなたの供述に加えて、児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機、経緯、その量、所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから、あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても、「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。
~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~
ところで、児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯で発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに、どうして発覚してしまうのか疑問、不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで、ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。
= 余罪捜査から発覚 =
一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば、児童買春、児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち、スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。
= 業者の摘発から発覚 =
児童ポルノの供給者側である業者が摘発され、業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され、個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。
= 児童の補導などから発覚 =
児童が警察に補導された場合は、援助交際などに関わっていないかどうか確認するため、児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に、児童が裸などの写真画像、動画を送っていた場合は、そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。
ここに挙げたのはほんの一例であって、発覚の経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは、ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で、対策を立てることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
強盗事件と不起訴
万引きから事後強盗罪へと発展し不起訴を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,家事育児に追われていることでストレスがたまり,お金に困っているわけでもないのに万引きをするようになりました。
ある日,Aさんが愛知県名古屋市内のスーパーマーケットで菓子数点を万引きしたところ,店を出ようとしたところで警備員に呼び止められました。
動揺したAさんは,警備員に向かって咄嗟にハンドバッグを振り回し,警備員の頭にハンドバッグが当たって怯んでいる隙にその場から逃走しました。
警備員に怪我はありませんでした。
後日,Aさん宅を愛知警察署の警察官が訪ね,Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの夫は,弁護士に不起訴を目指せないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【万引き事件が強盗罪に?】
上記事例のAさんは,事後強盗罪という罪の疑いをかけられています。
強盗罪は聞いたことがあっても事後強盗罪は聞いたことがないという方は多いかと思います。
まず,強盗罪は,暴行または脅迫を手段として財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
暴行・脅迫により被害者の抵抗を困難にして財産を自分の物にする点で,いわば窃盗罪がより悪質になったものとして位置づけられます。
これに対し,事後強盗罪は,窃盗に及んだあとで一定の目的のもと暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
一定の目的とは,①盗んだ物が取り返されるのを阻止するため,②逮捕されるのを防ぐため,③証拠を隠滅するため,のいずれかです。
窃盗犯がこうした目的で暴行・脅迫を行うことがよく見られ,なおかつその危険性が強盗罪における暴行・脅迫と同視できることから,事後強盗罪という類型が設けられました。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされているため,法定刑や他の罪との関係は強盗罪と同じということになります。
つまり,刑は5年以上の有期懲役であり,強盗致死傷罪など強盗罪の加重類型も成立しうることになります。
ちなみに,強盗罪と事後強盗罪における暴行・脅迫は,「相手方の反抗を抑圧するに至る程度」,つまりある程度強いものでなければならないと考えられています。
仮に暴行・脅迫が弱めのものだったとすると,強盗罪ではなく恐喝罪になったり,事後強盗罪ではなく窃盗罪と暴行罪または脅迫罪になったりする余地が出てきます。
【不起訴を目指すには】
仮に逮捕されるような事件を起こしたとしても,事件の内容と弁護活動によっては不起訴になる可能性があります。
不起訴は検察官が裁判を行わないという判断を下したことを意味するので,有罪となって刑罰が下されることは基本的になくなります。
そのため,刑事事件においては理想的な終わり方の一つだと言うことができます。
先述のとおり,検察官が不起訴処分を下すかどうかは,事件の内容と弁護活動により大きく左右されます。
事件の内容については,端的に言って事件の悪質性が低ければ不起訴になりやすくなると考えられます。
今回のケースで言うと,被害総額が高くないと見込まれる,少なくとも暴行は突発的なものである,といった事情が悪質性の低さを根拠づける要素となることが期待できます。
弁護活動については,やはり非常に重要なものとして示談が挙げられます。
今回のケースであれば,万引きの被害者である店と暴行の被害者である警備員が被害者に当たると考えられます。
弁護士を通して被害者にきちんと謝罪と被害弁償を行い,許しを得ることができれば,不起訴となる可能性はぐっと高まるでしょう。
逮捕された,あるいは強盗罪だからといって,絶対に不起訴にならないかと言うとそういうわけではありません。
不起訴を目指されるのであれば,まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,知識と経験を頼りに的確な不起訴の見込みをお伝えします。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご予約方法はこちら)
暴行罪か傷害罪か
暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市北区に住むAさんは、職場の同僚の勤務態度に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。その際、Vさんの鼻などから出血は確認できず、Vさんも病院には行かなかったようです。
ところが、それから1週間後、Aさんは愛知県北警察署の警察官に呼び出され、取調べで「Vさんから医師の診断書が出た」「診断名は歯牙破折だ」ということを聞かされ、傷害罪の被疑者として捜査すると言われました。
Aさんとすれば、暴行自体は認めているものの、事件当時、Vさんから歯が折れたなどとは聞かされていなかったため、怪我の点については納得できずにいます。
そこで、Aさんは、今後どう対応すればいいのか刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
Aさんが
・Vさんの胸ぐらをつかんだり
・Vさんの顔面を右拳で殴る
行為は、暴行罪の「暴行」に当たります。
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどの行為がその典型でしょう。もっとも、最近、マスコミで報じられている
あおり運転
もこの「暴行」に当たるとして、あおり運転をしたを暴行罪で処罰した例もあります。
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
見た感じ、暴行罪よりも、どのような要件がそろった場合に傷害罪が成立するのか分かりにくいですが、刑法208条と併せてみてみると、
「暴行」を加えた者が「傷害」するに至ったとき
に傷害罪が成立するものと解されます。
なお、「傷害」とは、
単に相手方に怪我をさること
のみならず、それよりももっと広く、
人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更すること
と解されています。
~ 暴行罪と傷害罪との違い ~
以上から、暴行罪と傷害罪との違いは、
「傷害」の結果が発生したか否か
によります。そして、その「発生したか否か」には、
もとから傷害が発生しなかった
という場合と、
傷害は発生したが、暴行との因果関係が認められない
という場合の2つのパターンがあることに注意が必要です。
~ 本件の刑事弁護 ~
本件で、Aさんは、「暴行」の事実自体は認めているものの、「暴行」と「傷害」との因果関係について疑問を持たれているようですから、まずは「暴行罪」での処分を主張していかなければなりません。
具体的には、Aさんはもちろん、周囲に直接の目撃者あるいはVさんの様子を知る人がいなかったかどうか調べ、その方たちからもお話を聴く必要があるでしょう。
そして、その聴取した結果を意見書という形にまとめ、処分を決める検察官に提出するといったことが考えられます。
それと同時に、「暴行」の事実に限っての示談交渉を進めていく必要があります。
仮に、傷害罪で起訴され裁判になった場合は、裁判で診察をした医師を尋問するなどして作成した診断書の証明力を減退させる必要も出てくる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
淫行条例違反で不起訴を目指すなら
淫行条例違反で不起訴を目指すなら
淫行条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~ケース~
愛知県一宮市の会社員のAさんはSNSを通じて仲良くなった高校2年生であるVさんとホテルで性交をした。
その日,Vさんは帰りが遅くなり,両親から理由を問いつめられた。
VさんがAさんとの関係を両親に話すと,Vさんの両親は激怒し,愛知県一宮警察署に被害届を提出した。
翌日,Aさんが会社に出勤しようとしたところAさん宅に来ていた愛知県一宮警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の疑いAさんは逮捕されてしまった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)
~愛知県青少年保護育成条例~
愛知県青少年保護育成条例は条例名の通り,愛知県の青少年の保護・健全な育成を目的として制定された条例です。
愛知県のみならず各都道府県が同じような条例を制定しています。
青少年とは18歳未満の者をいい(第4条),青少年に対する有害玩具や入れ墨,淫行・わいせつな行為などを禁止しています。
特に,青少年に対する淫行・わいせつな行為で摘発されることが多くなっており,「淫行条例」と呼ばれることも多いです。
第14条
何人も,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して,前項の行為を教え,又は見せてはならない。
第29条
第14条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
淫行条例違反の場合によく問題となるのが「いん行またはわいせつ行為」が具体的にどのような行為を指すのかが不明確な点です。
似たような事例の児童ポルノや児童買春の場合には,どのようなものが児童ポルノであり,どのような行為が児童買春であるかが条文に明記されています。
一方,「いん行」については上記条例に明記されているわけではなく,最高裁判所が昭和60年に以下のような判決を下しています。
「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解する。」
性交するに至った経緯,関係性などから「淫行」に当たるかどうか判断されることになると考えられます。
~不起訴を目指すには~
淫行条例違反で不起訴を目指すには,そもそも淫行には当たらない(無罪)という主張をする他,示談を成立させることが考えられます。
淫行には当たらないと考えられる場合,検察官は事件を不起訴処分にすると考えられます。
また,逮捕後に勾留されてしまうと起訴するかどうかの判断が勾留満期である10日ないし延長満期の20日間となってしまいますので示談交渉などの時間を確保するためにも勾留されないように弁護活動をします。
また,淫行条例違反の場合,被害者との示談を成立させ,加害者を許すという宥恕条項を頂ければ不起訴となる可能性が非常に高くなります。
ただし,淫行条例違反の場合,示談交渉の相手方が未成年である青年ではなく,保護者が相手となります。
そのため,直接の被害者となる青年が許しているという場合でも,保護者の怒りが強く示談交渉が難しい場合もあります。
淫行条例違反事件を含む刑事事件の弁護経験あ豊富な弁護士であればそのような場合でも示談交渉に応じて頂き,示談を成立させられる場合もございます。
淫行条例違反をしてしまい,不起訴処分を勝ち取りたいとお考えの場合にはまず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで淫行条例違反事件を受任し,示談を成立させ不起訴処分となっだ事例も数多く手掛けて参りました。
淫行条例違反を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
準強制性交等罪の弁護活動
準強制性交等罪の弁護活動
準強制性交等罪と弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
愛知県名古屋市昭和区在住のAさんはかねてから好意を抱いていたVさんと食事に行くことになった。
AさんとVさんはバーでお酒を飲んだ後解散することになったが,Vさんはかなり酔っており一人で自宅まで帰るのが難しいようであった。
そこでAさんは,Vさんを介抱するという名目でホテルに連れ込んだ。
AさんはVさんが酔っていることに乗じてVさんと性交をした。
後日,AさんはVさんからホテルでの性交は同意がなかったとして,昭和警察署への刑事告訴を考えていると告げられた。
どうすればよいかわからなくなったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
~強制性交等罪~
一般に,同意のない性交は強制性交(強姦)であると認識されている場合もあります。
しかし,刑法では強制性交等は以下のように定められています。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文上,強制性交となるのは暴行または脅迫を用いて性交をする必要があります。
同意のない性交がただちに強制性交となるわけではありませんが,同意のない性交の場合,性交は暴行または脅迫が用いられていることが多いでしょう。
今回のケースでは確かに同意はなかったといえますが,Vさんはかなり酔っており,Aさんは暴行または脅迫を用いてはいないといえそうです。
このような場合には罪刑法定主義の観点から刑法177条は適用できませんが,刑法は別の規定を設けています。
刑法第178条(準強制性交等罪)
1.略
2.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
心神喪失とは精神的な障害によって正常な判断力を失った状態,抗拒不能とは心理的もしくは物理的に抵抗できない状態をいいます。
したがって,抵抗することが不可能もしくは極めて困難な状態にある人と性交をした場合に刑法第178条2項の適用が考えられます。
実際の事件では,相手に酒を飲ませて酔い潰させた事案などが多くなっています。
~Aさんの場合の弁護活動~
では今回のAさんには準強制性交等罪は成立するのでしょうか。
Aさんに準強制性交等罪が成立するかどうかは,Vさんが抗拒不能であったといえるかが問題となるでしょう。
抗拒不能であったかどうかは,酩酊状態であった(=酔っていた)かどうかではなく,実際に抵抗することが不可能もしくは著しく困難であったかによって判断されます。
今回,Vさんは一人で帰るのが難しいくらいに酔っていたのですから抗拒不能であったと認められる可能性は高いでしょう。
もっとも,客観的にろれつが回っていない,足元がふらついているといった客観的な事情が重要となります。
もし,Aさんが事実を争うつもりであれば,居酒屋などに聞込みをし,Vさんは抗拒不能であったとはいえないという主張をすることになるでしょう。
一方で,Aさんに事実を争うつもりがない場合に,Vさんとの示談を視野にいれて弁護活動をすることになります。
強制性交等罪は法定刑として5年以上の有期懲役のみしか定められていませんので,起訴された場合には必ず刑事裁判が開かれます。
今回のようなケースでは酌量軽減により執行猶予付きの判決が付く可能性もあります。
執行猶予といえども,前科となってしまいますので,可能な限り不起訴となるように弁護活動をしていきます。
また,強制性交等罪(旧:強姦罪)は2017年の刑法改正で非親告罪となり,被害者の刑事告訴がなくとも処罰可能となりました。
被害者が刑事告訴できない事情があるといった場合を念頭に入れたものと考えられますので,今回のケースのような男女間のトラブルといった事案にまで警察などが積極的に介入してくるとは考えにくいでしょう。
今回のケースでは,Vさんの被害申告・刑事告訴がなければ,警察等は捜査の端緒を得られないので刑事事件化する可能性は低いといえるでしょう。
そのため,Vさんと示談をし,被害届提出や刑事告訴をしないという約束をしてもらうことで刑事事件化することを防ぐことが出来ます。
ただし,強制性交事件では,加害者が被害者の方と直接示談交渉をするのが難しい場合が殆どです。
そのような場合でも,弁護士であれば安心して示談交渉に応じていただけるという方も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等事件で被害者の方と示談をすることによって事件化を阻止したり,不起訴となった事例も数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
児童買春と逮捕の可能性
児童買春と逮捕の可能性
児童買春と逮捕の可能性について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,SNS上でいわゆる「パパ活」の相手を募集している女性と連絡を取っていました。
ある日,Aさんは愛知県岡崎市に住む自称大学生のVさんと会うことになり,Vさんに1万5000円を渡して一緒に食事をしました。
その際,Vさんから「3万払ってくれればエッチしてあげるよ」と言われたため,Aさんはそれに応じて市内のホテルで性行為を行いました。
その後,Vさんと何度か会ってはお金を払って性行為をしていたAさんでしたが,ある日岡崎警察署の警察官から呼び出しを受けました。
曰く,Vさんは実は18歳未満で,Aさんの行為が児童買春になるというのです。
Aさんは逮捕が不安になり,弁護士に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律では,刑罰の対象となる「児童買春」の定義や,児童買春をした場合の罰則などが定められています。
まず,処罰の対象となる「児童買春」とは、簡単に言うとお金などを対価として18歳未満の者と性的な行為に及ぶことを指します。
細かな点はいくつかありますが,基本的に18歳未満の者とお金を払って性的な行為に及べば児童買春に当たる可能性が高いと言えます。
今回のケースでは,Aさんが18歳未満であるVさんに3万円を交付し,それを対価として性行為に及んでいます。
このような行為は,上記法律が禁止している「児童買春」に当たる可能性が高いと考えられます。
ただ,今回の場合,AさんはVさんが18歳未満だということを知らなかったようです。
こうした場合には,犯罪の故意,すなわち児童買春に当たる行為をしているという認識がなかったと判断される余地があります。
児童買春については故意がなければ処罰されないので,もし「18歳未満だと知らなかった」という主張が認められた場合,児童買春として処罰を受けるのは回避できます。
だからといって,知らなかったという主張が易々と受け入れられるわけではないため,その点に関しては注意が必要です。
【逮捕の可能性】
児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっており,他の罪と比較すると決して軽いとは言えません。
事件の性質を見ても,たとえば暴行事件などとは違って被害者(児童)が自ら被害を申告することはあまりなく,犯行が繰り返されやすいと評価できます。
児童買春をしたことで逮捕されるかどうかにつき,一概に「される」または「されない」と言い切るのは難しいのが実情です。
そもそも逮捕とは,被疑者による逃亡や証拠隠滅を防ぐことを主な目的として,捜査機関の判断で行われるものです。
そのため,最終的には捜査機関次第という面が拭えず,逮捕の見込みにつき確実なことが言えないというわけです。
とはいえ,逃亡や証拠隠滅の防止という主な目的がある以上,それを手掛かりにして個々の事案ごとにある程度の見込みを立てることはできます。
たとえば,犯した罪が重大であればあるほど,厳しい刑罰から逃れようとして心理的に逃亡や証拠隠滅に及びやすくなるという傾向は考えられます。
また別の例として,特定の住居を持たず国内外を転々としている方は,生活の基盤が安定していない分逃亡に及びやすいと考えることもできます。
このように様々な事情に基づいて逃亡や証拠隠滅のリスクが検討されるため,そうした事情から逮捕の可能性が分かるというわけです。
ご自身のケースで逮捕の可能性をお知りになりたいのであれば,ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の可能性について的確な見通しをお伝えします。
児童買春を疑われたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
傷害事件で正当防衛
傷害事件と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、愛知県名古屋市中村区において傷害事件を起こしたとして、中村警察署の捜査を受けていました。
Aさんが傷害事件を起こした背景には、以下のような事情がありました。
ある夜、Aさんが区内を歩いていたところ、前から酒に酔った様子のVさんが歩いてきました。
AさんがVさんとすれ違った際、VさんはAさんに「てめえ今睨んだだろ」などと因縁をつけ、突然Aさんの胸倉を掴んできました。
Aさんはそれを振りほどいて逃走を図りましたが、Vさんが道端に落ちていた傘を持って追いかけてきたことから、身の危険を感じて持っていた鞄を振り回しました。
そうしたところ、たまたま鞄の角がVさんの顔に当たり、Vさんに全治2週間程度の怪我を負わせたというのが事の経緯です。
このことを聞いた弁護士は、正当防衛の主張ができないか検討することにしました。
(フィクションです)
【傷害罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、その名のとおり人に対して「傷害」を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害という結果を指すと考えられています。
このことから、たとえば出血や骨折といった怪我を負わせる行為以外でも、傷害罪が成立する余地があります。
たとえば、人体に有害な化学物質を食べ物に混ぜ、それを食べた者に腹痛を生じさせる場合などが考えられます。
傷害罪の成立を認めるためには、飽くまでも傷害を負わせた行為が故意に行われたものである必要があります。
仮に傷害が過失(簡単に言えば不注意)に基づくものであれば、過失傷害罪として軽く罰せられるに過ぎません。
上記事例において、身の危険を守るためとはいえ、Aさんが故意に鞄を振り回していることは否定できません。
そうすると、Aさんの行為が過失傷害罪に過ぎないという主張は難しいと言えるでしょう。
【正当防衛となる余地はないか】
たとえ行為そのものが傷害罪に当たるとしても、正当防衛の成立により適法な行為として扱われる余地はあります。
正当防衛の成立を肯定するには、①急迫不正の侵害、②自己または他人の権利を防衛する目的、③行為がやむを得なかったこと、を満たす必要があります。
簡単に言うと、①他人による違法な行為が突然降りかかったときに、②自己または他人の身体や財産などを守るため、③必要最低限の行為をした際に正当防衛が成立する可能性があります。
正当防衛は、言ってしまえば本来違法な行為を特別な条件の下で正当化するものです。
そのため、正当防衛が成立するかどうかの判断は、裁判官による厳しいものとなることが予想されます。
弁護士に事件を依頼するメリットとして、正当防衛のような専門的な事柄について的確な主張を展開できる点が挙げられます。
どのような主張をすべきかあらかじめ弁護士に聞いておけば、取調べや裁判において不用意な供述をしてしまうリスクを抑えることができるでしょう。
取調べも裁判も、一度した供述を撤回して別の供述を記録してもらうというのは簡単なことではありません。
ですので、もし正当防衛の主張をお考えであれば、やはり早い段階から弁護士に依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、正当防衛の主張が認められるよう尽力します。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
暴行罪で略式起訴
暴行罪で略式起訴
暴行罪と略式起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
自営業をしているAさんは,愛知県豊田市内のコンビニで買い物をした際,店員であるVさんが商品を乱雑に扱ったことに腹を立てました。
そこで,Vさんに対して暴言を吐いたうえで,胸倉を掴んで殴ろうとしました。
ただ,その様子を目撃した買い物客がAさんを羽交い絞めにしたため,Vさんは殴られることはありませんでした。
そこへ通報により豊田警察署の警察官が駆けつけ,Aさんは暴行罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【暴行罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
他人に対して「暴行」を加えたものの,その他人が「傷害」を負わなかった場合,暴行罪が成立する可能性があります。
「傷害」に至れば傷害罪が成立することになるので,暴行罪はそれよりも軽い罪だと言えます。
暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使一切を指すと考えられています。
この定義に従うと,「暴行」が一般的に意味する行為よりも多くの行為が暴行罪に当たる可能性があります。
今回のケースにおいて,AさんはVさんの胸倉を掴んだものの,殴ろうとしたところで他の買い物客にそれを阻止されています。
このようなケースでも,胸倉を掴んだ行為が「暴行」と評価され,Aさんに暴行罪が成立する可能性はあります。
【略式起訴による罰金刑の可能性】
刑事事件において最終的にどの程度の刑が科されるかについては,犯罪に当たる行為の具体的な内容のみならず,犯行に至った動機,本人のこれまでの経歴(前科など),犯罪後の
対応など様々な事情が考慮されます。
そのため,「何罪を犯したから刑はこれくらい」と一概には言えません。
ただ,ある程度量刑の傾向は存在しており,暴行罪の初犯であれば数十万円の罰金刑となるのが一般的だと言えます。
暴行罪に限りませんが,100万円以下の罰金刑を科すのが相当な事案の場合,被疑者の同意のもと略式起訴という手続を経て刑罰が科されることがあります。
略式起訴とは,検察官が事件を起訴して裁判にかけようとする際,本来の裁判よりも簡略化した裁判を行うよう求めるものです。
通常の起訴を経た裁判の場合,おなじみの法廷にて傍聴人などもいる中で裁判が行われます。
一方,略式起訴を経た裁判というのは,裁判官がいわば書面上で事件に関する判断を行うことになります。
そのため,法廷という公の場に出ることなく裁判を受けられる点において,通常の裁判に伴うような肉体的・精神的負担を感じないというメリットがあります。
ただし,略式起訴を経た裁判のデメリットとして,通常の裁判ほど手厚い保障が受けられないという実情があるのは見過ごせません。
事件を簡易かつ迅速に処理するために手続が簡素になっていることによる弊害です。
こうした事情から,略式起訴に当たっては被疑者の同意が要求されると共に,裁判官にも略式起訴が相当かどうか判断することが可能となっています。
更に,仮に略式起訴を経た裁判を終え,略式命令(判決のようなもの)を受けても,2週間以内であれば通常の裁判を要求することが可能となっています。
以上のとおり,略式起訴にはメリットとデメリットの両方が存在します。
そのため,略式起訴に同意すべきかどうか弁護士に相談されてもよいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が,略式起訴に関するご相談にも真摯にお答えいたします。。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
強盗事件で逮捕
強盗罪と逮捕の可能性について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,悪質なセールスに騙されて数十万円の時計を購入させられ,その代金の支払いの目途が立たず困っていました。
そうした話を友人のBさんにしたところ,「それなら俺と一緒にコンビニ強盗でもやろう。2人なら上手くやれる」と誘いを受けました。
悩みに悩んだ結果,Aさんはその誘いに乗り,Bさんと共に愛知県稲沢市内のコンビニで強盗をすることにしました。
そして,事前に立てた計画に沿って犯行を遂げ,およそ20万円を奪取しました。
しかし,犯行の翌日になって,Aさんは急に逮捕される自分を想像して恐怖を抱きました。
そこで,すぐに弁護士に相談し,逮捕の可能性について聞いてみました。
(フィクションです)
【強盗罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は,暴行または脅迫を手段として,他人から財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
単に相手方の意思に反して財産を盗むのではなく,それを暴行・脅迫によって実現する点で,窃盗罪より悪質性が高いと評価されています。
そのため,窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し,強盗罪は5年以上の有期懲役(上限20年)という厳しい刑が定められています。
強盗罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧するに至る程度のものでなければならないと考えられています。
具体的には,凶器の有無,発言の内容,暴行の程度などの様々な事情を考慮し,客観的に判断されます。
特に凶器を用いている場合については,実務上犯行を抑圧するに至る程度のものがあったと評価されやすい傾向にあります。
もし暴行・脅迫がこの程度に至っていなければ,強盗罪ではなく恐喝罪(10年以下の懲役)に当たる可能性が出てきます。
【逮捕の可能性】
犯罪をしてしまった場合,多くの方はまず「逮捕されるのではないか」という点を懸念されるのではないかと思います。
逮捕というのは,捜査機関が裁判所に令状を請求し,その令状の発布を受けたうえで行われるのが原則です。
そのため,逮捕されるかどうかは,理論的には①捜査機関による令状の請求,②裁判所による逮捕状の発布(逮捕の許可),③捜査機関による逮捕状の執行という手続を踏んではじめて行われるものです。
とはいえ,実務上②の段階で裁判所が逮捕状の請求を却下するのは稀であり,なおかつ③の段階で捜査機関が敢えて逮捕の執行をしないというのも考え難いので,基本的には①に掛かっていると言えます。
逮捕するかどうかが捜査機関の判断に掛かっている以上,弁護士などの法律家であっても確実に逮捕するかどうかは分かりません。
ただ,逮捕の目的というのは主に逃亡と証拠隠滅の防止なので,そうした視点からある程度予測を立てることは可能です。
まず,問題となる犯罪が重い場合,逮捕の可能性は高くなるのが一般的です。
犯罪が重いと,刑罰を免れるために逃亡や証拠隠滅を図る疑いがあると考えられるからです。
この観点からすれば,強盗罪を疑われたケースは逮捕の可能性が高いと予想できます。
また,犯行が複雑な場合についても,逮捕の可能性は高くなることがありえます。
こうした場合の例として,コンピュータに関する犯罪や,共犯者がいる犯罪などが挙げられます。
これらのケースでは,データの消去または共犯者間での口裏合わせによる証拠隠滅を捜査機関が懸念するからだと考えられます。
以上はあくまでも考慮要素と考えられるものの一部であり,実務上は個々の事案に応じて可能性が変わってきます。
逮捕の可能性について少しでも正確な予測を立てるなら,やはり自身の事案を弁護士に相談するのが一番かと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の可能性を含む事件の見立てを丁寧に説明いたします。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)