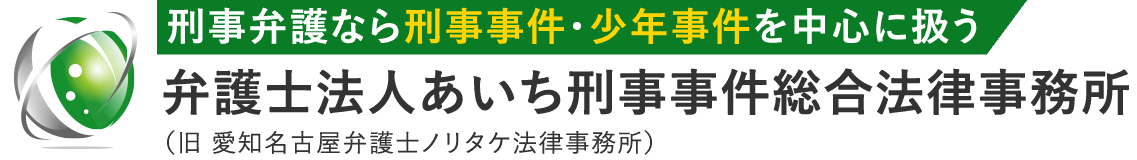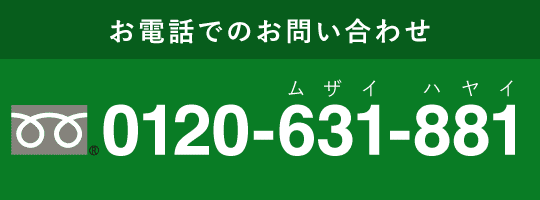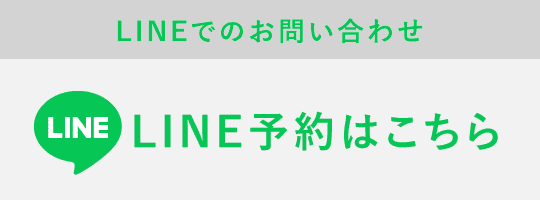Author Archive
覚醒剤の使用の再犯 執行猶予はつく?
覚醒剤の使用の再犯 執行猶予はつく?
覚醒剤の使用の再犯で執行猶予はつくのかということについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
事例
Aさんは名古屋市中村区に在住の男性会社員(35歳)です。
Aさんは4年前に覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕・起訴され,懲役6月執行猶予3年の有罪判決を受けたことがありました。
その後,社会復帰をしたAさんでしたが,会社でのストレスなどに押しつぶされてしまい,再び覚醒剤を手に入れて自宅で使用し始めてしまいました。
すると,覚醒剤の使用を再開して2か月後自宅に東海北陸厚生局麻薬取締部の捜査が入りました。
捜査の結果,未使用の覚醒剤が出てきたことと尿検査で陽性反応がでたためAさんは覚醒剤所持と覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
その後,Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されました。
Aさんの妻は,Aさんが実刑判決となり,長期間身柄を拘束されてしまうと生活が困難になるため,Aさんに執行猶予が付くか刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
覚醒剤に関しての法律
覚醒剤の所持及び使用について,覚醒剤取締法の以下の条文に定められています。
覚醒剤取締法第14条第1項 (所持の禁止)
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
覚醒剤取締法第41の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法第19条 (使用の禁止)
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5 法令に基づいてする行為につき使用する場合
覚醒剤取締法第41条の3 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
通常の覚醒剤関連での検挙の大多数は覚醒剤の所持と使用であると思われます。
これらについて法律は特別に許されている医療目的や研究目的以外の所持や使用を禁止しています。
そして,法律に違反して覚醒剤を所持,使用すると最悪の場合は10年の懲役に処されることもある重い犯罪であると言えます。
執行猶予について
刑の全てについて執行猶予にできる場合について,刑法の以下の条文に定められています。
刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる。
1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
刑法第25条第2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮以上の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときも,前項と同様にする。
まず,刑法第25条第1項の執行猶予が認められるためには,
1 5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
2 判決の言い渡しが3年以下の懲役若しくは,50万円以下の罰金であること
3 情状があること
の3点が必要になります。
このうち,3の情状とは,犯罪中若しくはその後の状態をみて,刑の執行を猶予することで自主的に更生することが期待できる状況を言います。
本件では,以前の執行猶予から5年経過していないため,第1項の執行猶予には当たりません。
そのため,第2項の執行猶予に当たるかが問題になります。
覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反事件の場合,実際の所持していた覚醒剤の量などによって裁判官が量刑を決めますが,再犯の場合,基本的に量刑は重くなる傾向にあります。
そのため,Aさんの場合には,1年を超える懲役に処せられる可能性が高いと言え,第2項の執行猶予を得ることも簡単にはできないと考えられます。
さらに,たとえ刑期が1年以下に抑えられたとしても,執行猶予を付けるには「情状に特に酌量すべきものがある」ことが必要です。
ですから,Aさんのようなケースでは,執行猶予を獲得することは非常に難しく厳しい道であることが分かります。
しかし,このような事件では絶対に執行猶予を得ることが出来ないというわけではありません。
今回は裁判中から治療を受けて,その経過を裁判で主張するなど「情状に特に酌量すべきものがある」ことを裁判官に納得させる手はないわけではないため,あきらめることなく,弁護士などの専門家と一緒に努力することが必要です。
もしも実刑判決となってしまっても,再犯防止策の構築などをしていくことは,その後の更生にも役立ちますから,まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが,24時間体制で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
業務上横領罪と時効
業務上横領罪と時効
業務上横領罪と時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説いたします。
~事例~
Aさんは、名古屋市北区にあるV社に勤務し、2020年12月末をもって定年退職した元会社員です。
Aは2006年からVのある支店の支店長をしていました。
しかし、2010年にギャンブルで損失を出したAさんは、2010年10月から2014年10月の約3年間、支店長として管理していたお金の内500万円を着服しました。
以上の着服はAさんが支店長として勤務している間は判明することはありませんでしたが、Aさんの退職後の調査でAさんの着服が判明しました。
そのため、V社は愛知県北警察署に業務上横領罪の被害届を出しました。
業務上横領罪の被害届が出されたことを知ったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~横領罪・業務上横領罪とは何か~
横領罪と業務上横領罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法は横領罪と業務上横領罪について以下のように定めています。
刑法第252条 (横領)
第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法第253条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
横領罪は、自分が占有している他人の物を横領する行為について成立する犯罪です。
また、業務上横領罪とは、上記の横領行為を業務として占有しているものに対して行った場合に成立します。
ここで、横領行為とは、「不法領得の意思の発現行為」を指すとされています。
そして、ここにいう不法領得の意思とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思」をいいます。
この横領行為の具体的な例としては、費消、着服、持ち逃げなどの行為がこれに当たります。
本件についてみると、Aさんは自身が支店長として管理しているお金を着服しています。
まず、Aさんが着服したお金は、会社という他人のものであるお金を、支店長という業務上の地位で占有していたものですから、業務上横領罪の対象になります。
そして、Aさんはこの会社のお金を着服しており、不法領得の発現行為を行なっていると言えます。
そのため、Aさんには業務上横領罪が成立することになります。
~時効は成立するか~
しかし、Aさんの横領行為は最近のものでもおよそ6年から7年前ですが時効は成立していないのでしょうか。
一般的に言われる時効とは、公訴時効のことを指します。
そして、その公訴時効は、刑事訴訟法において以下のように定められています。
刑事訴訟法第250条
第1項 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
1 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
2 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
3 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
第2項 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年
この公訴時効は、事件が起きた日から検察官が起訴するまでの時間を制限する規定です。
この事件が起きた日とは、事件の行為ごとに考えられるものです。
つまり、業務上横領行為を別日に分けて複数回行っていたというような場合には、1回目に業務上横領行為をしたときと2回目に業務上横領行為をしたときの公訴時効はずれてくることになります。
本件についてみてみましょう。
本件においてAさんが行った業務上横領罪は、人を死亡させてはいない罪で、かつ、長期10年の懲役が定められている犯罪です。
そのため、本件では250条2項4号に該当し、本件の時効は7年になります。
ですから、Aさんの最初の横領行為は7年以上経過しています。
他方で少なくとも最後の横領行為は、7年は経過しておりませんので公訴時効が成立しないことになります。
つまり、Aさんは少なくとも最後に行った業務上横領行為では起訴される可能性があることになります。
こうした時効の計算などは、専門的な知識も必要になりますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスお問い合わせを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県常滑市に住むAさんは、メキシコに海外旅行に行った際に、旅行先で知り合ったBさんから、荷物(スーツケース)を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼されました。
Aさんは、Bさんから預かった荷物(スーツケース)の中身は「覚醒剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない」と思いましたが、Bさんからの依頼を了承し、荷物を日本に持ち運びました。
その結果、中部国際空港の税関検査において覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件が発覚し、Aさんは覚醒剤取締法(覚醒剤輸入)の罪の容疑で逮捕されました。
(2020年11月13日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪とは】
覚醒剤取締法13条(輸入及び輸出の禁止)
何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
覚醒剤取締法は覚醒剤の輸入を絶対的に禁止しています。
覚醒剤取締法41条(刑罰)
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
覚醒剤をみだりに輸入した者については、1年以上の有期懲役が科せられることになります。
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪における「輸入」とは、国外から我が国内へ物品を搬入することをいいます。
そして、覚醒剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚醒剤を取りおろした場合、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪における「輸入」行為があったといえると考えられています。
【覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪の故意とは】
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪が成立するためには、輸入する物品が「覚醒剤」であることを認識・認容している必要があります。
具体的には、輸入する物品が覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識があれば、輸入する物品が「覚醒剤」であることの認識・認容があったといえると考えられています(最高裁裁判所決定平成2年2月9日)。
刑事事件例では、Aさんは、Bさんから預かった荷物(スーツケース)の中身は「覚醒剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない」と考えています。
このとき、Aさんは輸入する物品が、覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物かもしれないと考えているわけですから、Aさんには、輸入する物品が「覚醒剤」であることの認識・認容があるといえると考えられます。
以上より、Aさんには覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪が成立すると考えられるのです。
【関税法違反の罪(禁制品輸入罪)とは】
関税法69条の11第1項1号では覚醒剤は「輸入してはならない」と定められています。
そして、覚醒剤を所持して通関線を突破した場合、関税法69条の11第1項1号の「輸入」行為があったといえると考えられています。
関税法109条第1項では、関税法違反の罪(禁制品輸入罪)の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
よって、覚醒剤を密輸した場合、覚醒剤取締法違反(輸入)の罪とは別に、関税法違反の罪(禁制品輸入罪)の未遂罪が成立すると考えられています。
【覚醒剤取締法違反(輸入)事件の刑事弁護活動】
覚醒剤取締法違反(輸入)事件で逮捕された場合、Aさんは逮捕とそれに引き続く勾留がなされる可能性が高いといえます。
これは、共犯者との口裏合わせなど罪証隠滅の可能性が高いと考えられるからです。
また、その後は、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で起訴される可能性が高いといえます。
これは、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)事件の発覚した際に、輸入した覚醒剤が押収されている可能性が高く、覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪の立証が比較的容易であるからです。
そこで、刑事弁護士としては、Aさんが覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で起訴された場合は、情状証人の証拠調請求を行うなど、執行猶予判決の獲得や減刑を求めるための刑事弁護活動を行っていくことになると考えられます。
刑事事件を取り扱う弁護士に相談し、可能な弁護活動や見通しなどを詳しく聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反(覚醒剤輸入)の罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童虐待の傷害事件を起こしてしまったら
児童虐待の傷害事件を起こしてしまったら
児童虐待の傷害事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県刈谷市の自宅において、10歳の娘(Vさん)が口答えをしたことに腹を立て、Vさんの髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせました。
翌日、Vさんが通う小学校の担任教師がVさんの顔にあざがあることに気付き、Vさんが「親から暴力を受けて帰りたくない」と話したことから110番通報しました。
愛知県刈谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待をしたことによる傷害罪の容疑で逮捕しました。
(2020年10月27日にテレビ朝日NEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【児童虐待防止法とは】
児童虐待防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、児童虐待の定義について以下のように規定しています。
児童虐待防止法第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
そして、児童虐待防止法では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」(児童虐待防止法3条)と規定しています。
確かに、刑事事件例におけるAさんによるVさんの髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせる行為は、児童虐待防止法における「児童虐待」に該当すると考えられます。
しかし、児童虐待防止法で罰則が設けられている行為は、接近禁止命令(児童虐待防止法12条の4)に違反した場合(児童虐待防止法17条)のみです。
すなわち、刑事事件例のような傷害事件において、Aさんが児童虐待防止法違反により直接的に罰せられることはありません。
それでは、Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
【傷害罪の成立】
刑法第204条は、傷害罪を規定しています。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪が成立するためには、創傷や擦過傷、打撲傷、めまい、嘔吐、失神など、身体の生理機能の障害が生じている必要があります。
刑事事件例において、AさんはVさんに対し、髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせています。
このVさんの怪我は身体の生理機能の障害であるとして、傷害罪が成立する「傷害」に該当すると考えられます。
よって、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
児童虐待といっても、虐待の態様によって成立する犯罪は様々です。
どういった犯罪がどうして成立するのかをきちんと把握しておくことは、刑事手続に臨むうえで非常に重要なことです。
まずは専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童虐待の傷害事件を起こしてしまってお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
名古屋市天白区に住むAさんは,名古屋市天白区内の路上で帰宅途中の女性(Vさん,30歳)に背後から抱き付き,わいせつな行為をしました。
その後,Aさんは,愛知県天白警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんと面識はありませんでした。
Aさんは公務員であるため,何とか事が大きくならないようにしてほしいと考えています。
(2021年4月1日にテレ朝newsに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためは,「暴行又は脅迫」を手段とする必要があります。
具体的に強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫をいいます。
また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。
なお,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の成立には,手段の如何は問われません。
また,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪は,わいせつ行為の同意があった場合であっても成立します。
以上の各要件を満たす場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立します。
【強制わいせつ罪と公務員】
今回の事例のAさんは,公務員であることから,事が大きくならないようにできないかと考えているようです。
公務員については,国家公務員であれば国家公務員法に,地方公務員であれば地方公務員法にそれぞれ決まりがあります。
国家公務員法38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
国家公務員法38条や地方公務員法16条では,国家公務員や地方公務員の絶対的欠格事由が規定されています。
欠格事由とは,簡単に言えばその資格がないとされることを指し,例えば公務員の欠格事由というと,公務員という立場に立つ資格がないとされる事情を指すことになります。
そして,絶対的欠格事由とは,その事柄に当てはまってしまったら,その資格を剥奪されるなどする欠格事由ということになります。
公務員の場合,絶対的欠格事由に当たるということは,すなわち失職するということになります。
ここで,強制わいせつ罪で起訴されて有罪となってしまった場合,被告人の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
この強制わいせつ罪で科せられる懲役刑は,国家公務員法38条や地方公務員法16条の「禁錮以上の刑」に当たります。
そして,たとえ執行猶予付き判決を得ることができたとしても,国家公務員法38条や地方公務員法16条の欠格事由に当たることになります。
ですから,強制わいせつ罪で有罪となるということは,公務員の絶対的欠格事由に当たるということになり,失職することになるのです。
そのため,公務員が強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,強制わいせつ罪で起訴されることを避ける,すなわち不起訴処分を得ることを目指す必要があります。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合でも,不起訴処分を得ることができれば,前科はつかないことになります。
【強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには】
強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することが重要です。
示談締結のためには,検察官から刑事弁護士限りで強制わいせつ事件の被害者の方の連絡先を教えてもらい,被害者の方へ正式な謝罪と相当な被害の弁償を行うべく,示談交渉を開始することになります。
強制わいせつ事件で示談をする効果については,初めて強制わいせつ事件を起こした場合(初犯の場合),同様の強制わいせつ事件の前科がある場合に比べて,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性は高いといえます。
また,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することができた場合,逮捕から解放される時期が早まることがあります。
たとえ,強制わいせつ事件が不起訴処分で終わったとしても,逮捕・勾留による身体拘束期間が長引けば,そのことにより懲戒処分などを受ける可能性があります。
そのため,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結する,それも速やかに締結することが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化
愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化
愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県東郷町内において、飲料メーカーの社員を名乗り、自動販売機内を点検するという名目でV1さん・V2さん・V3さんが管理する自動販売機3台(三人がそれぞれ所有)を開けさせ、現金を盗む窃盗行為を繰り返し行いました。
窃盗行為によって得た金額は合計100万円に及びました。
愛知県愛知警察署の捜査により、窃盗事件の被疑者がAさんであることが判明し、Aさんは窃盗罪の容疑で任意の取調べを受けています。
Aさんは、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことをいいます(占有とは物に対する事実上の支配を指します)。
ここで、窃盗罪における「窃取」には「窃」という漢字が使われているため、「ひそかに」の意味を持つとも思われます。
しかし、必ずしも占有侵害行為がひそかに行われることを必要とせず、公然と占有侵害行為が行われても窃盗罪における「窃取」に該当することになると考えられています。
刑事事件例において、AさんはV1さんらに自動販売機を開けさせるという手口を使っており、窃盗罪の犯行態様としては必ずしも「ひそかに」行われているものとはいえませんが、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当することになります。
【窃盗罪と詐欺罪】
ところで、AさんはV1さんらに対して飲料メーカーの社員であると偽ってV1さんらに自動販売機を開けさせ、その結果現金を獲得しています。
このように一見するとV1さんらを欺く行為があり、Aさんには窃盗罪ではなく、詐欺罪が成立するのではないかとも思われます。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」場合、すなわち①欺く行為・②錯誤・③処分行為・④交付行為という一連の行為が連鎖した場合に成立します(刑法246条)。
そして、詐欺罪における処分行為には、主観的要件として財産を処分する意思が必要であり、客観的要件として財物の占有が終局的に移転したことが必要であるとされています。
刑事事件例を見てみると、確かにAさんはV1さんらに対して飲料メーカーの社員であり、自動販売機内を点検すると偽ってV1さんらに自動販売機を開けさせています。
しかし、V1さんらが現金を終局的にAさんに移転させたという詐欺罪における処分行為に該当するような事実はありません。
また、V1さんらにはAさんに対して現金を交付する意思はなかったと考えられます。
よって、今回の事例においては、Aさんには詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立すると考えられます。
刑事事件例における特徴は、窃盗事件の被害者がV1さん・V2さん・V3さんと複数いることです。
Aさんが窃盗罪で起訴されるのを回避したり、刑罰を軽減させたりするためには、窃盗事件の被害者と示談を締結することが非常に有効となりますが、窃盗罪の被害者が複数いる場合には、各被害者とそれぞれに示談を締結する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被害者が複数いる窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東郷町の窃盗事件で刑事事件化した場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験・予備試験受験生を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所の事務アルバイト求人募集を行っています。
令和3年度の司法試験・予備試験受験生にとって、新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって、勉強環境及びモチベーションを維持することは非常に大きな問題となっています。さらに司法試験・予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期となります。そんな時期には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、北海道は札幌から、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪(梅田、堺)、神戸、九州は福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
【勤務地】
札幌支部 さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部 仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部 千葉駅から徒歩2分
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
名古屋支部 名古屋駅から徒歩6分
京都支部 京都駅から徒歩5分
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
堺支部 堺東駅から徒歩5分
神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【名古屋本部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の本部にあたる場所で、多くの弁護士が常駐しています。
名古屋本部は、JR(東海道本線・中央本線・関西本線)、名古屋臨海高速鉄道、名古屋市営地下鉄が乗り入れている【名古屋駅】から徒歩9分の場所で、名古屋鉄道(名鉄)と近畿日本鉄道(近鉄)の乗り換えも可能です。
アクセスの良さゆえ、名古屋市内・愛知県内はもとより近隣の三重県や静岡県、岐阜県などからの御依頼も多く、多様且つ豊富な事件に携わることができる場所です。
法曹界で刑事事件に携わることを目標としている方は勿論のこと、刑事事件の実務について興味がある方、進路について検討中の方にとっても、貴重な経験になるでしょう。
御自分で勉強していて分からないことがあったり、実際の事件に携わる中で気になった点があれば、弁護士に質問することも可能です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
アルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール noritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊明市の路上で立ち小便していたのを近くにいた男性2人(V1さん、V2さん)に注意され、二人の顔を1回ずつ殴りました。
暴行を受けた二人の通報により、駆け付けた愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは酒に酔っており、「注意されて腹が立った」と話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊明市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪における暴行とは、他人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における暴行により傷害が発生した場合、行為者には傷害罪(刑法204条)が成立します。
したがって、暴行罪における暴行は、傷害を生じさせるものであることを要しません(大判昭和8年4月15日)。
例えば拡声器で大声を発する行為やお清めと称して塩を振りかける行為でさえも暴行罪における暴行に該当することになります。
刑事事件例において、Aさんは、V1さんとV2さんの顔面を1発ずつ殴っています。
これは暴行罪における暴行に該当する典型例です。
よって、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と勾留・示談交渉】
Aさんは愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんに本件暴行事件に関する罪証を隠滅するおそれや逃亡するおそれがあると考えられる場合、Aさんは最大20日間に及ぶ勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
このような長期間に及ぶ勾留がなされると、その間は学校や仕事に行けなくなってしまうため、退学や失業を余儀なくされるおそれがあります。
弁護士としては、暴行罪容疑での勾留を避けるための刑事弁護活動として、検察官や裁判官に対して、AさんがV1さんやV2さんと面識がないことを摘示して、本件暴行事件に関する罪証隠滅のおそれが客観的にないことを主張するなどしていくことになるでしょう。
加えて、もしV1さんやV2さんが既に愛知県警豊明警察署の警察官に対して暴行事件の被害を受けたことの供述をしている場合には、Aさんが二人に対して供述を変えるよう強いることがあっても、実際に二人が供述を変遷させることは考えにくいというような主張もできると考えられます。
暴行罪の容疑での勾留を阻止することができれば、在宅被疑事件として警察官や検察官の取調べを受けることになるでしょう。
そして身柄解放活動のあとには、弁護士と協力し、Aさんが暴行罪で起訴されないように、検察官に対して寛大な処分をするよう働きかけていくことも考えられます。
特に不起訴処分獲得を目指す場合には、暴行を受けた被害者との示談を締結することが有効であるといえますが、これらは専門家かつ第三者である弁護士のサポートが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、刑事事件例においては被害者が2名いることが特徴的ですが、このような複数の被害者との示談交渉を進めていくことも可能です。
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市名東区にある大型商業施設において、買い物客の30代女性(Vさん)のスカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を盗撮しました。
しかし、盗撮現場を保安員に目撃され、愛知県名東警察署に110番通報をされました。
その結果、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されました(Aさん所有の携帯電話内に盗撮動画がありました)。
愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月15日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは】
愛知県迷惑行為防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない」と規定されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「次に掲げる行為」としては、「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号)が規定されています。
また、「前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項3号)が規定されています。
すなわち、愛知県迷惑行為防止条例では盗撮行為が禁止されています。
なお、愛知県迷惑行為防止条例における卑わいな行為の禁止(盗撮行為の禁止)としての規制範囲は、「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)」にまで拡大されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
そして、愛知県迷惑行為防止条例第15条では、「第2条の2」「の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
刑事事件例における大型商業施設は、愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「公共の場所」に該当します。
また、Aさんが行ったVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮する行為は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号における「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」に該当します。
以上より、Aさんには愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立すると考えられます。
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪と余罪の取調べ】
刑事事件例では、Aさんの携帯電話からVさんを盗撮した動画が見つかっています。
愛知県名東警察署の警察官は、押収(逮捕の伴う捜索・差押え)したAさんの携帯電話からVさん以外の被害者が写った盗撮動画がないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)を捜査すると考えられます。
また、Aさん自身の取調べにおいても、Vさん以外の人を盗撮していないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)と厳しい追及がなされる可能性があります。
刑事弁護士としては、Aさんに対して余罪取調べ(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)の厳しい追及に対してどのように対応すればよいか、刑事事件の専門的な知識と豊富な経験をもとに助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県東海市内の遊園地でジェットコースターの整備責任者として勤務していました。
ところが、ジェットコースターが前の車両に衝突し、乗客であったVさんがケガをしてしまいました。
事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
Aさんは、愛知県警東海警察署の警察官により、業務上過失傷害罪の容疑で事情聴取(任意捜査)を受けています。
業務上傷害罪の容疑での事情聴取(任意捜査)を受けたAさんの両親は、愛知県東海市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【業務上過失傷害罪とは】
「業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者」には、業務上過失傷害罪が成立します(刑法211条1項)。
業務上過失傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
業務上過失傷害罪における「業務」とは、「本来人が①社会生活上の地位に基づき②反復継続して行う行為であって、かつその行為は③他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」とされています(最高裁判所判決33年4月18日)。
このような一定の危険な業務に従事する業務者には通常人よりもとくに重い注意義務が課されていると考えられます。
そのため、業務上過失傷害罪の法定刑は、通常の過失傷害罪(刑法209条1項)の法定刑である30万円以下の罰金又は科料よりも重く規定されています。
刑事事件例において、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、整備責任者としての社会生活上の地位に基づくものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件①)。
また、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、勤務として反復継続して行われています(業務上過失傷害罪の業務性の要件②)。
さらに、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、安全管理や整備を怠れば、乗客にケガをさせ、最悪の場合死に至らせてしまうおそれのあるものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件③)。
よって、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、業務上過失傷害罪における「業務」に該当すると考えられます。
また、刑事事件例では、事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
そのため、Aさんは業務上過失傷害罪における「業務上必要な注意を怠って」おり、そのために事故が起きて客がケガをしたといえると考えられます。
したがって、Aさんには業務上過失傷害罪が成立すると考えられます。
【業務上過失致傷罪と起訴】
業務上過失傷害罪の法定刑は、上述の通り、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このような刑罰は、業務上過失傷害罪で刑事裁判に起訴された場合に宣告され得るものです。
しかし、懲役刑や罰金刑が宣告され得る場合であっても、裁判所の量刑によっては執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
また、業務上過失傷害事件においても不起訴処分となった刑事事件例も多数存在します。
したがって、ひとくちに業務上過失傷害事件といっても、不起訴処分や執行猶予付き判決、罰金刑、懲役刑のように様々な終局処分の形があります。
そして、業務上過失傷害罪を犯した場合にどのような量刑が下されるのかは、その業務上過失傷害事件が起こった経緯や原因、被害の程度、示談の有無などが関係すると考えられます。
特に業務上過失傷害事件はその事件特有の事情があることもあるため、刑事弁護士が被疑者や関係者の方から事件の経緯や原因を詳しく伺うことから刑事弁護活動が始まることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上過失傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。