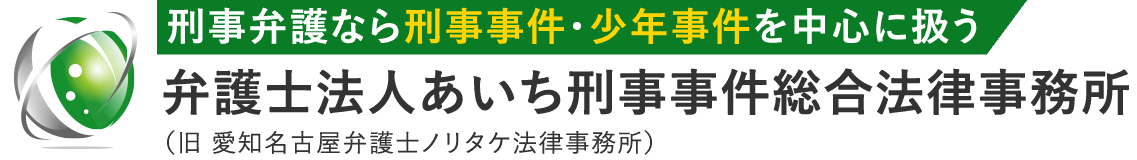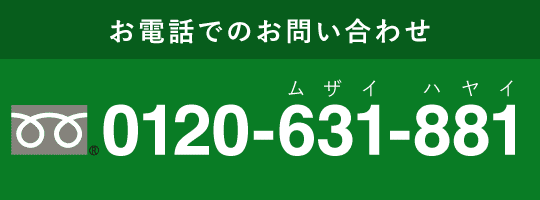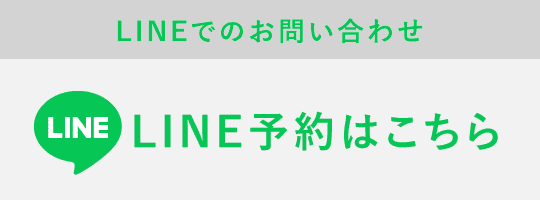Archive for the ‘未分類’ Category
公務執行妨害罪で現行犯逮捕
公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します,
【ケース】
愛知県一宮市に住むAさんは,会社の後輩と酒を飲み,すっかり酔った状態で自宅までの帰り道を歩いていました。
帰宅途中,Aさんは道路の真ん中で寝転び,その場で寝始めてしまいました。
その姿を警邏中の警察官が発見し,Aさん「大丈夫ですか。こんなところで寝てたら他の方に迷惑ですから」と声を掛けました。
それに対し,Aさんは「なんだてめえ。若造が」と言って警察官の胸倉を掴み,顔を近づけて怒号を浴びせました。
これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され,一宮警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんに事件の流れを伝えました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪について】
刑法(一部抜粋)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は,公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法では,暴行については暴行罪,脅迫については脅迫罪というかたちで,いずれの行為についても別途犯罪として規定されています。
ですが,公務というのは国や地方公共団体が行う公的な事務であり,特に保護に値すると言えます。
このような事情から,公務執行妨害罪という犯罪類型が定められ,公務が手厚く保護されるに至っているのです。
実務において見られる公務執行妨害事件は,逮捕を伴うものが少なくありません。
その理由の一つとしては,暴行・脅迫の対象となった公務員が警察官であり,犯行の現認によって現行犯逮捕に至っているからだと考えられます。
法定刑は率直なところ比較的軽いものですが,上記のような理由で逮捕がよく見られる点には注意が必要です。
【逮捕後の事件の流れ】
逮捕や勾留というのは,被疑者の身体の自由を奪う点で人権侵害の側面を持っています。
そのため,刑事事件の手続について定めた刑事訴訟法には,逮捕や勾留について厳格な時間制限を課しています。
これにより,身体拘束を伴う刑事事件では,基本的に以下の流れに沿って進むことになります。
まず,警察署は,被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察庁に送致しなければなりません。
警察署から身柄の送致を受けた検察庁は,被疑者の身体を引き続き拘束する勾留が必要か検討し,必要だと判断すれば身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求を行います。
以上の手続は逮捕から72時間以内に行わなければならず,事件制限を超えたり身体拘束の必要性が認められなかったりする場合,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
検察官の勾留請求があると,被疑者を勾留すべきかどうかの審査を裁判所が行うことになります。
こうした審査の結果,裁判官が勾留の必要性を認めると,被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間の勾留が決定します。
この被疑者に対する勾留の期間は,捜査の必要上やむを得ない場合については更に10日以内の範囲で延長される(つまり勾留が最長20日となる)ことがあります。
担当の検察官は,上記の勾留の期限までに被疑者を起訴するか不起訴にするか決めなければなりません。
もし起訴の判断が下された場合,勾留は被疑者向けのものから被告人向けのものへと変わり,勾留の期間は2か月延長されてしまいます。
更に,被告人に対する勾留については,必要に応じて1か月単位で更新が行われます。
以上のように,逮捕後の身体拘束は,事件によっては相当長期にわたってしまいます。
この間,弁護士は適切なタイミングで身柄解放活動を行い,被疑者・被告人の身柄解放を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の前後を問わず充実したサポートを行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件で観護措置を回避
少年事件で観護措置を回避
少年事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
愛知県一宮市に住む中学3年生のAくんは、他の2人の少年とともに、別の中学校に通う少年に対し、悪口を言ったことに対して腹を立て、暴行を加え怪我を負わせました。
Aくんは、当初、暴行を加えることには賛成していませんでしたが、その場の雰囲気に流され、2回ほど被害者を足で蹴ってしまいました。
Aくんは、中学卒業直後に愛知県一宮警察署に逮捕されました。
高校入学を控えるAくんは、高校生活にも影響が出るのではないかと心配でなりません。
Aくんの両親は、なんとか観護措置だけでも回避できないかと少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
少年事件では、捜査段階で逮捕・勾留され、長期間の身体拘束を強いられるだけでなく、家庭裁判所に送致された後に観護措置がとられ、審判までの数週間にわたり少年鑑別所に収容されることがあります。
観護措置とは
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護の2種類があります。
実務上、在宅観護はほとんど活用されておらず、観護措置という場合は収容観護を指すのが通常です。
観護措置の要件については、少年法は「審判を行うため必要があるとき」としか規定していません。
しかし、一般的には、以下の各要件を満たすことが必要であると理解されています。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
④の観護措置の必要性については、次の3つの事由うちいずれかに該当する場合に認められます。
(a)調査、審判及び決定の執行を円滑、確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
例えば、住居不定、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあり、身体を確保する必要がある場合などです。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
自殺や自傷のおそれがある場合、家族からの虐待のおそれがある場合、不良集団等の影響により非行性が急速に進行するおそれがある場合などです。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
観護措置の期間は、法律では2週間を超えることができないとされており、とくに継続の必要があるときに限り1回更新することができる、とされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がされていて、観護措置の期間は、通常4週間となっています。
家庭裁判所は、事件が係属している間、いつでも観護措置をとることができます。
捜査段階で逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に到着してから24時間以内に観護措置をとらなければならないため、送致されたときに観護措置をとることがほとんどです。
捜査段階で逮捕・勾留されていない少年であっても、家庭裁判所に送致された後に、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることもあります。
捜査段階で身体拘束を受けている場合、家庭裁判所に送致された後も、そのまま観護措置がとられることが多くなっています。
しかしながら、観護措置がとられることにより、更に1か月ほどの身体拘束を強いられることになり、その結果、少年に大きな負担を与えることになりかねません。
観護措置の必要性がないと考えられる場合や観護措置を回避する必要がある場合には、観護措置を回避するための活動を行うことが重要です。
付添人である弁護士は、家庭裁判所に事件が送致される時を見計らい、付添人選任届と共に、観護措置に関する意見書を提出します。
意見書では、観護措置の要件や必要性がないこと、観護措置を避けるべき事情があることについて、説得的に主張します。
被害者との示談が成立していること、少年が真摯に反省していること、保護者による監督が期待できること、そして、学校に出席しなければならない理由など、できるだけ具体的に観護措置の要件を満たしていないことや必要性がないこと、観護措置を回避したい事情について説明し、裁判所に対して観護措置をとらないよう積極的に働きかけます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
自殺強要で取調べ
自殺強要で取調べ
自殺強要で取調べを受けるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件】
Aさんは保険金を得る目的で愛知県豊田市においてVさんに交通事故を起こして死亡するよう脅迫しました。
VさんはAさんに指示されたように車を運転し事故を起こそうとしましたが寸前で逃走し豊田警察署に出頭しました。
Vさんの情報をもとにAさんは強要の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【自殺の強要】
強要罪と自殺関与罪・殺人罪の関係について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
AさんはVさんを自殺するよう脅迫しました。
この行為は強要罪(刑法第223条)に当たる可能性があります。
刑法第223条
第1項 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
第2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
現代の日本において自殺することは法的にはもちろん道徳的・倫理的にも義務とされることはありませんので,脅迫して自殺させることは強要罪に当たり得ます。
しかし,人の生命は他の法益よりも重要で要保護性が高いため,自殺を強要した場合には他の犯罪に問われる可能性があります。
その一つが殺人罪(刑法第199条)です。
刑法第199条
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
Aさんのケースと似た事案で,自動車事故を装った方法により被害者を自殺させて保険金を取得しようと企てた被告人が,暴行,脅迫を交え被害者に対し漁港の岸壁上から乗車した車ごと海中に飛び込むように執拗に命令し,被告人の命令するように海中に飛び込む以外の行為を選択できない精神状態に陥らせ実行させた事案があります。
この事件で最高裁は「被告人は,以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して,本件当日,漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ,被害者をして,自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから,被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は,殺人罪の実行行為に当たるというべきである」と判示しました(最決平成16・1・20刑集58巻1号1頁)。
したがって,Aさんの脅迫の程度やそれによってVさんがどのような精神状態に陥っていたのか,Vさんが死亡する現実的危険性の高い行為に及んでいたといえるかどうかによっては,判例による限り殺人未遂罪の適用も考えられます。
また,ここまではVさんが行為時に自殺する意思がなかったとする前提のお話でしたが,もし自殺する意思があったとしても自殺教唆として自殺関与罪(刑法第202条前段)に問われる可能性があります。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
Aさんが行った脅迫がどのようなものであったかにもよりますが,AさんがVさんを脅迫した時点で自殺を決意していないものの,Aさんの脅迫を通じて自殺を決意した場合は教唆行為と教唆による自殺意思の発生が認められます。
そのうえでVさんが自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及んだ場合,Aさんは自殺教唆未遂罪に問われる可能性があることになります。
以上から,暴行・脅迫によって相手方に自殺するよう命令した場合,強要罪や殺人罪,自殺関与罪およびこれらの未遂犯として処罰される可能性があります。
Aさんも事件の詳細によってこのご紹介したいずれの罪にも問われ得ることになります。
【弁護活動】
Aさんから依頼を受けた弁護士は,事件の具体的な状況を調査します。
調査の結果と捜査機関からかけられている被疑事実に合わせて取調べ等を受けるにあたっての適切な法的アドバイスをAさんに提供します。
Vさんに対して示談を申し入れることも活動内容となります。
事実の具体的内容や示談内容にもよりますが,示談を素早く成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
その他にもAさんの情状となりうる事実を主張するなど,弁護士の活動は多岐にわたります。
これらの弁護活動は初期から行わなければ十分な結果を期待することが難しくなります。
刑事事件では証拠等を捜査機関が独占している場合が多く,また時間の経過によってどんどん手続が進んでしまうからです。
強要罪や自殺教唆罪の被疑者となってしまった方,豊田警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
初回法律相談:無料
中学生による脅迫罪と示談
中学生による脅迫罪と示談
中学生による脅迫罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
愛知県名古屋市緑区に住む中学3年生のAさんは,友人のVさんと一緒に,男性アイドルグループのコンサートチケットの抽選に応募しました。
しばらくして結果を見たところ,Aさんは落選していた一方でVさんは当選しており,そのことをSNSで嬉しそうに報告していました。
このことをよく思わなかったAさんは,Aさんだと特定できないようなアカウントを用いて,Vさんに「家は○○だろ」「殺してやるから待っとけよ」などのダイレクトメッセージを送りました。
Vさんはこのことを両親に相談し,脅迫事件として緑警察署に被害届を出しました。
緑警察署の結果,Vさんにメッセージを送ったのがAさんであることが発覚し,Aさんは脅迫罪の疑いで取調べを受けることになりました。
事件のことを知ったAさんの両親は,弁護士から示談について話を聞くことにしました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
他人に対して何らかの害悪を与える旨告げた場合,脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪において害を加える対象とされている事項は,脅迫の相手方本人またはその親族の生命,身体,名誉,財産です。
そのため,これらの事項に害を加える旨の告知を行えば,脅迫罪が成立する余地が出てきます。
ただし,脅迫罪における「脅迫」と言うためには,様々な具体的事情を考慮して,客観的に見て一般人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
今回のケースでは,AさんがVさんに対し,家に行って殺害することを予告する内容のダイレクトメッセージを送っています。
このような行為は,少なくともVさんの「生命」に害を与える旨の「脅迫」と言えます。
そうすると,Aさんに脅迫罪が成立する可能性は高いでしょう。
【少年事件における示談の効果】
お子さんが犯罪をして取調べを受けることになった場合,ご両親としては「示談をして穏便に済ませたい」とお考えになるかもしれません。
ですが,少年事件,すなわち未成年が犯罪をしてしまった事件については,たとえ示談をしても事件にはあまり影響が及ばないと言っても過言ではありません。
以下では,少年事件における示談の効果について,少年事件の特徴と絡めて説明します。
少年事件の当事者である少年(20歳未満の者)は,心身が発達段階にあり,紆余曲折を経て心身ともに成熟していくものです。
この点を考慮し,少年が犯罪に及んだ場合については,成人とは異なる特殊な手続が行われるのが原則です。
少年事件の手続の最たる特徴は,最終的に行われるのが刑罰ではなく「保護処分」という少年の健全な育成のための処分であることです。
そのため,少年事件において焦点が当てられるのは,犯罪の内容や被害弁償の有無というよりも,それらを含む様々な事情から読み取れる少年の内面なのです。
ここで示談について簡単に触れておくと,示談というのは主に金銭による賠償を目的とする当事者間の合意です。
たしかに物理的損害の補填や慰謝料の支払いがされることは大事ですが,それが少年の内面に何らかの影響を及ぼさないのであれば,少なくとも少年事件においては意味がありません。
こうした事情から,少年事件において示談の効果は決して大きくないということになるのです。
逆に言うと,更生の意思が見られるなど少年の内面がプラスの方向になっていれば,示談が成立していないことはさして重要ではないと考えられます。
以上のように,少年事件は通常の刑事事件と異なる点が少なからず見受けられます。
ご不安であれば,ぜひ一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、個々の事件における示談の効果について丁寧に説明します。
お子さんが脅迫罪などを疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
誤振り込みから犯罪に?
誤振り込みから犯罪に?
誤振り込みされたお金を降ろして犯罪が成立しうるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件】
愛知県一宮市に住むAさんは自身の銀行口座にV名義の口座から約10万円の振り込みがあったことに気付きました。
身に覚えのなかったAさんですがつい出来心でこのお金を引き出し遊興費として使ってしまいました。
後日,誤振り込みをしてしまったことに気付いたVさんが銀行に問い合わせ銀行から一宮警察署に被害が届けられました。
Aさんは福岡県警察西警察署で事情を聞かれることになっています。
(フィクションです)
【誤振り込み】
誤振り込みされたお金を窓口で引き出した場合,詐欺罪が成立する可能性があります。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
判例(最決平成15・3・12刑集57巻3号322頁)は,被告人が自己の口座に誤振り込みがあったことを知りながら銀行に誤振り込みがあったことを告げず払い戻しを受けた事件について詐欺罪が成立するものとしました。
以下では,その理由をかいつまんで説明します。
前提として,誤振り込みにより金銭が振り込まれた受取人は,銀行に対して振り込まれた金銭を引き出すことを民事上請求できるとされています。
つまり,銀行としては,誤振り込みされた金銭であってもその引き出しを要求されたら応じなければならないということです。
そうすると,受取人は銀行に対して当然に誤振り込みされた金銭の引き出しを求めることができるとして,犯罪の成立は否定されるようにも思えます。
しかし他方で,誤振り込みの事実が発覚した際,銀行は誤振り込み前の状態に戻すべく様々な手続を行う必要があります。
受取人としても,誤振り込みの事実を知った以上はそのことを銀行に伝えるなど誠実に振る舞うべきだと言えます。
以上のような事情から,受取人には,振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があることが導かれます。
それにもかかわらず,受取人が誤振り込みの事実を隠してお金の引き出しを求めることは,言うべきことを言わずに相手方を騙す点で欺罔行為(刑法246条における「人を欺いて」の部分)に当たると評価できます。
そして,そのような行為により銀行の係員が正当な払戻しだという勘違いに陥り,金銭の払い戻しに応じれば,「財物」の「交付」もあったとして詐欺罪に当たるのです。
さて,以上の説明は,ATMでお金を降ろしたケースにおいては妥当しないと考えられています。
その理由は,詐欺罪は人を錯誤に陥れてこそ成立するものであって,ATMのような機械が相手なら錯誤が観念できないからです。
では,ATMで誤振り込みされたお金を降ろしても犯罪は成立しないかというと,そうとは考えられていません。
可能性のあるものとしては,電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)または窃盗罪(刑法第235条)のいずれかがだとする見解が有力です。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は詐欺罪と同様で,窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
【弁護活動】
Aさんから依頼を受けた弁護士は,事件のことをどのように警察に話したらよいのか,今後予想される手続はどのようなものか,考えられる弁護活動は何か,などをAさんに説明します。
今回のような詐欺事件ですと,有力な弁護活動として,やはり被害者との示談が挙げられます。
被害者との間で示談が成立し,処罰感情の軽減をアピールできれば,事件によっては不起訴処分を獲得できる可能性が出てくるでしょう。
今回のような誤振り込みのケースでは,示談を行うにあたって注意しておくべきポイントがあります。
それは,誤振り込みをして金銭を失った方だけでなく,誤振り込みされた金銭の引き出しに応じた銀行も被害者となりうることです。
なぜかというと,先ほど説明したように,理論的に詐欺罪の相手方となるのは銀行だからです。
ただ,だからといって,直ちに銀行と示談すべきかというとそうとも限りません。
この点については専門的で複雑なことが少なくないので,弁護士からアドバイスを受ける方が安心だと言えるでしょう。
謝罪や示談交渉が実を結ぶためには,場合によっては多くの時間がかかることもあります。
刑事事件はスピードが肝になることが多いので,事件の内容を問わず,早期から弁護士のアドバイスを受けておくことをおすすめします。
誤振り込みされたことを銀行に伝えずお金を使ってしまった方,詐欺事件の被疑者となってしまった方,一宮警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
強盗致死事件の弁護活動
強盗致死事件の弁護活動
強盗致死事件の弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件】
Aさんは深夜2時ごろ愛知県愛知郡所在のVさん宅に侵入し,宅内の金品を盗もうと考えました。
計画通りVさん宅に侵入したAさんは,高級腕時計や宝石類数点を得ました。
そして,AさんがVさん宅から立ち去ろうとしたところ,Vさんに発見されてしまいました。
Vさんは警察に通報しAさんを現場に取り押さえようとしたため,Aさんは近くにあった木刀でVさんを1回殴り逃走しようとしました。
暴行を受けたVさんは打ち所が悪く,搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは愛知警察署に住居侵入と強盗致死の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
【事後強盗から強盗致死傷罪へ】
強盗致死傷罪が成立し得るバリエーションにはどのようなものがあるのか,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
今回のケースでAさんは強盗致死の疑いをかけられています。
強盗致死の事実については,強盗致死罪(刑法第240条後段)の成立が検討されます。
刑法第240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致死傷罪が成立するためには,行為者が「強盗」でなければなりません。
ここでの「強盗」には,強盗罪(刑法第236条)の犯人のみならず,事後強盗罪(刑法第238条)や昏酔強盗罪(239条)の犯人も含まれます。
刑法第236条
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
強盗罪の構成要件は,財物や財産上不法の利益を得るために相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を行い,よって財物や財産上不法の利益を得たことです。
Aさんは高級腕時計や宝石類といった財物を得るために暴行・脅迫を行っていません。
よって,Aさんの行為は刑法236条が定める強盗罪には当たらないと考えられます。
しかし,財物を得たAさんは,Vさんから逃れるためにVさんを木刀で殴り,死亡させています。
この事実によって,Aさんが財物を得,Vさんや警察から逮捕されることから逃れるためにVさんに暴行を加えた一連の行為全体が,事後強盗罪として捉えられる可能性があります。
刑法第238条
窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。
さらに,Vさんを木刀で殴ったことが原因で死亡結果が発生していますので,強盗致死罪が成立する可能性があるということになります。
以上のように,強盗致死傷罪が成立する流れには
・強盗罪⇒強盗致死傷罪
という基本類型だけではなく,
・昏酔強盗罪⇒強盗致死傷罪
・窃盗罪⇒事後強盗罪⇒強盗致死傷罪
といったように,様々なバリエーションが存在します。
強盗致死傷罪は,強盗と死傷結果との間に一定の関連性があれば,殺人や傷害の故意の有無にかかわらず成立するとされています。
今回のケースにおいて,AさんにVさんを殺害する意思があったかどうかは分かりませんが,いずれにせよ強盗致死罪(強盗殺人罪)は成立する可能性があります。
強盗致死罪あるいは強盗殺人罪の法定刑は死刑または無期懲役なので,起訴され有罪判決を受けた場合は必ず実刑判決となります。
そのため,強盗致死罪の成立が考えられるケースでは,弁護活動によって可能な限り懲役の期間を短くすることが目標となるでしょう。
【弁護活動】
強盗致死事件や強盗致傷事件の被疑者から依頼を受けた弁護士は,被害者側と示談交渉を行い,一刻も早く依頼者に有利な内容で示談を成立させることを目指します。
被害者が死亡したケースでは一般的に示談が困難ですが,それでも弁護士を通じて誠心誠意アプローチしたことが裁判で評価される可能性はありうるでしょう。
また,事案の内容によっては,被疑者に適用されるべき罪名が本当に強盗致死傷罪なのかを争うことも考えられます。
たとえば,死傷結果が強盗とは無関係だとして強盗罪の成立を主張する,暴行・脅迫がさほど強くなかったとして恐喝罪の成立を主張する,などが考えられます。
事案次第では無罪の主張もありうるところでしょう。
そのような場合,弁護士としては犯罪があったというために必要な証拠が十分ではないことを示したり,他に真犯人と呼ぶべき人物がいることなどを証拠によって示します。
強盗致死傷罪は重い刑が定められていることから,起訴された場合は一般人が裁判員として関与する裁判員裁判となるのが原則です。
もしそうなれば,裁判員に対して職業裁判官に対するものとはまた違った働きかけをしていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所で,裁判員裁判に関するノウハウも事務所内で共有されています。
強盗致死傷罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が愛知警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留②
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留②
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留①の続きとなります。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときには、保護責任者遺棄罪が成立します(刑法218条)。
法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上5年以下の懲役です。
また、刑法218条の罪(保護責任者遺棄罪)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により、保護責任遺棄致死罪として処断されます(刑法219条)。
保護責任遺棄致死罪の場合,「傷害の罪と比較して、重い刑によ」るとは、傷害致死罪(刑法205条)と保護責任者遺棄罪(刑法218条)に定められた刑(法定刑)の上限及び下限を比較して、その重い方を選択するということを意味します。
保護責任者遺棄致死罪によってAさんが未成熟児(Vさん)を死亡させるに至った場合を見てみると、傷害致死罪(刑法205条)の下限は3年以上の懲役、上限は20年の懲役です(刑法205条・刑法12条)。
それに対して、保護責任者遺棄罪(刑法218条)の下限は3月以上の懲役、上限は5年以下の懲役です。
ここで、上述した傷害致死罪(刑法205条)と保護責任者遺棄罪(刑法218条)の下限及び上限について、それぞれ重い方を選択します。
したがって、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、下限が3年以上の懲役、上限は20年以下の懲役だと考えられます。
遺棄の意義
保護責任遺棄致死罪における「遺棄」は、①要救助者(要扶助者)の場所を移動させるという移置行為と、②保護しなければ生命の危険が生じ得る要救助者(要扶助者)を放置したまま立ち去るという置き去り行為をいうと解されています。
また、保護責任遺棄致死罪において「必要な保護をしなかった」とは、場所を移動させたり立ち去ったりするように物理的に離れずに、要扶助者に対し生存に必要な保護をしないという不保護行為をいいます。
ケースにおいて、Aさんは医師として未成熟児であるVさんを保護する必要があるにも関わらず、Vさんを放置したまま立ち去ったことから、置き去りによる遺棄が行われたといえます。
よって、Aさんには保護責任遺棄致死罪が成立すると考えられます。
以上より、Aさんには業務上堕胎罪と保護責任者遺棄致死罪が成立すると考えられ、愛知県北警察署による逮捕・勾留が行われたのだと考えられます。
ちなみに,AさんがVさんを殺すつもりで遺棄に及んだ場合,保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人罪に当たる余地が出てきます。
そうなった場合,殺人罪として法定刑の上限が死刑,下限が5年の懲役という非常に厳しいものになるおそれがあります。
勾留の要件と身柄解放活動
勾留とは、逮捕した被疑者の身柄を一定の事由がある場合に留置することをいいます。
その一定の事由とは、刑事訴訟法60条1項と87条1項に記載されている事由を指します。
具体的には、以下の①から③の全てに該当する場合に勾留が認められます。
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき
②次のうち最低でも1つに該当するとき
被疑者が定まった住居を有しない
被疑者が罪証を隠滅すると疑うにつき相当な理由がある
被疑者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
(上記①②をまとめて「勾留の理由」と呼ぶことがあります)
③勾留の必要があるとき
③については,その具体的な意味が日本語の一般的な意味とは少し異なる点に注意が必要です。
ここで言う「勾留の必要があるとき」とは,勾留の利益(たとえば円滑な捜査が行えること)と不利益(たとえば被疑者が会社に行けないこと)を比較し,不利益より利益の方が大きいことを指すと考えられています。
そのため,仮に①②に該当しても,勾留による不利益の大きさ次第では③が否定され,結果的に勾留されないということもありえます。
以上に対して、勾留中の被疑者の身柄拘束を解く刑事弁護活動には、
①勾留の理由または必要があると判断した裁判官の判断を争う準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)
②その後の状況の変化により、勾留の理由または必要がなくなったことを主張する勾留取消請求(刑事訴訟法87条)
③裁判官の職権による勾留の執行停止を求める活動
などが挙げられます。
また、この前提として、
④勾留された理由を公開の法廷において裁判官が告げることを求める勾留理由開示請求(刑事訴訟法82条)
も、勾留中の被疑者の身柄拘束を解く刑事弁護活動において重要な役割を果たします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、逮捕されている被疑者のもとに出向き、拘束されている身柄の解放に向けた刑事弁護活動を行っています。
業務上堕胎罪や保護責任者致死罪で逮捕された被疑者の身柄解放をお考えの方は、まずは刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご連絡ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留①
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留①
業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
ケース
愛知県名古屋市北区内の病院に勤務するAさん(医師)は、旧友のBさん(女性)から、母体保護法による適法な堕胎の期間を過ぎてしまっているにも関わらず、Bさんが妊娠している胎児の堕胎を依頼された。
Aさんが同病院内で堕胎を行った結果、母体外に胎児が排出されたが、Aさんの病院には保育器等の未熟児医療設備が整っており、堕胎により排出された未熟児(Vさん)は適切な処置を施せば生育可能な状態であった。
しかし、Aさんは、未成熟児を処置室にそのまま放置したため、未成熟児(Vさん)は死亡した。
その後、愛知県警北警察署の捜査によりAさんは業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪の容疑で逮捕され、またそれに引き続く勾留がなされた。
(この事例は、フィクションです。)
業務上堕胎罪と母体保護法
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときには、業務上堕胎罪が成立します(214条)
法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上5月以下の懲役です。
業務上堕胎罪における「堕胎」とは、①胎児を母体内で殺すか、あるいは、②自然の分娩期に先立って人工的に胎児を母体から分離・排出することです。
ケースでは、医師であるAさんが自然の分娩期に先立って母体外に胎児を排出しています。
そして,このような行為は妊婦であるBさんの依頼を受けて行っているため,「医師」が「女子の嘱託を受け」「堕胎」を行ったといえます。
そうすると,Aさんの行為は業務上堕胎罪に当たると考えられます。
ただし,形式的には業務上堕胎罪に当たる行為であっても,母体保護法が定める人工妊娠中絶に該当すれば不可罰となる余地があります。
まず,母体保護法2条2項は、「人工妊娠中絶」の定義について、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期(注:行政機関の通知によれば受胎後満22週間未満)に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出すること」と定めています。
そのため,第一にこの定義に該当することが必要となるでしょう。
そのうえで,母体保護法14条1条1号は、次の要件を満たす場合に限って適法に「人工妊娠中絶」を行えるとしています。
①医師会が指定した医師の手によること
②妊婦が次のいずれかに該当すること
・妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある
・暴行もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した
③妊婦と配偶者の双方が同意していること(ただし一定の場合は妊婦のみで可能)
以上の各要件を満たす場合には,適法な行為と評価される結果,業務上堕胎罪の成立も否定されるでしょう。
ケースでは、母体保護法による適法な堕胎の期間を過ぎています(受胎後満22週間を過ぎています)。
また、上記の身体的・経済的理由や倫理的理由は存在しないと考えられます。
したがって、適法な「人工妊娠中絶」とは見られず、Aさんには業務上堕胎罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上堕胎罪と保護責任者遺棄致死罪で逮捕・勾留された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部へご相談ください。
次回の記事では、業務上堕胎罪と保護責任遺棄致死罪で逮捕・勾留(後編)を解説します。
(無料法律相談のご案内はこちら)
名誉毀損罪で任意の取り調べを受けた
名誉毀損罪で任意の取り調べを受けた
名誉毀損罪で任意の取り調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
ケース
愛知県名古屋市瑞穂区の新聞社に勤めるAさん(45歳)は、愛知県内の選挙区から当選した国会議員であるVさん(40歳)に対し、かねてから自分の政治信念と一致しないことからVさんの人気に立腹していた。
そこで、Aさんは、Vさんについて綿密に取材を重ね、既婚者であるVさんが妻以外の複数の女性と交際関係にあると突き止めた。
Aさんは、Vさんは国民の代表たる政治家として不適切であると考え、取材情報を新聞に公表した。
一方、Vさんは自身の名誉が傷付けられたとして、愛知県警瑞穂警察署に告訴した。
その後の愛知県警瑞穂警察署の捜査の結果、Aさんは名誉毀損罪の容疑で任意の取り調べを受けるに至った。
Aさんは、「自分は正しいことをしたのではないか」と考え、自身を弁護してくれる法律事務所を探している。
(この事例はフィクションです。)
名誉毀損罪の成立
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者には、名誉毀損罪が成立します(刑法第230条第1項)。
法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ、検察官は起訴することができません。
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
しかし、親告罪について告訴の提出がされていない場合でも、告訴の可能性の有無や事案の大小から慎重に判断した上で犯罪の捜査を開始することは可能であると解されています。
ケースでは、名誉毀損罪の被害者であるVさんが、愛知県警瑞穂警察署に告訴していることから、検察官が起訴することは可能であると考えられ、また、愛知県瑞穂警察署の捜査も適法であると考えられます。
名誉毀損罪が不可罰になる場合
名誉毀損罪として規定されている行為(「公然と、事実を摘示」する行為)が
①公共の利害に関することに係り、
かつ、
②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合
には、
③事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき
は、これを罰しない(名誉毀損罪は成立しない)とされています(刑法第230条の2第1項)。
さらに、名誉毀損罪として規定されている行為(「公然と、事実を摘示」する行為)が、公務員又は公選による公務員の候補者に関す事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しないとされています(刑法第230条の2第3項)。
つまり、名誉毀損罪が不成立となる条件(①、②、③)のうち、③が満たされれば基本的に不可罰となります。
このように①②の要件が不要となる理由は,公務員に対する批判の自由の保障を徹底すべきだという考えに基づきます。
そのため,公務員の身分を持つ者に関する事実であれば何でもいいとまでは考えられていません。
ケースにおいてAさんが公表した情報は、国会議員であるVさんが妻以外の複数の女性と交際関係にあるというものです。
このこと自体はVさんのプライベートに関わる事柄ですが,Vさんは国民の代表たる国会議員としての資質が問われる立場にあると言えます。
そうすると,Aさんが公表した内容は「公務員…に関する事実」だと考えられます。
Aさんの公表した内容が「公務員…に関する事実」である以上,その内容が真実だと証明できれば名誉毀損罪は成立しない可能性が高いです。
それでは,仮に真実だと証明できなかった場合,Aさんには名誉毀損罪が成立することになるのでしょうか。
この点については,確実な資料・根拠に基づく相当な理由によって真実だと誤信したのであれば,責任を問うべきではないとして名誉毀損罪の成立が否定されると判断した裁判例が存在します。
この裁判例に従えば,仮にAさんが公表した情報の真実性を証明できずとも,真実だと信じたのが相当な理由によることを理由に名誉毀損罪の成立を否定する余地があるということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件のみを専門に扱う法律事務所として、名誉毀損罪に関する刑事弁護も自信をもってお受けいたします。
名誉毀損罪で任意の取り調べを受けた場合は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談下さい。
(無料法律相談のご案内はこちら)
傷害のつもり(故意)はなかったのに傷害罪で逮捕
傷害のつもり(故意)はなかったのに傷害罪で逮捕
傷害のつもり(故意)はなかったのに傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
ケース
会社員のAさん(25歳)は、職場において同僚の目の前で上司のVさんから激しい叱責を受けた腹いせに、Vさんの帰宅時を待ち伏せし、愛知県名古屋市守山区の周辺の雑居ビルの隙間から石を投げて脅かしてやろうと考えた。
しかし、意外にもこれがVさんに当たり、かつVさんは転倒して後頭部を打って全治2週間の怪我を負った。
その後、Vさんは愛知県警守山警察署に被害届を提出した。
その際、実はVさんがAさんの投石行為を目撃していたことから、後日Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなった。
Aさんは、「自分は石を投げて脅かしてやろうと考えただけだ。Aが転倒して怪我をさせてやろうなんて考えなかった。」と主張している。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市守山区周辺の法律事務所に法律相談を検討している。
(この事例はフィクションです。)
傷害の故意がなかった場合にも傷害罪が成立するのか
人の身体を傷害した者には、傷害罪が成立します(刑法204条)。
法律に定められた刑(法定刑)は、15年以下の懲役又は50年以下の罰金です。
傷害罪における「傷害」(刑法204条)とは、身体の生理機能の障害を意味すると考えられています。
これには、怪我をさせることは当然、病気や精神衰弱状態に陥れることも含まれます。
事例では、Aさんは後頭部の打撲という怪我を負っていますので、結果としては「傷害した」といえます。
ここで、刑法38条1項は、故意犯を原則とし、過失犯は「法律に特別の規定のある場合」に限って例外的に処罰することとしています。
確かに、傷害罪の成立においても,傷害罪の故意が必要と考えるのが自然のようにも思えます。
しかし、暴行罪(208条)の条文を見ると、暴行を加えた者が人を「傷害するに至らなかったとき」に暴行罪が成立するとされています。
この条文を素直に読むと,暴行を加えて結果的に傷害が生じた場合,「傷害するに至らなかった」とは言えないことから暴行罪は適用できないということになります。
ここでもし故意が欠けることを理由に傷害罪も成立しないとすると,次に適用が考えられるものとして過失傷害罪が挙げられます。
ですが,過失傷害罪は法定刑が著しく軽く,故意の暴行により傷害が生じたケースで科すべき刑としては軽すぎる感が否めません。
そのため,暴行の故意があった以上は傷害罪の適用を認めてもよいとする見解が支配的になっているのです。
ケースにおいて、確かに、Aさんの「自分は石を投げて脅かしてやろうと考えただけだ。Aが転倒して怪我をさせてやろうなんて考えなかった。」という主張では、Aさんは投石行為によりVさんに怪我をさせるつもりはなかったのでしょう。
しかし、暴行罪を犯すつもり(故意)で行為に及べば傷害罪を適用する余地はあるので,Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と傷害罪の法定刑の違いについて
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(刑法208条)。
これに対して、傷害罪の法定刑は、上述の通り、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法204条)。
懲役とは、刑事施設において所定の作業を伴う拘置をいいます。
罰金とは、1万円以上の金銭を国庫に納付することを指します。
拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設における拘置をいいます。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を国庫に納付することを指します。
したがって、暴行罪が成立すると、2年以下の懲役(上限)から1000円以上の科料(下限)までの範囲で刑が定まることになります。
一方、傷害罪が成立すると、15年以下の懲役(上限)から1万円以上の罰金(下限)までの範囲で刑が定まることになります。
このように暴行罪と傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は大きく異なります。
この場合、傷害事件において、適切な刑事弁護活動がなされないまま判決が下された場合に被疑者・被告人が被る損害は、暴行事件に比較して大きくなります。
このため、たとえAさんに暴行罪ではなく傷害罪が成立し得るとしても、起訴された場合の適切かつ妥当な判決獲得のためには、刑事事件に強い弁護士による強い刑事弁護が依然として必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、24時間対応の法律相談受付で行っています。
フリーダイヤルにご連絡いただくか、弊所ホームページ上のお問合せフォームより必要事項をご記入ください。
フリーダイヤルにご連絡いただくと、対応スタッフが傷害事件の事情をお伺いし、ご来所の日時を調整して予約をお取りします。
その後、事務所にて担当弁護士との法律相談が可能となります。
初回無料法律相談のご予約は、0120―631-881までご連絡ください。
傷害のつもり(故意)がなかったのに傷害罪で逮捕された場合は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談下さい。
(無料法律相談のご案内はこちら)