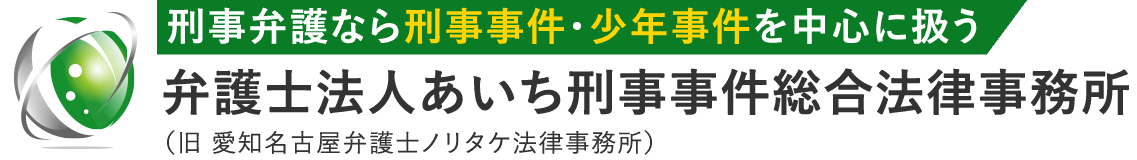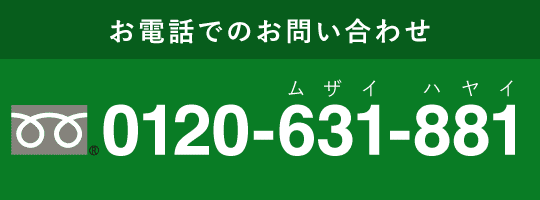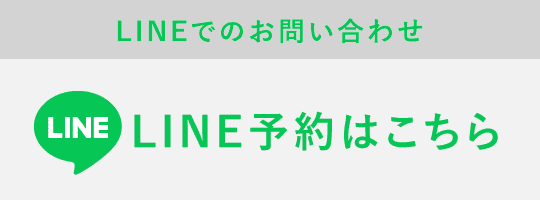Author Archive
愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)
愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(上記は前回までと同様)
今回は第4条(ダフ屋行為の禁止)を解説していきます。
~ダフ屋行為と各種法令~
愛知県迷惑行為防止条例第4条はダフ屋行為の禁止を規定しています。
ダフ屋行為とは以下の2つの行為を指し,いずれか片方でも行うと、ダフ屋行為として愛知県迷惑行為防止条例違反となります。
・チケット類を転売目的で公共の場所または公共の乗物で購入し,または購入しようとすること
・公共の場所または公共の乗物で転売し,または転売しようとすること
ここでいうチケット類とは乗車券,急行券,指定券,寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券,観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物と規定されています(第4条)。
罰則は各都道府県によって異なりますが愛知県の場合は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
ダフ屋行為は都道府県の条例以外にも各種法令によって規制される場合がありますので併せて説明していきたいと思います。
日本の民法では契約の自由が原則となっています。
その為,ダフ屋が購入者にチケット類を販売しても契約の自由の原則から適法なようにも思われます。
しかし,ダフ屋行為はチケット類を不当に高値で売り付けたり,盗品や偽造のチケット類を流通させたり,虚偽告知や強要的要素が強く公序良俗に反する行為とみなされています。
また,ダフ屋行為は暴力団などの反社会的勢力の資金源となっていたこともあり,契約自由の原則を適用せず,取り締まりの必要があるとされています。
ダフ屋行為の規制が一番最初に盛り込まれた条例は1962年の東京都迷惑防止条例だと思われます。
しかし,ダフ屋行為が禁じられたのは戦後食糧難の時代において,配給券の買い占め行為が存在し,放置すれば餓死者が発生する恐れがあったため,時代に要請され緊急に取り締まる必要があったためといわれています。
その際には物価統制令という勅令を使用しダフ屋行為を取り締まっていました。
また,1957年の事件では最高裁判所が「ダフ屋」と名指しして処断をした例もあります(昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決)。
物価統制令では「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格での売買を禁止しており,違反すると10年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
近年でも,ダフ屋行為を条例で規制されていない都道府県でダフ屋行為を規制するために物価統制令が用いられた事件も存在します(1997年の京都府)。
大量に反復継続してチケット類を転売した場合古物営業法違反となる場合があります。
チケット類を含む証票券類も古物営業法の古物に該当するためです。
なお,町中にある金券ショップはすべて営業許可を取得しています。
さらに,チケット類購入時の規約に違反して転売目的でチケット類を購入した場合,詐欺罪に問われる可能性もあります。
最近では購入サイト等で会員証や本人確認書類の提示を求められる場合がありますが,他人の会員証や本人確認書類を用いて購入した場合にも詐欺罪に該当します。
加えて,これら会員証や本人確認書類が他人の物ではなく,偽造・変造したものであった場合,文書偽造罪に問われる場合もあります。
また,近年では,インターネットの普及によりインターネットオークションやチケット転売サイト等でのチケット類の転売事件が多くなっています。
インターネットオークションやチケット転売サイトを利用した場合,転売目的や営業性,反復継続性によっては都道府県条例以外にも各種法令の適用により検挙,逮捕される場合があります。
インターネットオークション等が「公衆の場」に該当するかどうかは定まった見解が存在しませんが、迷惑行為防止条例の「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」が適用された事例も多くあり,古物営業法違反や詐欺罪に問われたケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ダフ屋行為をし,検挙・逮捕されないか不安,お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(法律相談:初回無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
瀬戸市の殺人罪事件
瀬戸市の殺人罪事件
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、先日上司Vさんからこっぴどく叱られたことに憤りを覚え、殺してやりたいと思っていた。
そんな中、上司のVさんにコーヒーを淹れるように頼まれたBさんが、給湯室でコーヒーを入れた後目を話した隙に、Aさんはそのコーヒーに毒を盛った。
コーヒーに毒薬を入れられたことを知らないBさんは、そのままコーヒーをVさんに渡し、その結果コーヒーを飲んだVさんは毒により死亡した。
(フィクションです)
~関節正犯とは~
上記のケースでは、Vさんを殺そうとしてコーヒーに毒を持ったのはAさんですが、実際に毒入りのコーヒーをVさんに渡したのはAさんではなくBさんです。
この点、事情を知らない他人を利用して犯罪を遂行した場合、実行した者(Bさん)は利用者(Aさん)の「道具」に過ぎないと考え、利用者が罪責を負います。
この利用者は刑法上「間接正犯」と呼ばれます。
ただし、殺人罪だけではなく、犯罪における実行行為は、通常行為者自らの手で行われる(直接正犯)ため、上記のケースのような間接正犯において、どのような場合に殺人罪の実行行為がAさんにあったと認められるのかが問題となります。
この点、実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為のことをいいます。(殺人罪でいえば、人の生命を奪う危険性を帯びた行為ということになります。)
とすれば、他人を自己の意のままに使って、その動作や行為をあたかも一種の道具として自己の犯罪に利用する場合であって、当該構成要件の予定する法益侵害の現実的危険性があれば、自ら手を下してその実行行為をしたのと同一に考えることができると考えられています(道具理論)。
そこで、間接正犯の実行行為性が認められるためには、
①主観的には、行為者は、故意のほかに、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること
②客観的には、行為者が、被利用者の行為を道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部又は一部を行ったこと
が必要とされます。
上記のケースでは、AさんはVさんを殺すつもりでコーヒーに毒を盛っています(①)。
また、BさんがVさんの元へコーヒーを持っていく機会を利用し、毒を盛ったコーヒーを運ばせ、その結果Vさんは死亡しています(②)ので、Aさんには殺人罪の間接正犯としての実行行為性が認められる可能性が高いです。
そして、当然何もしらずコーヒーを運んだBさんは、殺人罪の故意がないため無罪となります。
~無実を主張するために~
しかし、理論上Bさんが無実であったとしても、実際にはBさんにも嫌疑がかけられることが予想されます。
そのような場合、捜査機関の取り調べに対してどのような供述をするのかが、その後の展開を大きく左右することになります。
捜査機関としては、嫌疑を掛けている以上、時には自白するよう迫ったり、被疑者としては認めていないつもりでも、認めているような内容の調書を取られてしまうことがあります。
仮に、虚偽の自白をしてしまった場合、後々虚偽の自白だったと主張したとしても、供述の信用性の低下につながってしまう恐れが出てきてしまい、被疑者にとって不利に働くことが予想されます。
そこで、殺人罪といった刑事事件で無実を主張する場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士から、取り調べでどのように対応すべきがアドバイスを受けることで、虚偽の自白や事実とは異なるな内容の供述調書を作成されてしまうリスクを軽減することが可能です。
また、弁護士が早期に弁護活動を開始することが出来れば、被疑者・被告人の方や事件関係者の方の話を聞いたり、事件を詳細に調査して無実の証拠を集め、裁判所や検察官に主張することで無罪判決・不起訴処分の可能性を高めることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は依頼者の方の利益を守るため迅速丁寧な活動を行います。
瀬戸市で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無実の主張をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見:39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)
愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)
~いわゆる迷惑行為防止条例とは~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(上記内容は前回までと同様)
今回は第3条以下を解説していきます。
~押し売り行為等の禁止~
第3条1項は押し売り行為等を禁止しています。
条文は以下のようになっています。
第3条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。
古典的な押し売りは,「刑務所から出て来たばっかなんだけど買ってくれないか」等と言って物品を購入させるものです。
「刑務所から出てきた」という言葉は1号の犯罪の前歴を告げる行為になります。
そして,一般人はそのように言われた際,「買わないと何かされるかもしれない」と不安になるでしょう。
また,買うまで帰らないといった居座るタイプも典型的な押し売りにあたります。
上記のような押し売り行為を愛知県内で行ってしまった場合、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
そして、3号の身分や物品の内容を誤解させるような表示または言動の場合,場合によっては愛知県迷惑行為防止条例ではなく、特定商取引法違反にとわれる場合もあります。
~キャッチセールスに関する規制~
第3条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に対して売買等を行うに際し,不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし,又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。
こちらは,路上などのいわゆるキャッチセールスなどに対する規制を規定しています。
キャッチセールスなどの場合でも,内容その他の事実を誤解させるような表示または言動があった場合,その内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となる場合があります。
~役務提供の押し付けの規制~
第3条3項 何人も,依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工,広告の掲載,遊芸その他の役務の提供を行なつて,その対価をしつように要求してはならない。
こちらは相手方の承諾なしに役務の提供(サービスの提供)をし,その対価をしつように要求することを禁止しています。
押し売りは物品が対象となりますが,第3条3項はサービスの押し売りに対する規制です。
こちらは内容その他の事実を誤解させるような表示や言動の有無は関係なく,対価を執拗に要求することそのものが禁止されています。
~電話販売等の規制~
第3条の2 何人も,物品を売買する目的で,売買の当事者となるように,電話,電報又は郵便の方法により誘引するに際し,その目的を偽り,又は秘してはならない。
こちらは電話等でのセールスの際に、「売るつもりはない」等と言いつつも、実際には物やサービスの販売をするといった行為を禁止しています。
具体的には、アンケートや何らかの調査であると偽って商品を購入させるケースが多いようです。
こちらも、内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となります。
愛知県迷惑行為防止条例第3条は、特定商取引法によって規制されている行為態様と類似している部分が多くあります。
押し売りやキャッチセールス等に対し,特定商取引法で対処することが難しい場合に愛知県迷惑行為防止条例によって規制することが目的であると考えられます。
次回はダフ屋行為等の禁止について解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反を犯してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)
愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(以上は前回の記事と同様)
今回は第2条の3の「嫌がらせ行為の禁止等」について解説していきたいと思います。
~第2条の3,嫌がらせ行為~
愛知県内おけるストーカー事案は,年々増加しています。
事案の中には,ストーカー行為をしていながら恋愛感情を否定し,ストーカー規制法の適用を免がれようとする事案や,そもそも恋愛感情を伴わない妬み、恨みなどの悪意の感情から外形的にはストーカー行為と同様のつきまとい、押し掛け等の行為を執拗に繰り返す陰湿な事案も発生しております。
ストーカー行為規制法は第2条第1項でつきまとい等を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と規定しています(具体的な行為の内容は後述します)。
そのため,恋愛感情に起因しない,人間関係のこじれから生じた恨みなどからストーカー行為をした場合にはストーカー行為規制法の対象とならず、他の法令に違反していない場合,検挙ができないという状況でした。
そこで,愛知県迷惑行為防止条例を改正し,新たに「ストーカー行為規制法第2条第1項に規定する目的を除くほか,正当な理由なく,専ら,特定の者に対する妬み,恨みその他の悪意の感情を充足する目的で・・・(以下略)」という第2条の3を追加しました。
愛知県迷惑防止条例およびストーカー規制法が規制している行為は以下になります。
ただし,以下1 – 4と,5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とストーカー規制法で規定されており(2条2項),愛知県迷惑行為防止条例でも同様であるといえるでしょう。
1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
また,愛知県迷惑行為防止条例では嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら,その者に対し,当該嫌がらせ行為の相手方の氏名,住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報を提供することを禁止しています。
愛知県迷惑行為防止条例およびストーカー規制法の規制する内容は基本的には同一ですが,その行為の目的によってどちらで検挙されるかが変わります。
~弁護活動~
ストーカー行為規制法および愛知県迷惑行為防止条例2条で規制されているつきまとい行為はどちらも1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ストーカー行為規制法や愛知県迷惑防止条例2条の3違反の場合,まずは被害者の方との示談を試みます。
被害者の方に謝罪し,同様の行為をしないように,今後,被害者の方や職場等に近付かない,電話やメール等も一切しないという約束をします。
そして慰謝料の支払いや上記の約束,可能であれば加害者を許すという事項も盛り込んだ示談書を作成していただきます。
そういった示談書を提出することで,起訴猶予処分や略式手続き,執行猶予付き判決となる可能性が高くなります。
まずはお近くの刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為をしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
誤振り込みから詐欺罪に
誤振り込みから詐欺罪に
~ケース~
岡崎市在住のAさんは、自分の銀行口座の残高に身に覚えのないお金が振り込まれていることに気付いた。
Aさんは誰かが間違って振り込んでしまったのだろうと思いながらも、お金に困っていたことからこのお金を引き出し、生活費に充ててしまった。
誤振り込みをしてしまったことに気付いたVさんが銀行に連絡をし、銀行が愛知県警察岡崎警察署に被害届を提出した為、後日Aさんは愛知県警察岡崎警察署で取調べを受けた。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~誤振り込みを告知しなかった場合~
上記のケースと似た事案において、最高歳は被告人に詐欺罪を認定しています。(最高裁判所決定平成15年3月12日)
詐欺罪については、刑法第246条において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、詐欺罪が成立するためには、相手を騙してお金や物を交付させることが必要です。
上記のケースにおいて、Aさんはたまたま自分の口座に入ったお金を使っただけなので、Vさんを騙している訳ではありませんが、このような場合でも詐欺罪が成立するのでしょうか?
この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
その為、Aさんは誤振り込みされたお金だと知りつつATMからお金を引き出しているので、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~詐欺罪における示談交渉~
弁護士としては、詐欺罪において事件を早期に解決し、前科を回避するためには、ます不起訴処分の獲得を目指すことが多いです。
そして、被害者に金銭的な損失を与えてしまう詐欺罪においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を目指す上で重要となります。
ただし、上記のケースにおいて、実質的に損害を被っているのはVさんですが、詐欺罪における欺罔を受けたのは銀行となります。
そのため、弁護士としては、示談交渉のなかでVさんに被害弁償をするだけではなく、銀行側にも謝罪し、被害届の取り下げてもらうよう交渉していくことになります。
その結果、仮に示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
ただし,示談交渉をする場合,被疑者・被告人と直接話すことを嫌がる被害者も多く、特に銀行などは直接本人が謝罪の申し出をしても取り合ってくれない可能性が高いです。
そして、詐欺罪のように、被害者を騙して損害を負わせてしまったような場合、被害者側の怒りが強いことも予想されます。
その為,詐欺罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てることをお勧めします。
弁護士であれば、被害者側も安心して話を聞いてくれるケースも多く、示談交渉が迅速かつ円滑に進むことが多いです。
また、被害者の連絡先が分からないような場合、捜査機関も犯人には被害者情報を教えられなくとも、弁護士限りであれば取り次いでくれることが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、詐欺罪や示談に関して安心してご相談下さい。
岡崎市で詐欺罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用 39,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(ここまでは前回と同様)
今回は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2,1項2号以下の「盗撮」および「卑わいな言動」について解説していきたいと思います。
~卑わいな言動~
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
前三号とは,前回説明した1号の「痴漢」,および後ほど説明する二,三号の「覗き・盗撮」を指します。
どういった行為が「卑わいな言動」といえるのかは条文からははっきりとわかりません。
卑わいな言動に当たるかどうかが問題となった事件として最高裁平成20年11月10日決定があります。
この事件は女性の後ろからスマートフォンで撮影したもので,ズボンを着用した臀部を撮影することが迷惑行為防止条例のいう「卑わいな言動」に当たるかが争点となりました。
最高裁の多数意見は「被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえる」として卑わいな言動に当たるとしました。
その他の事件では,性器を模した作り物を見せつけたり,下半身を露出しようとした事件などで卑猥な言動だとされました。
なお,実際に露出した場合には刑法の公然わいせつ罪や軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
~覗き・盗撮~
愛知県迷惑行為防止条例違反事件の多くが痴漢および盗撮です。
盗撮および覗き行為は第2条の2,1項二号および三号,2項,3項に規定されています。
第2条の2
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
今回の改正で学校の教室や会社の便所,ネットカフェやカラオケ等の個室。更衣室,タクシーや貸し切りバス,住居やホテルの居室なども愛知県迷惑行為防止条例における覗き・盗撮の規制場所となりました。
近年のスマートフォンの発達・普及により盗撮行為がされる場所が増加し,新たに規制する必要がでてきた影響と思われます。
また,実際に撮影できなくても,盗撮目的でカメラを設置することやカメラを向ける行為そのものが盗撮行為として規制されるようになりました。
また,改正前は「公衆が利用できる場所」という要件があったため,住居の浴室などを撮影しても盗撮とはなりませんでした。
今回の改正により,学校,会社などのトイレや住居の浴室なども規制場所となりました。
なお,改正前は軽犯罪法違反とせざるをえませんでした。
次回は嫌がらせ行為について解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
数回に分けて,愛知県迷惑行為防止条例の具体的な内容を解説していきたいと思います。
~第1条~
第1条では条例の目的を定めています。
第1条 この条例は、県民、滞在者等に著しく迷惑をかける行為を防止し、もってその平穏な生活を保持することを目的とする。
条例や法令の多くは第1条に制定目的を第2条で用語の定義などの規定を定めている場合が多いです。
愛知県迷惑防止条例は愛知県の条例ですので愛知県内のみで有効です。
もちろん、他都道府県の方が愛知県内にいる場合にも適用されます。
~第2条~
第2条では粗野または乱暴な行為の禁止を定めています。
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼、又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
第2条ではいいがかり等の刑法の暴行罪とはならない粗暴な行為などを規制しています。
2項はイベント会場などでイベントに対する抗議としてイベントを中止させようとするような行為をした場合に問われることがあります。
3項は刃物,鉄棒,木刀などのいわゆる凶器を「見えるように」持ち歩くことを規制しています。
これらの凶器を「隠して」持っていたような場合には軽犯罪法1条2号違反となります。
~第2条の2~
第2条の2は卑わいな行為の禁止を規定しています。
卑わいな行為とはわかりやすくいうと,痴漢および盗撮のことをいいます。
愛知県迷惑防止条例違反事件の多くは痴漢または盗撮事件です。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
この規定はいわゆる痴漢に関する規定です。
公共の場所または公共の乗物とは第2条に規定されています。
痴漢行為は刑法に規定があるものではなく,各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されています。
条文に書かれているように「痴漢」となるのは人の身体に衣服等の「上から」触れた場合です。
衣服の中に手を入れて触れるような場合には刑法176条の強制わいせつ罪となります。
また,公共の場所または公共の乗物ではないプライベートな空間であれば、愛知県迷惑防止条例のいう痴漢にはあたりませんが、状況次第では強制わいせつとなる場合もあります。
次回は第2条の2,1項第2号の「盗撮」以降を解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で示談なら
器物損壊罪で示談なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、社内で日頃よく言い合いになる後輩Vさんを困らせてやろうと思い、Aさんの社内用サンダルを盗み、近くのコンビニのゴミ箱に捨てた。
偶然、AさんがVさんのサンダルを捨てるところを目撃したBさんがVさんにそのことを話したため、VさんはAさんに文句を言い、被害届を出すことも考えている旨伝えた。
何とか刑事事件化を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~物を盗んでいるのに器物損壊罪に~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんのサンダルを盗み取っていますので、窃盗罪が成立するようにも思えます。
ただし、他人の物を盗んだからといって、全てが窃盗罪に問われるわけではありません。
窃盗罪が成立するためには、盗んだ物を自分の物にしようとする意思が必要だとされています(不法領得の意思)。
上記のケースのように、初めから物を壊そうとしていたり、捨てる意志で物を盗んでも窃盗罪とはなりません。
上記のケースのAさんも、端からサンダルを捨ててVさんを困らせることが目的で不法領得の意思がありませんので、窃盗座は成立しません。
では、Aさんはなんの罪に問われるかというと、器物損壊罪が成立すると考えられます。
器物損壊罪については、刑法第261条において、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」とされています。
その為、物を叩き割るような物理的損壊だけではなく、上記のケースのように物を捨てる行為も「損壊」にあたると考えられます。
~示談で刑事事件化回避~
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
その為、器物損壊罪のような親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの器物損壊罪のように、相手を困らせる目的で行ってしまった犯罪の場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日頃から刑事事件のみ受任している弁護士が多数在籍しておりますので、器物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
豊田市で器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をして刑事事件化を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用 40,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
犬山市の盗品関与罪なら
犬山市の盗品関与罪なら
~ケース~
犬山市に住むAさんは、友人のBさんから新品のゲーム機を買わないかと持ち掛けられた。
Bさんが提示した売値が、市場価格の4分の1の値段だったため、何故そんなに安いのか不審に思いながらも、以前から欲しかったゲーム機だった為、購入した。
その後、愛知県警察犬山警察署の警察官により、Bさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、ゲーム機が盗品だったのだと悟り、自分も何か罪に問われるのではないかと不安になったため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~盗品関与罪が成立するためには~
他人が盗んだ物を譲り受けたり、保管したり、運搬したり、あっせんした場合には盗品関与罪となります。
盗品関与罪は、実際に窃盗を行った人を盗品の保管や換金などにより後発的に援助することを罰する規定です。
盗品関与罪については、刑法第256条に規定されており、第1項では無償の場合、第2項では有償の場合について規定されています。
第1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
このように、無償譲り受け以外の盗品関与罪は、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い法定刑が設定されています。
ただし、盗品を譲り受けてしまえば必ず盗品関与罪に問われるわけではなく、故意がないと盗品関与罪は成立しません。
盗品関与罪については,行為者が関与した物品が盗品などであることを認識していることが必要ですが、具体的な犯人や被害者を特定していることまでは不要だとされています。
そして、盗品の譲受や保管などを行った者が,本犯者(実際に物を盗んだ人)と意思の連絡が無かったような場合でも、盗品関与罪は成立すると考えられています。
上記のケースにおいて、AさんはBさんから買い取ったゲーム機が値段が安すぎることに不信感を抱いてはいるものの、盗品だと言うはっきりとした認識はありませんので、盗品関与罪は成立しない可能性が高いです。
ただし、盗品であることを知ることが出来た蓋然性が高い場合、捜査機関から嫌疑をかけられてしまう可能性はあります。
現実には,結果として盗品だと知っていたかどうかがハッキリと判明しないケースが多いようです。
~不起訴処分を目指す弁護活動~
盗品関与罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することがまず考えられます。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。
上記のケースのように、犯罪の故意の有無が問題になる場合、不起訴処分を目指すためには、捜査機関の取り調べに対しどのような供述をするかがとても大切になります。
時には、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、盗品関与罪に問われたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの際のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件双方法律事務所では刑事事件に強い法律事務所です。
犬山市で盗品関与罪に問われてお困りの方、不起訴処分の獲得を目指される方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは無料法律相談をご希望の方は0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署の初回接見費用 38,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
信号無視で危険運転致死罪に
信号無視で危険運転致死罪に
~ケース~
通勤のため愛西市内の道路を車で走行していたAさんは、始業時間に遅刻しそうだった為、焦っていた。
そのため、普段から人や車の往来が少ない交差点に差し掛かった際、信号を見ることなく交差点に進入したところ、横断歩道を通行中のVさんと接触した。
その結果、事故から数時間後にVさんは死亡した。
事故現場に駆け付けた愛知県警察津島警察署によって、Aさんは逮捕され、被疑罪名は危険運転致死罪だと聞かされた。
危険運転致死罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、今後がとても不安になり、家族を通じて刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~危険運転致死罪とは~
危険運転致死傷罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死傷させた場合に適用される罪で、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されています。
その法定刑はとても重く設定されており、危険運転致傷罪の場合は15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は1年以上の有期懲役と規定されています。
同条には、危険運転にあたる行為として、以下の6つを挙げています。
① アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
② その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③ その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤ 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥ 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記のケースのような信号無視運転による交通事故は⑥に当たりますが、危険運転致死罪が成立するためには、「赤色信号を殊更に無視した場合」にあたることが必要です。
「赤色信号を殊更に無視した」とは、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
その為、単に過失によって赤信号を見逃してた場合には危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪(7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金)に問われることになり、法定刑は軽くなります。
~刑の減軽を求める活動~
上記のケースでは、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪であることを主張することも刑を軽くする方法のひとつです。
そのためには、例えばAさんが信号を無視したのではなく見落としたといえる客観的な証拠を集め、主張していくことが考えられます。
また、危険運転致死罪となる場合でも、刑の減刑を求めていくことも可能です。
例えば、Aさんが事故後被害者であるVさんに積極的に応急処置をし、救急車を呼んでいたり、事故後遺族に対して謝罪や被害弁償をしっかりと行っていれば、裁判ではそういった事情を考慮され、刑が減軽される可能性が高まります。
そして、このような被疑者・被告人にとって有利となる事情を効果的に捜査機関や裁判官に主張していくためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が裁判官や検察官に情状酌量を訴え、刑の減軽を目指します。
愛西市内で危険運転致死罪に問われてお悩みの方、刑の減軽を目指される方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用 37,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。